
「事業を新たな市場へ広げたい!」と考えている中小企業経営者の方必見です。
中小企業新事業進出促進補助金は、「事業再構築補助金」の後継制度として2025年4月22日に公募がスタート。
新しい市場や高付加価値事業への挑戦を、最大9,000万円・補助率1/2で後押しします。
この記事では、初めての方でもわかりやすく、申請のポイントや注意点を最新情報とともに解説します。
目次
1.中小企業 新事業進出促進補助金とは?
中小企業新事業進出補助金は、既存ビジネスとは異なる分野・市場に踏み出す中小企業を資金面からサポートする制度です。
高付加価値な新製品・サービスで新市場に進出し、企業全体の生産性と収益を押し上げ、その成果を従業員への賃上げにつなげていく
―そんな“攻めの投資”を後押しするのが目的です。
公式HPはこちら
▶中小企業 新事業進出補助金
2.補助対象者
原則、日本国内に本社・事業拠点がある中小企業が対象です。
※製造業やサービス業、小売業など各業種に応じた資本金や従業員数の要件があります。
補助対象外となる事業者(一部代表的なものを紹介)
①応募申請時点で従業員数が0名の事業者
②新規設立・創業後1年に満たない事業者
③中小企業 新事業進出促進補助の申請締切日(第1回の場合はR7.7.10)を起点にして16カ月以内に、以下の補助金に採択された事業者、
又は、申請締切日(第1回の場合はR7.7.10)時点において、以下の補助金の補助事業実施中の事業者
・事業再構築補助金
・ものづくり補助金
④事業再構築補助金において採択の取り消しを受けた事業者
⑤事業再構築補助金の補助事業者のうち、「事業化状況・知的財産権報告書」が未提出の事業者
⑥事業再構築補助金の補助事業者のうち、「中小企業等事業再構築促進補助金(新市場進出)交付規定」第22条第1項1号、3号、5号、7号、10号、11号及び12号に基づく交付決定の取消を受けている事業者
など。詳しくは、公募要領または、専門家に問い合わせてください。
・応募申請時点で従業員数が0名の事業者
・新規設立・創業後1年に満たない事業者 は申請することが出来ません。
本補助金は、賃金引上げをを目的としていることから、従業員が0名の事業者は残念ながら対象となりません。
また、新規事業への進出を目的としていることから、創業間もない事業者は対象となりません。
申請時には、最低でも1期分の決算書の提出が必要とされています。
3.補助金の額と率
3-1.補助金額
補助金額の上限は、従業員数に応じて変わります。
| 従業員数 | 補助金額 |
| 従業員数20人以下 | 750万円~2,500万円(3,000万円)※ |
| 従業員数21~50人 | 750万円~4,000万円(5,000万円)※ |
| 従業員数51~100人 | 750万円~5,500万円(7,000万円)※ |
| 従業員数101人以上 | 750万円~7,000万円(9,000万円)※ |
※()内は、大幅賃上げ特例を適用した場合の上限額
3-2.補助率
一律で2分の1とされています。
また、交付決定時点で交付決定額の減額により、補助金額が750万円を下回ることとなった場合は、採択取消となります。
4.補助対象経費
経費として認められるのは、新しい市場に打って出る、または製品・サービスの価値を大きく高めるために使う費用だけです。
既存事業で利用したり、別の事業で使用する場合は補助の対象外となります。
大きく次のカテゴリーに分けられます。
それぞれ具体例と押さえておきたいポイントについて簡単に解説します。
| 経費区分 | 具体例 | 押さえておきたいポイント |
| 機械装置・システム構築費 (建物費といずれか必須) | 生産設備/検査装置/業務効率化システム/ECサイト構築/器具及び備品/工具など | 車両及び運搬具は対象外 |
| 建物費 (機械装置・システム構築といずれか必須) | ・生産施設/加工施設/販売施設/検査施設/作業場等の建設・改修にかかる経費 ・補助事業のために使用される建物に付随する構築物の建設にかかる経費 | ・建物の単なる購入や賃貸は対象外 ・構築物のみでの計上は不可 |
| 運搬費 | 運搬料/宅配/郵便料 | ・購入する機械装置等の運搬料は、機械装置・システム構築費に含む |
| 技術導入費 | 知的財産権等の導入に要する経費 | ・知的財産権を所有する他者から取得(実施権の取得を含む)する場合は書面による契約の締結が必要。 |
| 知的財産権等関連経費 | 特許権当の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続き代行費用や、外国特許出願のための翻訳料など | ・ただし、出願料、審査請求料、特許料等、日本の特許庁に納付する手数料は補助対象外 |
| (検査・加工・設計等に係る)外注費 補助上限:補助金額全体の10% | 補助事業遂行のために必要な検査、加工、設計等 | ・事業計画書に、外注先の概要及び、選定理由を記載する必要あり。 ・外注先との書面による契約の締結が必要。 |
| 専門家経費 補助上限:100万円 | 補助事業遂行のために必要な専門家経費 (学識経験者、兼業・副業、フリーランス等の専門家に依頼したコンサルティング業務や、旅費等の経費) | ・事業計画書に専門家の概略・略歴及び当該専門家からの技術指導や、助言が必要不可欠である理由を具体的に記載する必要あり。 |
| クラウドサービス利用費 | 専ら補助事業のために使用されるクラウドサービスの利用に関する経費(クラウドサービス・WEBプラットフォーム等の利用費) | ・自社の他事業と共有する場合は補助対象外 ・パソコン、タブレット端末、スマートフォンなどの本体費用は補助対象外 |
| 広告宣伝・販売促進費 補助上限:事業計画期間1年あたりの売上高見込み額(税抜き)の5% | パンフレット、動画、写真等の作成及び、媒体掲載、補助事業のPR等に係るWEBサイトの構築、展示会出展、ブランディング、プロモーションに係る経費 | ・補助事業実施期間内に広告が使用、掲載されていること、WEBサイトが公開されていること、展示館が開催されていること |
・「機械装置・システム構築費」または、「建物費」のいずれかが必ず補助対象経費に含まれなければなりません。
例えば、「広告宣伝・販売促進費」のみでの補助金申請は認められていません。
・汎用性があり、補助事業以外にも使用ができるもの(パソコン・プリンター・タブレット端末・スマートフォン・複合機・カメラ・書籍・家具家電、自動車等の車両)の購入費は対象外です。
5.申請するための主な要件
申請には、以下の要件を満たす必要があります。
| 要件 | 概要 |
| 新事業進出要件 | 既存事業と異なる新しい市場へ進出すること |
| 付加価値額要件 | 事業終了後3〜5年間で付加価値額を年平均4%以上向上させること |
| 賃上げ要件 | 給与支給総額または一人当たり給与を一定基準以上に引き上げること(未達成時返還義務あり) |
| 事業場内最低賃金要件 | 地域の最低賃金より30円以上高く設定すること (未達成時返還義務あり) |
| ワークライフバランス要件 | 「次世代育成支援対策推進法」に基づく一般事業主行動計画を策定・公表すること |
| 金融機関要件(金融機関から資金提供を受ける場合) | 補助事業の実施に当たり金融機関等から資金提供を受ける場合、金融機関から事業計画の確認を受けていること |
| 賃上げ特例要件(賃上げ特例の適用を受ける場合) | 補助事業実施期間内に、給与支給総額を年平均6.0%以上増加させるかつ、事業場内最低賃金を年額50円以上引き上げること |
大変重要な要件ですので、各要件について、「何が求められているのか」「判定のポイント」「実践ポイント」の3つの視点で解説していきます。
5-1.新事業進出要件
何が求められている?
既存事業とは異なる製品・サービスで、これまでリーチしていなかった顧客層(市場)に挑戦すること
判定のポイント
①自社にとって“新規性”のある製品・サービスか
②ターゲット市場がこれまでと明確に異なるか
③3~5年後に新事業売上高または付加価値額が、応募申請時の総売上の10%以上又は、総付加価値額の15%を占めることが見込まれるか
実践ポイント
既存事業の延長ではなく“用途”や“顧客属性”が変わることを事業計画内で示しましょう。
5-2.付加価値額要件
何が求められている?
補助事業終了後3~5年間で、付加価値額(=営業利益+人件費+減価償却費)を年平均4%以上伸ばす計画を策定すること。
付加価値額とは?
売上から原材料費などの仕入れを引いた“会社が生産活動によって生み出した価値”のこと。
式にすると「営業利益 + 人件費 + 減価償却費 = 付加価値額」となります。
ここでは「会社が稼いだ利益」と「従業員や設備に払ったコスト」を合わせて“どれだけ世の中に価値を生み出したか”を見る指標だと考えてください。
判定のポイント
申請者自身で、付加価値額年平均成長率4.0%以上の付加価値額目標値を設定し、事業計画期間最終年度において、付加価値額目標値を達成する。
実践ポイント
売上を増やす:値上げ・追加提案・新しい客づくりで粗利を厚くする。
ムダを減らす:IT化や自動化で同じ人数でもっと稼げる体制に。
儲かる投資だけする:費用以上の利益が出る設備に絞って実行。
5-3.賃上げ要件(未達成時返還義務あり)
何が求められている?
補助事業終了後3~5年間で、以下のいずれかの水準以上の賃上げを行うこと。
①一人当たり給与支給総額の年平均成長率を、事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間の年平均成長率以上増加させること。
(これを、一人当たり給与支給総額基準値という。)
【都道府県別最低賃金年平均成長率(令和2年度~6年度)】
| 都道 府県 | 年平均成長率 | 都道 府県 | 年平均成長率 | 都道 府県 | 年平均成長率 | 都道 府県 | 年平均成長率 |
| 北海道 | 3.2% | 東京 | 2.8% | 滋賀 | 3.3% | 香川 | 3.5% |
| 青森 | 3.8% | 神奈川 | 2.8% | 京都 | 3.1% | 愛媛 | 3.9% |
| 岩手 | 3.8% | 新潟 | 3.5% | 大阪 | 2.9% | 高知 | 3.8% |
| 宮城 | 3.4% | 富山 | 3.3% | 兵庫 | 3.2% | 福岡 | 3.4% |
| 秋田 | 3.8% | 石川 | 3.4% | 奈良 | 3.3% | 佐賀 | 3.9% |
| 山形 | 3.9% | 福井 | 3.5% | 和歌山 | 3.4% | 長崎 | 3.8% |
| 福島 | 3.7% | 山梨 | 3.4% | 鳥取 | 3.9% | 熊本 | 3.8% |
| 茨城 | 3.4% | 長野 | 3.3% | 島根 | 4.0% | 大分 | 3.8% |
| 栃木 | 3.3% | 岐阜 | 3.3% | 岡山 | 3.3% | 宮崎 | 3.8% |
| 群馬 | 3.4% | 静岡 | 3.2% | 広島 | 3.2% | 鹿児島 | 3.8% |
| 埼玉 | 3.1% | 愛知 | 3.1% | 山口 | 3.4% | 沖縄 | 3.8% |
| 千葉 | 3.1% | 三重 | 3.2% | 徳島 | 4.3% |
②給与支給総額の年平均成長率を2.5%以上増加させること。(これを、給与支給総額基準値という。)
判定のポイント
・申請者自身で、一人当たり給与支給総額基準値および、給与支給総額基準値以上の目標値を設定し、応募申請までにすべての従業員等に対して表明していること。
・事業計画期間最終年度において、一人当たり給与支給総額基準値または給与支給総額基準値のいずれかを達成すること。
これらが達成されていなかった場合、補助金全額の返還が求められます。
実践ポイント
・給与支給総額とは、従業員に払った給料、賃金賞与等のことを言い、役員報酬、福利厚生費、法定福利費、退職金は除きます。
・一人あたりの給与支給総額とは、給与支給総額を従業員数で割ったものを言います。
5-4.事業場内最低賃金要件(未達成時返還義務あり)
何が求められている?
補助事業終了後3~5年間で、補助事業を行う事業場の最低時給を、地域最低賃金+30円以上に保つこと。
判定のポイント
・毎年、賃金台帳を提出して判定。
地域最低賃金+30円以上になっていなかった場合、補助金を事業計画年数で按分した金額を返還。
実践のポイント
・事業場内最低賃金とは、補助事業を行う事業所の中で 最も低い時給 のこと。
パート・アルバイト・嘱託社員など雇用形態を問わず、実際に支払っている“時給換算額”で判定します。
5‑5. ワークライフバランス要件
何が求められている?
次世代育成支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画」を策定し、厚労省サイト「両立支援のひろば」に公開すること。
次世代育成支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画」とは?
次世代育成支援対策推進法は、企業が「仕事と子育てを両立できる職場環境」を整備し少子化対策に寄与することを目的とした法律です。
この法律に基づく「一般事業主行動計画」とは、企業が、育児休業取得率や所定外労働削減などの数値目標と具体的施策を盛り込み、策定・公表する中期計画書です。
計画を着実に実行し一定の基準を満たすと、厚生労働大臣の認定(くるみん・プラチナくるみん等)を受けられ、企業イメージ向上や公共調達での加点などのメリットがあります。
▶一般事業主行動計画の概要について詳しくはこちら
判定のポイント
補助金の申請までに公開が完了していることが必須
実践ポイント
・一般事業主行動計画を両立支援のひろばに掲載するにあたって、1~2週間程度期間を要すため、行動計画の策定も含め、遅くとも、補助金締切の1ヶ月前には着手しておくと安心です。
・厚生労働省サイトの記入例を見ながら進めれば、一般事業主行動計画の作成はさほど手間取りません。
▶一般事業主行動計画の策定について詳しくはこちら
5-6.金融機関要件
何が求められている?
補助事業実施にあたり、金融機関から資金提供を受ける場合には、金融機関から事業計画書の確認をうけること。
判定のポイント
・資金提供元の金融機関から「金融機関による確認書」を発行してもらい提出する
実践ポイント
・複数の金融機関から資金提供を受ける場合は、任意の1者からの「金融機関による確認書」で要件を満たします。
5-7.賃上げ特例要件(未達成時返還義務あり)
何が求められている?
補助事業実施期間内に、給与支給総額を年平均6.0%以上増加させるかつ、事業場内最低賃金を年額50円以上引き上げること。
賃上げ特例適用によって、補助上限額が500万円~最大2,000万円アップします。
判定のポイント
・応募申請時に、大幅な賃上げに取り組むための計画書を提出
・事業化状況報告時に、決算書・賃金台帳の提出が求められる。
実践のポイント
達成できなかった場合、補助金交付額のうち、賃上げ特例適用による補助上限引き上げ分の額の全額返還が求められる。
詳細な要件があります。
また、目標未達の場合、補助金全額返金のペナルティがありますので注意してください。

6.申請方法
申請は電子申請システムを使用し、事前に「GビズIDプライムアカウント」の取得が必要です。
(取得には1週間程度かかります)
電子申請システムから、事業計画の内容を入力、申請に必要な書類をアップロードする必要があります。
GビズIDプライムアカウント とは?
GビズIDは、補助金申請や社会保険の届出など、いろいろな行政サイトに“同じID・パスワード”で入れる共通ログインキーです。
GビズIDプライムアカウントの取得方法について詳しくはこちら
▶補助金の申請にはGビズIDが必須!パソコンが苦手でも大丈夫!GビズIDの取得方法8ステップ
6-1.事業計画へ記載すべき内容
事業計画書へ記載すべき項目は以下の通りです。
(1)既存事業の内容
①申請者の概要
②既存事業の内容
(2)補助事業の具体的取組内容
①新事業進出指針への該当性
②新規事業の内容・目的
(3)現状分析
①現在の事業の状況
②SWOT分析を実施した上での新規事業を実施することの必要性
(4)新規事業の新市場性・高付加価値性〈①と②は選択制〉
①新市場性
②高付加価値性
(5)新事業の有望度
①新規事業の将来性
②参入可能性
③競合分析
(6)事業の実現可能性
①課題及びスケジュール
②事業実施体制
(7)公的補助の必要性
①新規事業の内容が、川上・川下への経済波及効果が大きい事業や社会的インフラを担う事業、新たな雇用を生み出し事業など、国が補助する積極的な理由がある場合はその理由とともにその旨を記載【任意】
②新規事業の内容が、先端的なデジタル技術の活用、新しいビジネスモデルの構築等を通じて、地域やサプライチェーンのイノベーションに貢献し得る事業である場合はその理由とその旨を記載【任意】
③国からの補助がなくとも自社単独で容易に事業を実施できるものではないことについての説明
(8)政策面
新規事業の内容が、以下の項目に該当する場合は、その理由とともにその旨を記載【任意】
① 経済社会の変化(関税による各産業への影響等を含む)に伴い、今後より市場の成長や生産性の向上が見込まれる分野に進出することを通じて、日本経済の構造転換を促すことに資するか。
② 先端的なデジタル技術の活用、低炭素技術の活用、経済社会にとって特に重要な技術の活用、新しいビジネスモデルの構築等を通じて、我が国の経済成長・イノベーションを牽引し得るか。
③ ニッチ分野において、適切なマーケティング、独自性の高い製品・サービス開発、厳格な品質管理などにより差別化を行い、グローバル市場でもトップの地位を築く潜在性を有しているか。
④ 地域の特性を活かして高い付加価値を創出し、地域の事業者等に対する経済的波及効果を及ぼすことにより、大規模な雇用の創出や地域の経済成長(大規模災害からの復興等を含む)を牽引する事業となることが期待できるか。
※ 以下に選定されている事業者や承認を受けた計画がある事業者は審査で考慮いたします。
・地域未来牽引企業
・地域未来投資促進法に基づく地域経済牽引事業計画
(9)補助対象予定経費
①補助対象とするすべての経費の内容を具体的に記載
・経費の分類
・名称
・取得価格
※単価500万円(税抜)を超える機械装置については、機会種類が具体的にわかる名称を記載
②補助対象とするすべての経費について、それらか必要不可欠である理由を具体的に説明
(10)収益計画
①補助事業の事業化見込み(収益計画表を作成)
②補助対象要件への該当性
③大幅な賃上げ計画の妥当性(賃上げ特例の適用を希望する事業者のみ)
積極的に活用し、わかりやすい説明を心がけましょう。
6-2.必要資料
申請の際に提出が必要となる一般的な書類は以下の通りです。
・決算書
・従業員数を示す書類(労働者名簿)
・収益事業を行っていることを説明する書類
【法人の場合】
・直近の確定申告書別表一の控え
・法人事業概況説明書の控え
【個人事業主の場合】
・直近の確定申告書第一表の控え
・所得税青色申告決算書の控え(白色申告の場合、収支内訳書の控え)
・固定資産台帳
・賃上げ計画の表明書
・金融機関による確認書
7.審査方法
ポイントは「書類で高得点を取ること」です。
審査は原則として書類審査で行われ、一定の基準を満たした事業者に限り、必要に応じて口頭審査が追加される場合があります。
したがって、まずは書類審査で評価を得られるように準備することが最重要です。
事業計画書が完成したら、審査項目を一つひとつ確認し、自社の計画が各項目を満たしているかを必ずチェックしましょう。
以下は、公募要領の審査項目です。
書面審査
(1)補助対象事業としての適格性
① 本公募要領に記載する補助対象者、補助対象事業の要件、補助対象事業等を満たすか。
※ 満たさない場合は補助対象外として不採択となります。
② 補助事業により高い付加価値の創出や賃上げを実現する目標値が設定されており、かつその目標値の実現可能性が高い事業計画となっているか。
※ 付加価値額要件及び賃上げ要件において、基準値を上回る高い目標値が設定されている場合、高さの度合いと実現可能性を考慮して審査します。(2)新規事業の新市場性・高付加価値性
※ 「新市場・高付加価値事業とは」もご参照ください。
① 補助事業で取り組む新規事業により製造又は提供(以下「製造等」という。)する、製品又は商品若しくはサービス(以下「新製品等」という。)のジャンル・分野の、社会における一般的な普及度や認知度が低いものであるか。※ 補助事業で取り組む事業の内容が、新事業進出指針に基づく当該事業者にとっての新規事業であることを前提に、社会においても一定程度新規性を有する(一般的な普及度や認知度が低い)ものであることを求めます。
⚫ 新製品等の属するジャンル・分野は適切に区分されているか。
⚫ 新製品等の属するジャンル・分野の社会における一般的な普及度や認知度が低いものであるか。それらを裏付ける客観的なデータ・統計等が示されているか。② 同一のジャンル・分野の中で、当該新製品等が、高水準の高付加価値化・高価格化を図るものであるか。
⚫ 新製品等のジャンル・分野における一般的な付加価値や相場価格が調査・分析されているか。
⚫ 新製品等のジャンル・分野における一般的な付加価値や相場価格と比較して、自社が製造等する新製品等が、高水準の高付加価値化・高価格化を図るものであるか。高付加価値化・高価格化の源泉となる価値・強みの分析がなされており、それが妥当なものであるか。(3)新規事業の有望度
① 補助事業で取り組む新規事業が、自社がアプローチ可能な範囲の中で、継続的に売上・利益を確保できるだけの市場規模を有しているか。成長が見込まれる市場か。
② 補助事業で取り組む新規事業が、自社にとって参入可能な事業であるか。⚫ 免許・許認可等の制度的な参入障壁をクリアできるか。
⚫ ビジネスモデル上調達先の変更が起こりにくい事業ではないか。③ 競合分析を実施した上で、顧客ニーズを基に、競合他社と比較して、自社に明確な優位性を確立する差別化が可能か。
⚫ 代替製品・サービスを含め、競合は網羅的に調査されているか。
⚫ 比較する競合は適切に取捨選択できているか。
⚫ 顧客が商品やサービスの購入を決める際に重視する要素や判断基準は明らかか。
⚫ 自社が参入して、顧客が商品やサービスの購入を決める際に重視する要素や判断基準を充足できるか。
⚫ 自社の優位性が、他者に容易に模倣可能なもの(導入する機械装置そのもの、営業時間等)となっていないか。(4)事業の実現可能性
① 事業化に向けて、中長期での補助事業の課題を検証できているか。また、事業化に至るまでの遂行方法、スケジュールや課題の解決方法が明確かつ妥当か。
② 最近の財務状況等から、補助事業を適切に遂行できると期待できるか。金融機関等からの十分な資金の調達が見込めるか。
※ 複数の事業者が連携して申請する場合は連携体各者の財務状況等も考慮します。
③ 補助事業を適切に遂行し得る体制(人材、事務処理能力等)を確保出来ているか。第三者に過度に依存している事業ではないか。過度な多角化を行っているなど経営資源の確保が困難な状態となっていないか。(5)公的補助の必要性
① 川上・川下への経済波及効果が大きい事業や社会的インフラを担う事業、新たな雇用を生み出す事業など、国が補助する積極的な理由がある事業はより高く評価。
② 補助事業として費用対効果(補助金の投入額に対して増額が想定される付加価値額の規模、生産性の向上、その実現性、事業の継続可能性等)が高いか。
③ 先端的なデジタル技術の活用、新しいビジネスモデルの構築等を通じて、地域やサプライチェーンのイノベーションに貢献し得る事業か。
④ 国からの補助がなくとも、自社単独で容易に事業を実施できるものではないか。(6)政策面
① 経済社会の変化(関税による各産業への影響等を含む)に伴い、今後より市場の成長や生産性の向上が見込まれる分野に進出することを通じて、日本経済の構造転換を促すことに資するか。
② 先端的なデジタル技術の活用、低炭素技術の活用、経済社会にとって特に重要な技術の活用、新しいビジネスモデルの構築等を通じて、我が国の経済成長・イノベーションを牽引し得るか。
③ ニッチ分野において、適切なマーケティング、独自性の高い製品・サービス開発、厳格な品質管理などにより差別化を行い、グローバル市場でもトップの地位を築く潜在性を有しているか。
④ 地域の特性を活かして高い付加価値を創出し、地域の事業者等に対する経済的波及効果を及ぼすことにより、大規模な雇用の創出や地域の経済成長(大規模災害からの復興等を含む)を牽引する事業となることが期待できるか。
※ 以下に選定されている事業者や承認を受けた計画がある事業者は審査で考慮いたします。
・地域未来牽引企業
・地域未来投資促進法に基づく地域経済牽引事業計画(7)大規模な賃上げ計画の妥当性(賃上げ特例の適用を希望する事業者に限る)
① 大規模な賃上げの取組内容が具体的に示されており、その記載内容や算出根拠が妥当なものとなっているか。
② 一時的な賃上げの計画となっておらず、将来にわたり、継続的に利益の増加等を人件費に充当しているか。
上記は書類における審査項目です。
これらの他に、加点項目・減点項目もありますので、公募要領のP44~46もしっかり確認をするようにしましょう。
8.補助金申請の流れスケジュール
📌 第1回 応募締切:2025年7月10日(木)18:00[厳守]
補助金の申請から、補助金の入金までの流れは以下の通りです。
| フェーズ | 期間の目安 | 主なアクション |
| 公募開始~締切 | 公募開始:R7.4.22 応募開始:R7.6月中旬を予定 応募締切:R7.7.10 | ・GビズID取得 ・一般事業主行動計画の公表 ・事業計画書の作成 ・見積取得 ・電子申請完了 |
| 審査~採択発表 | 採択結果発表:R7.10月頃 | ・口頭審査(対象者のみ) |
| 交付申請~交付決定 | 交付申請締切:採択発表日から2ヶ月以内 | ・説明会への参加 ・交付申請 |
| 補助事業実施 | 交付決定日から14カ月以内 (ただし、採択発表日から16カ月の日まで) | ・補助事業の実施 ・補助対象経費の発注、契約、支払等 |
| 実績報告 | 補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日または、補助事業完了期限日のいずれか早い日まで。 ※補助事業完了期限日は、各自交付決定通知書に記載。 | ・実績報告書の作成、提出 ・補助対象経費の証票(発注書・契約書・請求書・領収書等)の整理 |
| 確定検査(補助金額の確定) | ― | ・実地検査 |
| 補助金の請求・入金 | ― | ・補助金請求書の提出 |
| (事業計画期間) | 5年間 | ・事業化状況報告書の提出(年1回) |
・交付決定前に、発注・契約・支払を行った経費は、補助対象外になってしまいます。
「採択=内定」と考えて、採択結果がでたからと慌てて発注等をしないようにしましょう。
・補助金は「まず自社で立て替えて、後で精算してもらう」仕組みです。
そのため採択されても、事前に自己資金やつなぎ融資等で資金を準備できなければ、事業を始めること自体が難しくなります。
・実際に補助金が入金されるまで、1年以上時間がかかります。その間、キャッシュ不足に陥らないよう、注意が必要です。
9.専門家支援の活用
補助金申請は 認定支援機関にサポートを依頼するのがベスト。
採択率が上がり、作業負担や不採択リスクを大幅に減らせます。
ただし 丸投げは厳禁。事業計画書の作成・実行は、申請者自身が責任を持って取り組む必要があります。
【認定支援機関に頼むメリット】
・採択率アップ
審査基準を熟知しており、加点ポイントを押さえたブラッシュアップが可能
・時間コスト削減
事業計画書の作成にかかる「数十時間」を短縮し、通常業務に集中できる
・不採択リスク低減
要件漏れや書類不備を事前にチェック
認定支援機関とは?
認定経営革新等支援機関とは、中小企業を支援する高度な知識と実務経験を国から公式に認められた専門機関です。
理士・公認会計士・中小企業診断士などの士業のほか、商工会・商工会議所、金融機関等が該当し、経営アドバイス、事業計画書のブラッシュアップ、資金調達や補助金申請のサポートを総合的に提供します。
10.まとめ
中小企業新事業進出促進補助金は、新しいことにチャレンジしたい企業を、応援してくれる制度です。
ただし、要件が多く、自己資金の準備や計画づくりがしっかりしていないと、せっかく申請しても採択されない可能性があります。
この補助金、ここがポイント!
・補助額は最大9,000万円(補助率1/2)
⇒最低補助金額(750万円)が定められているため、 最低でも1,500万円以上の投資が必要です。
・従業員の賃上げや事業の成長が必須
⇒ “どれだけ成長するか”“どれだけ給料を上げるか”を数字で説明します。
・補助金はあと払い方式
⇒ いったん自分でお金を払ってから、あとで補助金が入ってくる仕組みです。
・申請には細かなルールと書類の準備が必要
⇒ 審査では「書類の内容」がすべて。計画の中身と見せ方がとても大切です。
これからどう動けばいい? ― 3ステップで整理
まずは準備からスタート!
・「GビズIDプライム」というIDを取得(1週間かかる)
・「一般事業主行動計画」を作成して厚労省サイトに登録
・やりたい事業の内容を整理して、見積書などを集め始めましょうお金の準備も忘れずに
・補助金は“あとで”もらうもの。事前に自己資金やつなぎ融資の準備が必要です
・金融機関に事業計画を見せて、資金面のサポートを受けられるとベストです困ったら専門家に相談を!
・補助金に詳しい“認定支援機関”に相談するのがおすすめです
・申請書の作り方、要件のチェック、採択されるポイントまで一緒に見てくれます
・丸投げではなく、一緒に作り込むことが成功のカギです
📌 第1回の締切は 2025年7月10日(木)18:00!
締切ギリギリでは間に合いません。今から準備を始めることが成功への第一歩です!

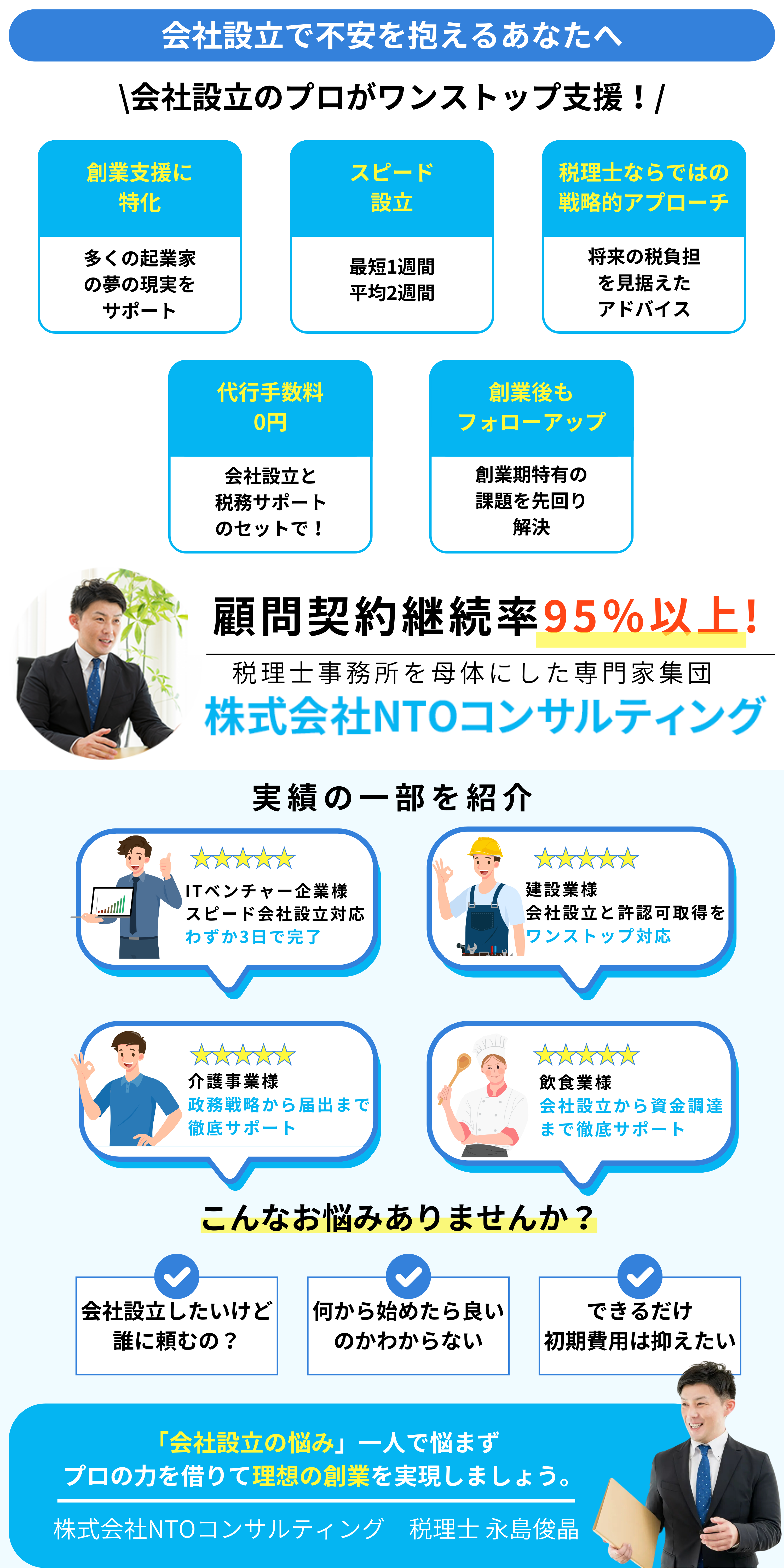
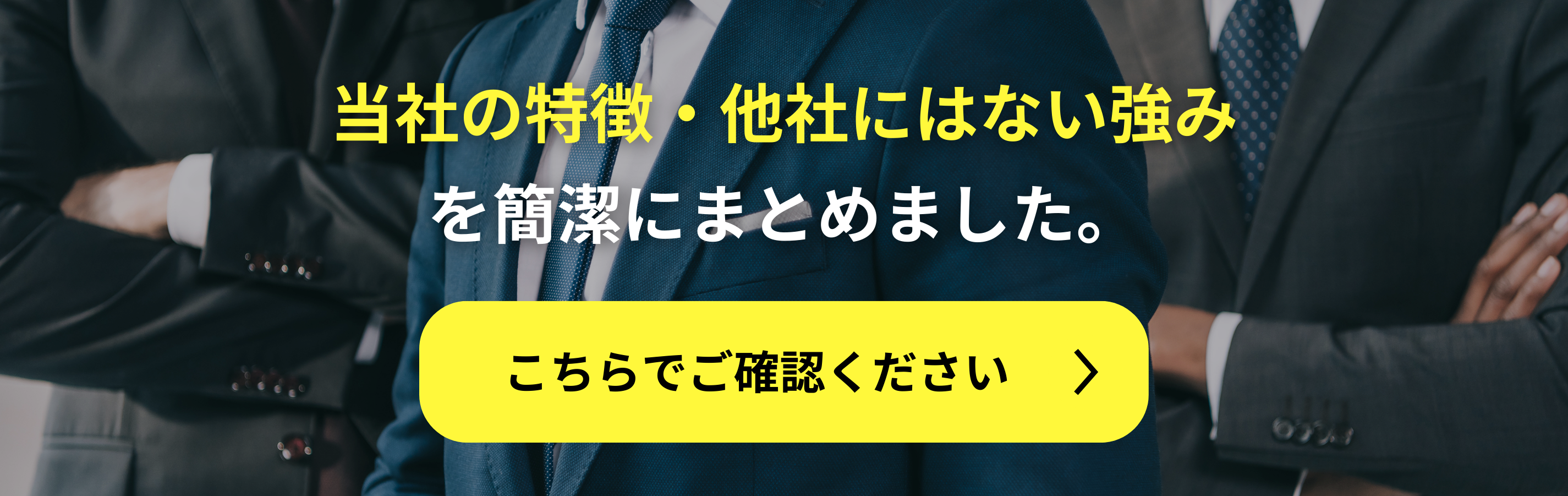
コメント