
「一般社団法人って、融資が受けづらいって聞いたけど、本当に借りられるの?」
そんな不安や疑問を感じられているのではないでしょうか?
たしかに、株式会社や合同会社と違い、一般社団法人は非営利法人という特殊な立場のため、金融機関からの見え方が異なり、利用できる融資制度に制限があるのは事実です。
しかし、「一般社団法人だから融資は無理」とあきらめるのは早すぎます。
実際には、日本政策金融公庫の創業融資や、事業内容によってはソーシャルビジネス向け融資など、非営利法人でも利用できる制度は存在します。
この記事では、「なぜ一般社団法人は融資を受けにくいと言われるのか?」という理由から、実際に使える具体的な融資制度や成功のための準備ポイントまで、専門家の視点でわかりやすく解説します。
「うちは社団法人だから…」とあきらめていた方こそ、ぜひ最後まで読んでみてください。
目次
1.一般社団法人でも融資は受けられる!なぜ、受けにくいと言われるのか?
結論:一般社団法人でも融資は受けられます。
実際に、公的融資や民間のプロパー融資などを活用して資金を調達することは可能です。
ただし、株式会社や合同会社などと比べると制度の制約や金融機関の見方の違いにより、「融資を受けにくい」と感じられる場面があるのも事実です。
一般社団法人が融資を受けにくいと言われる理由は次の3つです。
1.非営利法人であるため、返済能力が伝わりにくい
結論:一般社団法人は、営利を目的としない法人であるため、金融機関にとって「返済能力があるのか」が判断しづらく、結果として審査が厳しくなる傾向があります。
一般社団法人は、「利益を出してはいけない」わけではありませんが、「利益を得ること自体が目的ではない」法人です。
主な目的は社会貢献や公益的な活動の実現にあり、収益を上げることはあくまでその活動を続けるための手段にすぎません。
この“営利を目的としない”という特徴が、融資を申し込む場面では壁になります。
なぜなら、金融機関が融資の審査で重視するのは「安定して利益を上げられるのか」「確実に返済してもらえるか」という視点だからです。
たとえば、株式会社なら「サービスを売って利益を出し、その一部で返済する」というモデルがわかりやすいのですが、一般社団法人では「社会のための活動」が目的になるため、返済の原資(=収益)がどこから出てくるのかが読み取りづらいのです。
2.保証協会付き融資が使えない
結論:一般社団法人は、「信用保証協会付き融資」を原則として利用できません。
信用保証協会付き融資とは、「信用保証協会」という第三者が保証人となり、万が一返済できなくなったときに肩代わりしてくれる仕組みです。
金融機関にとっては、リスクが大きく下がるため、特に創業間もない企業や法人にとっては、非常に頼りになる制度です。
ところが、一般社団法人はこの保証制度の対象外とされているため、銀行などの金融機関にとっては「保証のない、リスクの高い融資」となり、必然的に審査が慎重になるのです。
保証のない融資=プロパー融資は、信用力の乏しい創業間もない企業は、ほとんど利用できないのが現実です。
※補足※
通常、創業期に利用される代表的な融資には、以下の2つがあります。
① 日本政策金融公庫の創業融資(国の公的金融機関による融資)
② 信用保証協会付き融資(民間の金融機関(銀行・信金等による融資)
株式会社や合同会社などの営利法人であれば、どちらも利用できる可能性がありますが、一般社団法人は、創業時に多くの法人が利用する「2本柱のうち1本」、すなわち信用保証協会付き融資の道が閉ざされてしまっているということになります。
3.原則、制度融資も使えない
結論:自治体が実施する「制度融資」は、信用保証協会の保証が前提となっているため、原則として一般社団法人は利用できません。
つまり、信用保証付き融資が使えないという時点で、制度融資も自動的に対象外となってしまいます。
そもそも、「制度融資」とは、自治体が地域の中小企業や創業者を支援するために用意している融資制度で、以下の三者が連携して行います。
①自治体(融資制度の枠組みと利子補給などの支援)
②金融機関(実際に融資を行う)
③信用保証協会(返済不能時に肩代わりする保証人)
このように、信用保証協会の存在が制度融資の中核をなしており、保証を前提に成り立っている仕組みなのです。
ただし、一部例外として一般社団法人も制度融資を利用できる自治体もあるようです。
自分の地域で利用できる制度があるかどうかは事前に自治体の窓口や、金融機関に確認するようにしてください。
一般社団法人は融資を受けにくい側面はありますが、使える制度がまったくないわけではありません。
次の章では、一般社団法人でも実際に利用できる融資制度と、その他の現実的な資金調達の選択肢をご紹介します。
2.一般社団法人が使える融資制度と資金調達手段
結論:一般社団法人でも利用できる融資制度は存在します。
日本政策金融公庫の融資や、一般社団法人だからこそ利用できる基金という制度があります。
1. 日本政策金融公庫(公的融資)
日本政策金融公庫は、国が100%出資する政府系金融機関で、これから創業する方や、創業間もない中小企業や小規模事業者支援をすることを目的としています。
一般社団法人も利用できる制度が用意されており、資金調達の有力な選択肢となります。
日本政策金融公庫には、一般社団法人にとって特に活用しやすい制度が2つあります。
① 新規開業資金(旧・新創業融資制度)
「新規開業資金」は、これから事業を始める人や、創業して間もない法人を対象とした融資制度です。
以前は「新創業融資制度」と呼ばれていた制度が統合・整理されたもので、現在は「新規開業資金」として提供されています。
一般社団法人もこの制度の対象となっており、事業として継続的な活動が見込まれ、返済計画が明確であれば、営利法人と同様に申請が可能です。
【主な特徴】
・対象者:新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方
・無担保・無保証人で融資を受けることが出来る
・融資限度額:7,200万円(うち運転資金4,800万円)
・申込から融資実行まで1ヶ月程度
日本政策金融公庫の創業融資について詳しくはこちら
▶日本政策金融公庫の創業融資|保存版完全ガイド
② ソーシャルビジネス支援資金
この制度は、保育、介護、障がい者支援など、社会的課題の解決を目的とした事業を行う法人向けの融資です。
非営利法人である一般社団法人も、事業の内容によっては十分に対象となります。
【対象となる事業例】
・地域の子育て支援・学童保育
・高齢者向けの福祉サービス
・障がい者の就労支援事業 など
【主な特徴】
・日本標準産業分類における老人福祉・介護事業、児童福祉事業、障がい者福祉事業等が対象
・融資限度額:7,200万円(うち運転資金4,800万円)
・事業内容により特別利率適用
社会的課題を解決する事業(ソーシャルビジネス)は、利益を追求する一般企業に比べて収益性が低く評価されがちです。
そのため、資金調達のハードルが高く、特に創業期や拡大期に金融機関からの融資が難航するケースが多くあります。
そこで、日本政策金融公庫ではこのような社会貢献性の高い事業者を支援するため、融資要件を緩和し、低利での融資制度として「ソーシャルビジネス支援資金」が設けられています。
2. 銀行や信用金庫からのプロパー融資
信用保証がつかない分、審査は厳しくなりますが、直接交渉での融資獲得が可能です。
プロパー融資とは、銀行が「独自の判断と責任」で実行する融資のことです。
信用保証協会の保証がつかない分、銀行がリスクをすべて負うため、「本当にこの企業に貸しても大丈夫か」を細かく審査されます。
株式会社などの営利法人でも、プロパー融資を受けるには一定の信用力や実績が必要なため、ハードルはかなり高めです。
一般社団法人の場合は、収益性や返済能力が見えにくいため、より一層の説明と信頼構築が求められます。
もし、返済能力がしっかり評価されれば、日本政策金融公庫や信用保証協会付き融資よりも、好条件で借りられる可能性もあります。
プロパー融資について詳しくはこちら
▶プロパー融資とは?信用保証協会付き融資との違いを比較解説!
3. 一般社団法人ならではの資金調達手段:基金制度の活用
基金とは、一般社団法人が社員以外の第三者から受ける金銭や財産の拠出で、法人の活動資金として活用できる仕組みです。出資とは異なり、株式のような所有権は発生しません。
基金には以下の2種類があります
・返還基金:一定の期間や条件により、将来的に拠出者へ返還される基金
・永久基金:返還義務がなく、法人が継続的に活用できる基金
社会貢献活動を行う一般社団法人にとって、返済の必要がない資金を確保できるのは大きなメリットです。
基金制度は、一般社団法人にとって数少ない資金調達の選択肢のひとつとして有効ですが、資金を集めるまでに時間を要するケースも少なくありません。
たとえば、募集内容の設定や準備に手間がかかるほか、いざ募集を開始しても希望する拠出者が思うように集まらないことがあります。
このように、さまざまな理由で資金の確保が遅れる可能性があるため、基金制度だけに依存するのではなく、他の資金調達手段と並行して進めることが望ましいでしょう。

3.一般社団法人が融資を成功させるための3つの準備ポイント
一般社団法人が融資を成功させるには、「事業の収益性と社会性をわかりやすく示す」「面談対策をする」「必要に応じて専門家のサポートを受ける」ことが不可欠です。
ここでは、実際に融資を受けるために必要な3つの重要な準備ポイントを、専門家の視点から解説します。
1. 収益性と社会性を両立させた事業計画書を作る
般社団法人の特徴である「非営利性」は、社会的な意義を評価される一方で、収益性が見えにくいため、融資審査ではマイナスに働くことがあります。
だからこそ、事業計画書では「社会性」と「収益性」を両立させていることを、きちんと説明する必要があります。
【審査で評価されやすいポイント】
・活動の目的や社会課題への貢献内容が明確に書かれている
・誰に対して、どのようなサービスを提供し、どう収益が発生するのかが具体的に説明されている
・売上見込み、支出の内訳、月ごとのキャッシュフローが数字で整理されている
・借入金の使い道と、そのお金がどう事業成長につながるかのストーリーがある
・毎月の返済額に対して、確実な返済原資があると示せている
単なる理念ではなく、「どう稼ぎ、どう返すか」を見える形で説明することが、融資成功のカギです。
事業計画書・創業計画書の書き方について詳しくはこちら
▶日本政策金融公庫の創業計画書の書き方11ステップ!審査を通すためのテクニックを完全公開!
2. 面談対策は万全に!
融資審査において、書類と同じくらい重要なのが「面談(ヒアリング)」です。
特に日本政策金融公庫で初めて融資を受ける際には、担当者との面談が必須でここでの受け答えによって融資の可否が左右されることも少なくありません。
基本的には、事前に提出している、創業計画書の内容をもとに面談が進められていきます。
創業計画書に記載した内容について、根拠立てて説明をする必要があります。
【面談でよく聞かれる質問(例)】
・なぜこの事業を始めようと思ったのですか?
・サービスの収益モデルはどのような仕組みですか?
・なぜ今、このタイミングで融資が必要なのですか?
・資金の利用目的を詳しく教えてください。
・売上の根拠を教えてください。
・どのように集客を行いますか?
・万が一、計画通りにいかなかった場合はどう対応しますか?
これらの質問に対し、準備なく曖昧な回答をしてしまうと、信頼性が一気に下がります。
一方で、しっかりと想定問答を準備しておけば、あなたの思いや事業の価値がしっかり伝わり、面談は融資通過の後押しになります。
面談時のよくある質問を下記の記事にまとめておりますので、併せて確認し、面談のシミュレーションをしておくようにしましょう。
3.専門家のサポートを受ける
必要に応じて、専門家のサポートを受けましょう。
特に一般社団法人のように、制度上の制限や説明の難しさがある法人では、経験豊富な専門家のサポートが審査通過の確率を大きく高めます。
初めて融資を受ける方や、一般社団法人という法人格特有の事情を抱える方にとって、以下のような課題は避けて通れません。
・事業計画書の作成に自信がない
・数字の根拠をどう説明すべきかわからない
・面談でどのように答えたらいいか不安
こうした悩みは、融資支援に慣れた税理士などの専門家に相談することで、適切なアドバイスを受けることができます。
【専門家に相談するメリット】
✅ 審査に通りやすい事業計画書の作成を一緒に行ってくれる
✅ 面談対策や提出書類のチェックなど、実務的な支援が受けられる
✅ 専門家の「紹介」という形で信用が補完されることもある
書類や面談の“仕上がり”がまったく違ってくるため、初めての融資申請では特に大きな力になります。
一般社団法人の資金調達は、制度の選定・事業計画の作成・面談の対応と、やるべきことが多く、判断に迷う場面も多くあります。
そんな時は、信頼できる専門家に相談することで、融資成功までのプロセスが格段にスムーズになります。時間や労力を節約できるだけでなく、融資の確率そのものが大きく上がります。
専門家のサポートは、単なる“代行”ではなく“戦略的パートナー”です。
4.まとめ|一般社団法人でも、準備次第で融資は実現できる
一般社団法人でも融資を受けることは可能です。
ただし、株式会社などと比べると、制度上の制限や金融機関の見方の違いから「受けにくい」とされる側面があるのも事実です。
特に注意すべきポイントは以下の2点でした。
・非営利法人であるため、返済能力が伝わりにくい
・信用保証協会付き融資や制度融資の多くが利用できない
とはいえ、日本政策金融公庫の「新規開業資金」や「ソーシャルビジネス支援資金」など、一般社団法人でも使える公的制度は確かに存在します。
また、銀行等との交渉によるプロパー融資や、一般社団法人特有の「基金制度」など、選択肢は決して一つではありません。
さらに、融資を成功させるためには以下の3つの準備が重要でした。
1.収益性と社会性を両立させた事業計画書の作成
2.日本政策金融公庫などでの面談対策の徹底
3.専門家(税理士など)のサポートを活用すること
これらを踏まえれば、制度の制約がある中でも、融資を通すことは十分に可能です。
次に取るべき行動は?
✅ 収益モデルを含めた事業計画書を作成する
✅ 専門家に相談し、書類・面談の準備を万全にする
「一般社団法人だから難しい」と諦める前に、的確な準備を進めることが大切です。
必要に応じて専門家の力を借りながら、一歩ずつ資金調達の準備を進めましょう。

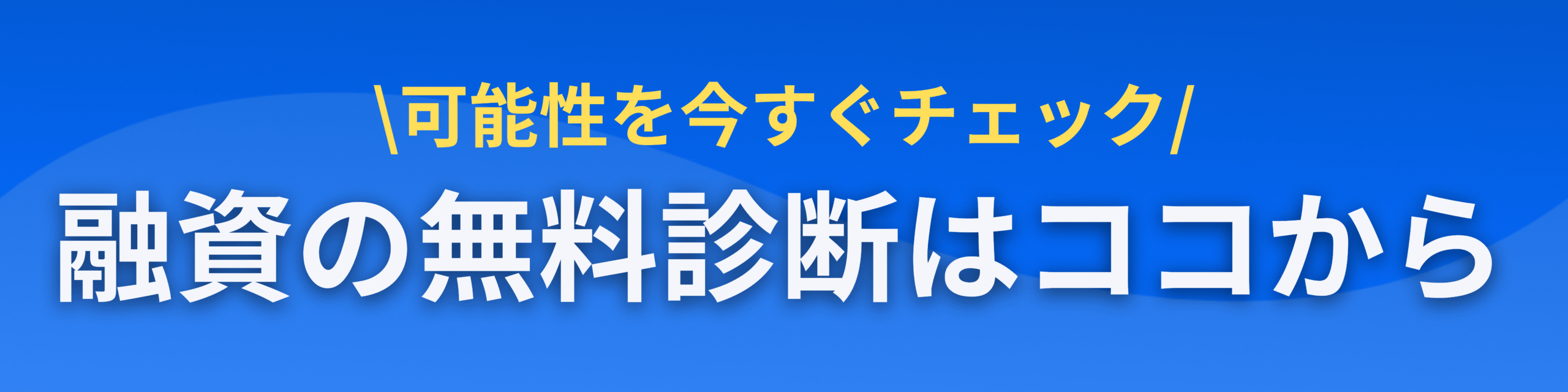

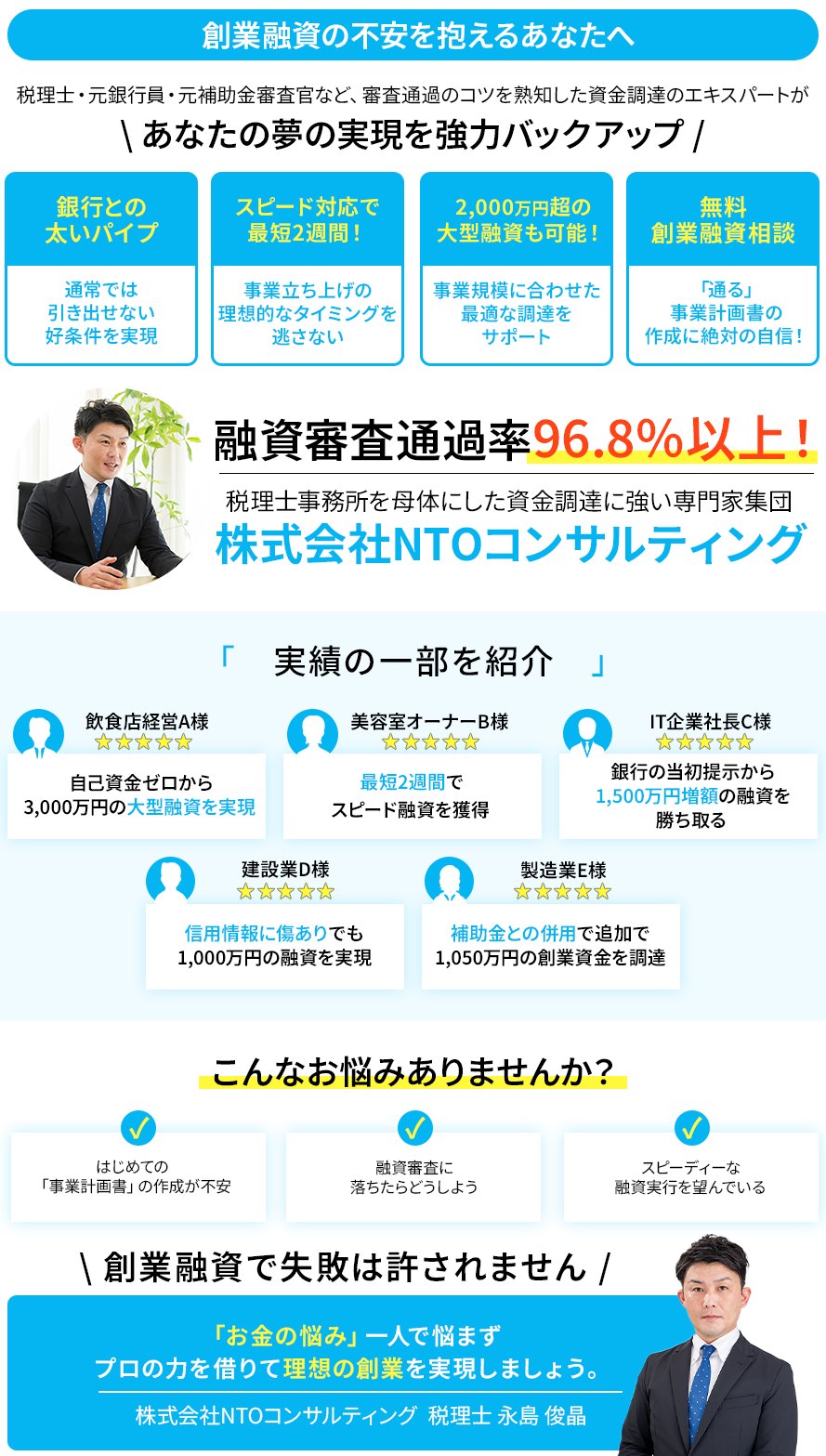
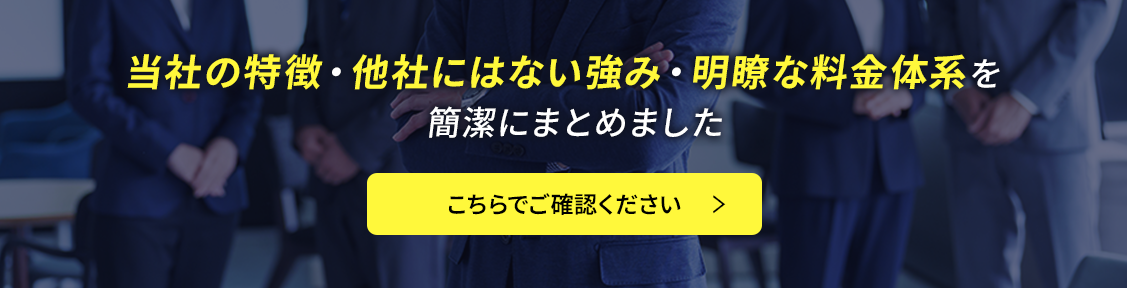
コメント