
「未経験だから無理」と決めつけるのは早い。でも、甘くはありません。
結論から言えば、業界未経験であっても創業融資を受けられる可能性は十分にあります。
ただし、「経験がなくても通る人」と「経験がなくて落ちる人」には、はっきりとした違いがあります。
その違いとは、ズバリ「経験不足をどう補っているか」
たしかに、金融機関(特に日本政策金融公庫)は「その事業を続けていける根拠」を重視します。
そのため、開業予定の業種での実務経験がある方が審査で有利です。
一方で、未経験であっても以下のような対策をしていれば、融資が通るケースも数多くあります。
・アルバイトや副業などで少しでも事前に業務経験を積んでいる
・事業計画書に具体的な根拠や数字があり、説得力がある
・販路・仕入先・協力者など、事業の実行体制が整っている
専門家としても、「未経験=絶対に無理」というわけではなく、むしろ“補い方次第”で融資の成否が分かれると日々感じています。
この記事では、未経験からでも創業融資を通すために、どんな工夫や対策ができるのか、
金融機関に信頼される事業計画の作り方や面談対策まで、専門家の視点から具体的に解説します。
目次
1.なぜ未経験だと創業融資は不利になりやすいのか?
経験が「信用」に直結します。
創業融資において、未経験者が不利になりやすい最大の理由は、「返済できる見込みが立ちにくい」と金融機関に判断されるからです。
金融機関が融資を行う際、重視するのは「事業が本当に継続・成功するかどうか」そして、「貸したお金が返ってくるか」です。
そしてその根拠として、過去の「業務経験」は非常に強い信用材料になります。
たとえば…
・飲食店を開業するのに、飲食業界での勤務経験がゼロ
・ネイルサロンを始めるが、美容系の職歴がない
・コンサル業を立ち上げるが、類似業種の経験もなし
こうしたケースでは、「実際にサービスを提供できるのか」「トラブルに対応できるのか」など、金融機関が不安を抱きやすく、融資の審査が厳しくなります。
| 専門家からのアドバイス |
| 未経験だからといって一発NGになるわけではありませんが、「なぜ自分がこの事業をやるのか」「どうしてできるといえるのか」を数字や根拠で語れないと、説得力に欠けます。 融資は夢ではなく、あくまで“ビジネス”。その目線で、自分の経験値をどう補完するかを考えることが重要です。 |
2.未経験でも創業融資を通すための4つの補完策
経験がなくても、「信用」をつくる方法はあります。
未経験だからこそ、“それでも事業がうまくいく理由”を、別の形で金融機関に伝える必要があります。
ここでは、未経験者が創業融資を成功させるために実際に効果的だった4つの補完策をご紹介します。
① アルバイトや副業で「実務経験」を積む
いちばんシンプルかつ効果的なのが、開業予定の業種でアルバイトや副業をしてみることです。
・飲食店開業 → 飲食店でホールや調理補助の経験
・ネイルサロン開業 → 他店でのスタッフ経験
・EC販売 → 他社のEC運営やSNS運用を請け負う
たとえ短期間でも、実務を通じて業界構造や仕事の流れを把握しているだけで、融資担当者の印象は大きく変わります。
| 専門家からのアドバイス |
| 「経験」と一口に言っても、やはり長ければ長いほど信頼性は高くなります。 融資担当者としても、「数年にわたり業界で勤務していた人」と「1か月だけ副業で触れた人」では、安心感が全く違います。 ただし、まったく経験がない状態よりも、短期間でも“現場に触れた”実績がある方が、間違いなく有利です。 ですので、未経験で起業を目指す方は、最低限、数か月でも業界に関わる経験を持っておくべきです。金融機関に対する最低限の信用の土台になります。 |
② 自己資金をしっかり積み上げる
未経験者が最も見落としがちなのが、自己資金のインパクトです。
「自己資金がある = 本気度が高い」「返済能力がある」と評価され、未経験のリスクを一部相殺できます。
✅ 目安:開業資金の3分の1以上は欲しい。
✅ NG例:開業費のすべてを借りようとする計画は、融資が通りにくい傾向。
| 専門家からのアドバイス |
| 自己資金は“信用の証明”です。 毎月、計画的に貯めてきた通帳記録があると、金融機関に本気度が伝わります。 |
③ 仕入先・販路・協力者を確保しておく
経験はなくても、「この人なら事業が回るかもしれない」と思わせるのが、実行体制の明示です。
・商品の仕入先との取引契約
・販売先の内諾(企業や親族など)
・士業・コンサル・パートナーなどの支援体制
こうした「誰と組んで何をするのか」が明確であれば、経験のなさはカバーできます。
| 専門家からのアドバイス |
融資審査では、「経験のある人がそばにいるかどうか」が大きな安心材料になります。 特に金融機関は、「この人がアドバイスすれば事業は続くだろう」「最低限のノウハウを教えてくれる人がいる」と判断できれば、未経験でも前向きに評価してくれることがあります。 そのため、 また、その協力者に十分なスキルやノウハウがある場合、「なぜその人自身が事業主ではなく、あなたが代表なのか?」という質問もよくあります。 |
④ フランチャイズや専門家の力を借りる
特定の業種では、フランチャイズに加盟することで、ノウハウや仕入・集客の仕組みを借りられるため、未経験でも成功しやすくなります。
また、融資に強い税理士・中小企業診断士などの専門家と一緒に事業計画書を作成すれば、経験不足のリスクをさらに低減できます。
| 専門家からのアドバイス |
未経験だからこそ、「知っている人に頼る」「成功モデルに乗っかる」という戦略は非常に有効です。 ただし、フランチャイズの契約内容やサポート範囲は、事前によく確認しておくことが不可欠です。 高額な加盟料やロイヤリティを支払っているのに、顧客開拓をすべて自力で行う羽目になり、苦労している経営者も少なくありません。 |
3.未経験者でも信頼される「通る事業計画書」の作り方
経験を補うのは「説得力のある計画書」
未経験者が創業融資を成功させるには、「この事業なら実現可能だ」と金融機関に思わせる事業計画書の説得力がカギとなります。
単に夢や希望を書くだけではなく、「数字の裏付け」や「実行可能な体制」があることを、ロジカルに伝える必要があります。
ここでは、金融機関に信頼されるためのポイントを、項目別に解説します。
① 創業動機は“経験ゼロ”を逆手にとって語る
未経験であることを隠す必要はありません。むしろ、「なぜこの業種で起業しようと思ったのか」「どんな準備をしてきたのか」を正直に、熱意を持って説明することが大切です。
✅ 良い例
初めは趣味でネイルを始め、独学でネイル検定2級を取得しました。これまでに家族や友人のネイルを定期的に施術し、技術を磨いてきました。
ネイル作品はInstagramに投稿しており、フォロワーから“施術してもらいたい”という声もいただいています。(面談時には、これまでの施術実績がわかる写真とSNSの反応をポートフォリオとして持参)
❌NG例
子育てが一段落して時間に余裕ができたので、空き時間に自宅でネイルサロンを開業してみようと思いました。昔からネイルが好きだったので、自分のペースでできたらいいなと思っています。
✅良い例は、資格・実績・発信・他人からの評価を根拠に「経験は浅くても、事業としての信頼性がある」ことをアピールしています。
❌NG例の問題点は、以下の通りです。
・事業としての具体性がない(どんなサービスを提供するかが見えない)
・事業の継続性や収益性への説明がない
・「空き時間でやりたい」=本気度が低いと見られるリスク
・「ネイルが好き」だけで、技術や顧客の裏付けがない
金融機関は、「好き」や「生活のついで」ではなく、継続的に返済できる見込みがあるかを最も重視するため、こうした動機では不利になります。
創業の動機の書き方について詳しくはこちらの記事で解説しています。
▶審査に通る!創業計画書の「創業の動機」【業種別の記入例付き】
② 売上・利益計画には根拠のある数字を
収支計画は、単なる「希望」ではなく、根拠ある数字で構成されていることが前提です。
たとえば…
・1日平均◯人来店 × 客単価=売上
・月商から原価・固定費を引いた利益
・借入額に対する返済可能性(キャッシュフロー)
売上や利益に対して“数字の根拠”が見えるようになっていれば、未経験であっても納得感が出ます。
| 専門家からのアドバイス |
| 収支計画には、希望だけでなく「実際の相場」「地域の商圏データ」などの参考値を使うと、金融機関の評価が上がります。数値の裏付けが最大の武器です。 数値計画の作り方について詳しくはこちらの記事で解説しています。 ▶【創業計画書】事業の見通しの書き方8ステップ!資金調達のプロが完全解説 |
③ 実行スケジュールで「準備の具体性」を見せる
金融機関は、「この人は本当に開業に向けて動いているのか」という点を非常に重視します。
特に未経験者の場合、計画書に書かれた内容だけでは説得力に欠けるため、具体的な準備の進捗を示すことで本気度を伝えることが重要です。
以下のようなスケジュールや行動実績を明確に示すと、金融機関からの評価が高くなります。
| 項目 | 内容 |
| 物件の検討・契約時期 | 既に候補の物件を内覧済みで、今月中に契約予定(賃貸契約書のコピー・物件の説明書があれば◎) |
| 仕入先・業者との調整 | ・取引予定先と打ち合わせ済み、仕入れ価格の見積書を取得 ・見積もりを依頼し、仕入価格や納期の情報を収集、比較検討中。 |
| スタッフ採用の準備 | 必要な人員数や勤務条件を整理し、求人媒体や紹介会社の選定を行っている段階。採用スケジュールも草案として作成中。 |
| 集客・広報の準備 | ・SNSアカウントを開設済み。プレ開業の認知度アップに向けて投稿コンテンツを準備中。 ・チラシデザインを業者と打ち合わせ中 |
| 手元資金の使い方 | 開業準備資金(設備投資・広告費・運転資金)として●万円を自己資金から支出予定。用途を明記 |
こうした「行動ベースの情報」があると、単なる構想ではなく“実行段階”に入っていると判断され、信頼性が増します。
| 専門家からのアドバイス |
| 「いつやるか」「どの順番で進めるか」が曖昧なケースがよくあります。 開業に向けた工程表(スケジュール表)を作って、物件契約・備品購入・採用・告知などのタイミングを具体的に説明できると、金融機関は「準備力のある人」と評価してくれます。 また、契約書や見積書など、実際に準備を進めていることが裏付けられる資料を持参すると、審査の説得力が格段に上がります。 |
④ 誰がやるのか、チーム体制も記載
創業計画書では、「誰が事業をどう運営していくのか」を明確にしておくことが重要です。
特に未経験での起業の場合、「どの業務を誰が担当するのか」がはっきりしていると、金融機関は“事業の実行力がある”と評価します。
すべてを一人でこなす計画では、「本当に回るのか?」「負担が大きすぎないか?」と不安を与えることがあります。
そのため、専門的な部分や手が足りない業務は、外注や協力者に任せる形で、現実的な体制を示すことがポイントです。
【具体的な役割分担の例】
| 業務 | 担当・外注先の例 |
| 経理・会計処理 | 開業前からサポートを受けている税理士に依頼 |
| 集客・SNS運用 | WEBマーケティング会社と協力 |
| 顧客管理・予約対応 | ITツールを導入して業務効率化 |
| 仕入管理 | メインの商材は知り合いの卸業者と契約交渉中 |
| 専門家からのアドバイス |
| 創業計画では「何をやるか」と同じくらい、「誰がやるか」も重要です。 特に未経験の場合、“その道のプロが関わっている”という構図があると、金融機関は安心感を持ちます。 税理士やデザイナー、仕入れ先、経験者のパートナーなど、名前を出せる協力者がいれば、計画書に記載しておくのがおすすめです。 また、「外注先や支援者がいなくなったらどうするか」といったリスク対応も事前に考えておくと、面談でも慌てずに説明できます。 |
⑤ 創業計画書の作成に不安があるなら、専門家に相談
事業計画書の作成に不安がある方は、日本政策金融公庫の「創業計画書フォーマット」をベースにしつつ、創業支援に強い税理士などの専門家に相談するのがベストです。
創業計画書は、単なる“計画”ではなく、金融機関に対する「プレゼン資料」でもあります。
未経験からの起業であればなおさら、「本当にこの人にお金を貸して大丈夫か?」と審査される立場になるため、事業の魅力や実現性を、論理的かつ具体的に示す必要があります。
専門家は、実際に多くの融資案件を見てきており、「どこを見られるか」「どう補えば良いか」を熟知しています。
✅ 専門家に依頼するメリット
・金融機関の目線でブラッシュアップ
審査担当者がどこを見るかを熟知しており、通りやすい構成に整えてくれます。
・数値の根拠付けが明確になる
売上予測や収支計画を実際の業界相場に合わせて構築可能です。
・経験不足の補い方を戦略的に提案
実績がない部分をどう補完するか、協力者や他の制度の活用法も含めてアドバイスしてくれます。
・面談対策もサポート
よく聞かれる質問や回答の準備まで、金融機関とのやりとりに慣れた視点で支援
✅ どこに相談すればいい?
・商工会議所・商工会の創業相談窓口(無料)
・自治体の創業支援センター(事業計画作成支援・専門家紹介など)
・創業融資支援に強い税理士(有料だが専門性高い。起業全般の知識有。起業後の税務の相談も可能)
| 専門家からのアドバイス |
| 創業融資においては、「伝え方」が肝になります。 融資を申し込む方はどうしても「自分のことを一方的に説明する」形になりがちですが、審査をする側の視点で見ていくと、不安をどう払拭するか、論理的にどう説明するかが極めて重要です。 だからこそ、創業計画書は、経験豊富な専門家と一緒に練り上げることで、実現可能性の高い、説得力ある計画に変わります。 具体的な創業計画書の書き方についてはこちらの記事で解説しています。 |

4.融資面談で失敗しないための3つのポイント
面談は“審査の山場”。
未経験だからこそ「人柄」や「準備姿勢」が問われます。
事業計画書を提出した後に待っているのが、金融機関との面談です。
日本政策金融公庫の場合、担当者との1対1での面談が行われ、その内容が最終的な融資判断に大きく影響します。
未経験者にとって、この面談は“マイナス印象を挽回するチャンス”でもあります。
ここでは、面談を有利に進めるために押さえておきたい3つのポイントをご紹介します。
① 「誠実さ」と「本気度」を全身で伝える
面談では、知識や経験の多さよりも、「この人は信用できそうか」「本当にやる気があるか」という“人間性”の部分が見られています。
✅ やるべきこと
・計画書に書いてある内容を、自分の言葉で説明する
・質問に対して正直に、誠実に答える
・「なぜその事業をしたいのか」を熱意を持って語る
② よく聞かれる質問を事前に準備しておく
金融機関の担当者が面談でよく質問する項目はある程度決まっています。
事前に準備しておけば、緊張していても落ち着いて答えることができます。
【想定される主な質問例】
・なぜその業種で起業しようと思ったのか?
・業務経験がない中で、どうやって運営するつもりか?
・収益が出るまでの間の資金繰りはどうするのか?
・販路や仕入れ先はすでに決まっているのか?
✅ 質問に対しては、“数字”や“事実”で裏付けをしながら回答するのがポイントです。
融資面談で聞かれる質問や模範回答についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
▶日本政策金融公庫の面談|全質問と模範解答例で完全攻略
③ 清潔感ある服装・丁寧な態度で臨む
面談はビジネスの場。服装や態度も評価対象になります。
服装や態度などで、マイナスの印象を与えないように社会人として最低限のマナーを心がけましょう。
✅社会人として当然備えておきたい基本姿勢
・清潔感のある服装(スーツまたは業種にふさわしい服装)で面談に臨む
・約束の時間を守る(5分前行動が基本)
・丁寧なあいさつと落ち着いた受け答えを心がける
・メモや必要書類を忘れず持参し、準備を整えている姿勢を見せる
融資面談とはいえ、前提として“人間同士の対話”であることを忘れないようにしましょう。
面談時の服装については、こちらの記事で詳しく解説しています。
▶【男女別】日本政策金融公庫の融資面談時の服装ガイド
5.未経験者が活用すべき資金調達の方法
どれか1つだけではなく、複数を組み合わせること可能です。
資金調達の方法には、単に融資だけでなくいくつかの方法があります。
自己資金が少なかったり、経験が乏しかったりする場合でも、複数の制度と組み合わせることで資金調達の可能性はぐっと広がります。
ここでは、代表的な資金調達手段を3つ紹介します。
① 創業時に使える2つの融資制度|公庫+制度融資の併用も可能
創業時に利用できる代表的な融資制度は、2つ存在します。
・日本政策金融公庫の創業融資
・民間の金融機関(銀行や信金)を窓口とした制度融資(信用保証協会付き)
この2つは、どちらか一方を選ぶ必要はありません。
条件やタイミングに応じて、併用することも可能です。
また、一方の審査に落ちたとしても、もう一方で再チャレンジすることができます。
✅ 日本政策金融公庫の創業融資とは?
国が100%出資する政府系金融機関で、創業間もない企業や個人事業主に対して積極的に融資を行っている機関です。
【主な特徴】
・創業融資に積極的
・無担保・無保証人で融資を受けることが出来る
・申込から融資実行まで1ヶ月程度
日本政策金融公庫の創業融資について詳しくはこちら
▶日本政策金融公庫の創業融資|保存版完全ガイド
✅ 民間の金融機関(銀行や信金)を窓口とした制度融資(信用保証協会付き)
民間の金融機関(銀行や信金)と自治体(市区町村)、信用保証協会が連携して行う融資制度で、地域の創業者・中小企業を支援するための仕組みです。
【主な特徴】
・民間の金融機関(銀行や信用金庫)を窓口として申込
・要件を満たすことで、長期/固定/低金利の有利な条件で融資が受けられる
・保証協会付き融資とも呼ばれ、保証料が発生するが、創業間もない企業でも融資が受けやすくなる仕組み
・融資の申込から実行まで1ヶ月半~2ヶ月程度時間がかかる
制度融資について詳しくはこちら
▶制度融資とは?制度融資のメリット・デメリットを一般融資と比較【図解】
| 専門家からのアドバイス |
創業融資は、「日本政策金融公庫」と「制度融資」、この2つをうまく使いこなすことがカギになります。 この2つを併用することで、融資総額を増やすことも可能です。 |
② 補助金・助成金の活用(返済不要)
創業時の資金調達で、融資と並んで検討したいのが「補助金・助成金」です。
審査を通過する必要はあるものの、補助金や助成金は返済の必要がないため、融資と違い、資金のリスクを軽減できる非常に魅力的な手段です。
✅補助金・助成金の活用のメリット
・採択されれば、各補助金制度の対象となる経費の1/2~2/3程度が補助される
・自己資金の持ち出しを減らすことで、資金繰りの余裕が生まれる
✅補助金・助成金の注意点
・補助金・助成金には審査があるため、申請しても必ず受給できるわけではない
・経営計画書の内容で審査が行われるため、精度の高い経営計画書の作成が必要
・既に購入済み、支払済みの経費については対象外
・補助金は、原則、後払い。補助金の入金を待ってから経費の支払いをするのではなく、自己資金から経費の支払いをして事業を進めていきます。
・募集期間が限られているため、チャンスを逃さないよう情報収集が必要
✅ 補助金・助成金の例
| 補助金名 | 概要 |
| 小規模事業者持続化補助金 | 販路開拓・業務効率化の取組に係る経費を補助 |
| 創業支援補助金(自治体) | 自治体が独自に設ける創業者支援制度。補助額や対象経費は地域によって異なる |
| キャリアアップ助成金 | 非正規労働者を正社員化する、人材育成を行う、待遇を改善するなどの取り組みを行った事業主対して助成 |
補助金・助成金について詳しくはこちらの記事で解説しています。
▶補助金とは?7つの特徴と起業時に活用すべき補助金5選【専門家が厳選】
▶補助金と助成金の2つの共通点と4つの違い【専門家がおすすめする「補助金」「助成金」を一挙紹介!】
| 専門家のアドバイス |
補助金は実質的な資金調達手段として非常に有効です。 ただし、補助金は審査であり、たとえば小規模事業者持続化補助金でも採択率はおおむね50%前後と、決して簡単ではありません。 また、補助金は申請できる時期が限られており、申請準備にも時間がかかるので、間に合わないケースが多々あります。 ・中小企業庁・経済産業省の公式サイト |
③ クラウドファンディングでテスト販売&資金確保
未経験者でも「実績」を作れる、強力な資金調達手段
未経験での起業において、「実績がないこと」が最大の不安材料になります。
そこで、近年活用が進んでいるのがクラウドファンディングです。
これは、創業前に商品やサービスの企画を発表し、ネット上で共感してくれた支援者から資金を募る方法です。
「先に売る」ことで、未経験者でも事業の実行力とニーズの証明ができるのが最大の魅力です。
最近では、創業前にクラウドファンディングを活用して、先に顧客を集め、売上を得るという手法も増えています。
✅ クラウドファンディング活用の3つの効果
・売れるかどうかを事前に確認できる(=テストマーケティング)
→ 実際に購入希望者が集まるかを見ながら、商品コンセプトの修正も可能。
・集まった支援額・支援者数をそのまま「実績」として提示できる
→ 融資申請時の事業計画書に、「●名の支援者から合計●万円の資金を集めた」と記載でき、金融機関からの信頼性がアップ。
・「すでに顧客がいる状態」での創業が可能になる
→ 開業時点で応援してくれるファンがいるということは、未経験者にとって非常に大きな強みになります。
| 専門家からのアドバイス |
| クラウドファンディングは、未経験の起業家が実績と顧客の信頼を同時に得られる手段として注目されています。 支援者数や資金調達額をそのまま事業計画書に記載できるため、金融機関へのアピールにも効果的です。 ただし、「とりあえずやってみる」では成功しません。 また、クラウドファンディングは一度限りの資金調達であり、事業の継続的な収益にはつながりにくい面もあります。 初めて挑戦する場合は、MakuakeやCAMPFIREなど支援体制が整った実績あるプラットフォームを選び、必要であれば専門家のアドバイスも受けながら慎重に進めることをおすすめします。 |
6.まとめ|未経験でも創業融資は受けられる。そのために“準備”がすべて
創業融資は、経験がある人だけのものではありません。
未経験でも、「しっかりと準備している人」には、金融機関も前向きに評価してくれます。
重要なのは、「経験のなさをどう補うか」という視点です。
そのためには、
・今からでも可能なら。アルバイトや副業で業務経験を少しでも積む
・自己資金をしっかり準備する
・協力者や仕入先・販路などの体制を整える
・専門家やフランチャイズの支援を受ける
といった信用力を補う工夫が非常に重要です。
さらに、「説得力のある事業計画書」を作成することで、未経験というハンデは十分にカバー可能です。
そして、創業融資だけに頼らず、補助金や助成金など、複数の資金調達手段を組み合わせることで、起業の実現性をさらに高めることができます。
【次に取るべき行動チェックリスト】
✅ 開業予定の業種で少しでも実務経験を積む
✅毎月コツコツと自己資金を貯める
✅ 協力者・仕入先・販路の確保を進める
✅事業計画書のドラフトを作ってみる
✅創業支援に強い専門家に相談してみる
✅公庫・制度融資・補助金の情報を調べておく
「未経験だからできない。」とは言わせないために、やれることは全部やる!
その覚悟が未来を切り拓きます。
創業融資は、行動した人にこそ開かれるチャンスです。
まずは、今日からできる準備を一つずつ進めていきましょう。
そして迷ったときは、経験豊富な専門家の力を借りることも忘れずに。

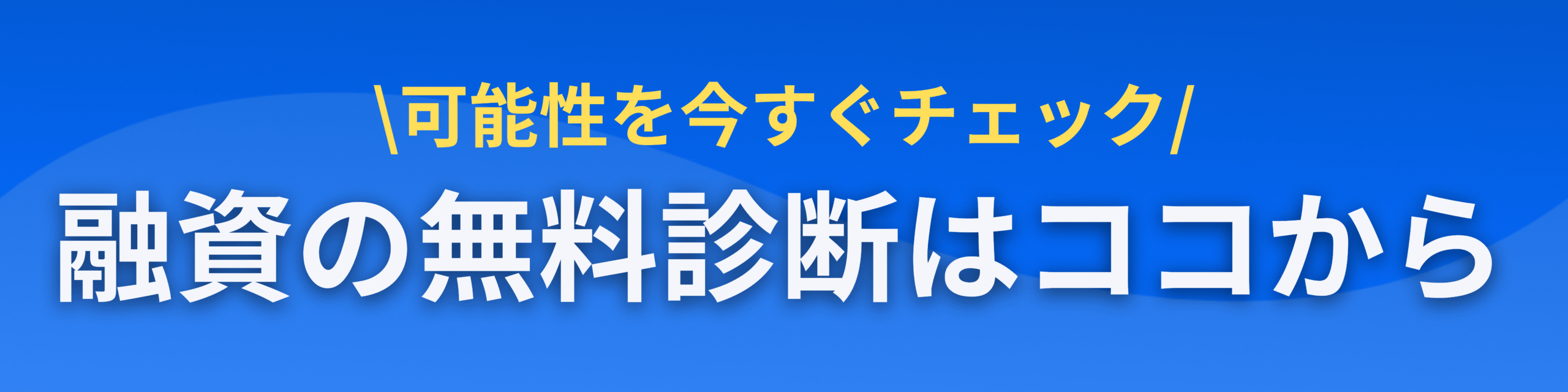

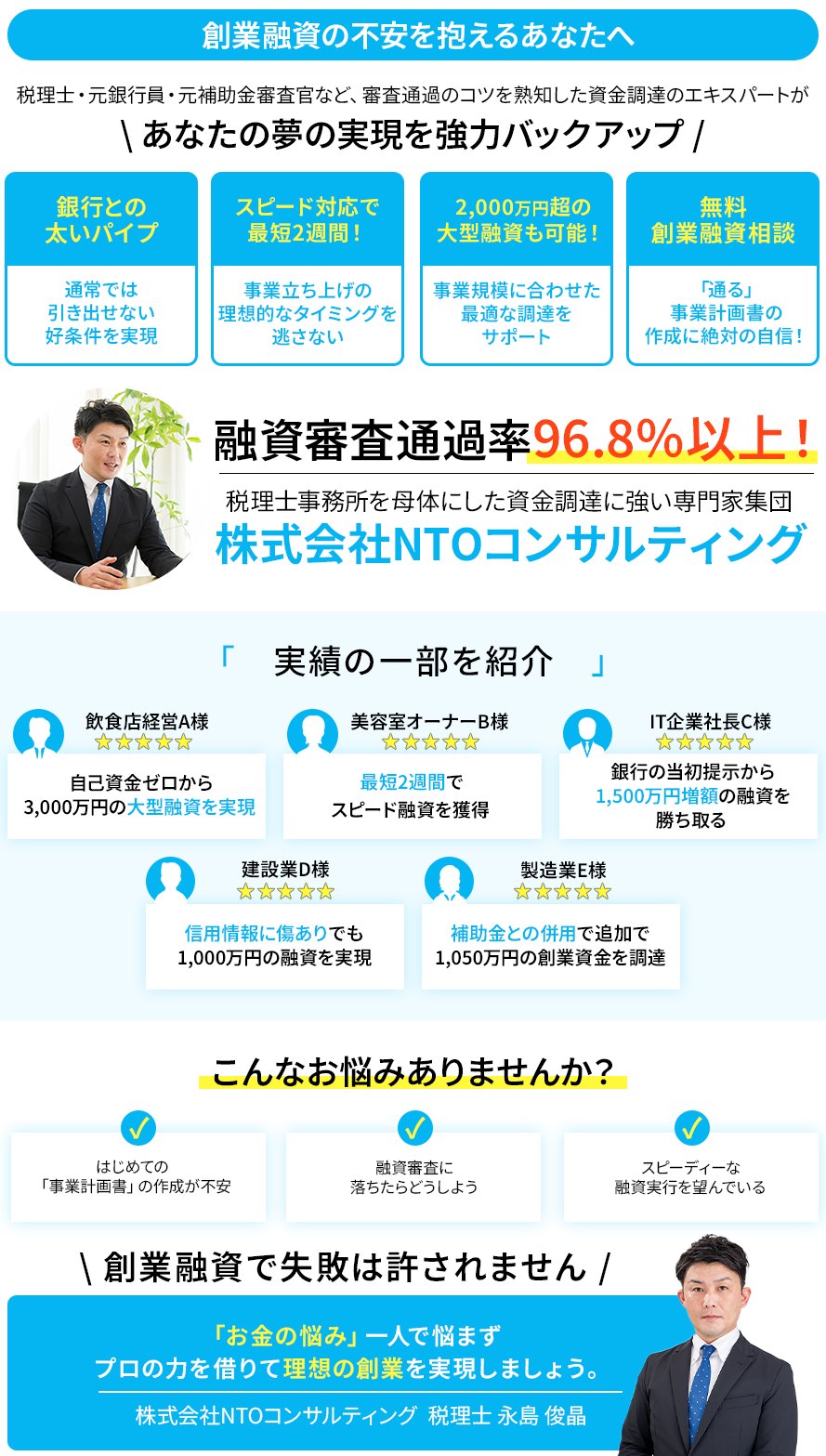
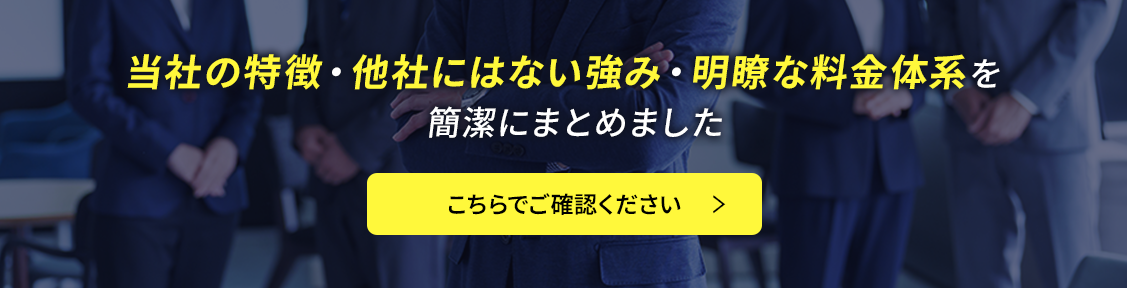
コメント