
「会社は設立したけれど、毎月どれくらいお金がかかるの?」
起業直後、多くの方が不安に感じるのが“会社を維持するためのコスト”です。
税理士報酬や社会保険料、家賃、会計ソフト代…。
こうした毎月かかる固定費に加えて、決算期や年末調整など、年に数回まとまって発生する費用もあります。
特に売上がまだ安定しない創業初期こそ、「いつ・何に・いくらかかるのか」を把握しておくことが、経営をスムーズに進めるための第一歩です。
結論:会社設立後には毎月の固定費用と年に数回のスポット費用が発生します。
中でも、社会保険料、税理士報酬、決算関連費用が大きな割合を占めます。
このページでは、4月設立・3月決算の場合をモデルケースとして、1年間の維持費を月別・費目別にわかりやすく解説していきます。
今後の事業計画や資金計画にぜひお役立てください。
目次
1.会社設立後のランニングコストは「固定費用」と「スポット費用」の2種類
会社を運営していくうえで必要なコストには、毎月必ず発生する固定費用と、時期によって一時的に発生する費用の2種類があります。
それぞれの特徴を知っておくことで、資金繰りに余裕を持った経営が可能になります。
✅ 毎月の固定費用… 給与や家賃、通信費、税理士報酬など、月ごとに一定額がかかるコスト。
✅ 季節・決算期などのスポット費用… 決算処理や税務申告など、年に数回だけ発生する一時的な費用。
定常費用とスポット費用を切り分けて管理することで、予期せぬ支出を防ぎ、経営の安定感が増します。
➡次章では、「毎月かかる定常費用」の内訳と金額感を詳しく解説していきます。
2.毎月かかる「固定費用」の内訳と目安金額
会社を設立すると、たとえ売上が1円もなくても、毎月確実に出ていくお金があります。
これが「固定費用」です。
特に創業初期はまだ売上が安定せず、利益が出ない月も多くなるため、「何もしなくても出ていくお金」を正確に把握しておくことが、キャッシュアウトによる倒産リスクを防ぐうえで非常に重要です。
固定費用には、オフィスの家賃や通信費などに加えて、役員報酬や従業員給与に伴う社会保険料、税金(源泉所得税)なども含まれます。
ここでは、まず社長ひとりで運営している場合の固定費用を、次に従業員を1名雇用している場合のコストを、それぞれ目安金額とともに紹介します。
2-1.社長1人(役員報酬:額面30万円)の場合にかかる固定費用
たとえ従業員がいなくても、社長自身に役員報酬を出している場合は、それに伴う源泉所得税や社会保険料の支払が発生します。
また、会計業務を自力でこなすのは現実的ではないため、会計ソフトや税理士との契約も必要です。
オフィスを借りていれば当然、家賃や水道光熱費、通信費も毎月かかります。
以下は、役員報酬を月30万円とした場合の主な費用項目と、その目安金額です。
| 費用項目 | 内容 | 金額目安(円) | 備考 |
| 役員報酬 (支給額) | 社長1名(額面30万円) | 約236,500円 | 社保・源泉税・住民税を差し引いた手取り額の目安(前年の年収360万円・扶養なし想定) |
| 源泉所得税 (預り金) | 役員報酬30万円に対する源泉所得税 | 約5,500円 | 会社が報酬から差し引き、税務署へ納付。※翌月10日まで or 年2回(納期特例届出済みの場合) |
| 社会保険料 (預り金) | 健康保険・厚生年金 (本人負担) | 約45,000円 | 報酬から差し引いた本人分。会社が法人負担分と合わせて毎月納付。 |
| 社会保険料 | 健康保険・厚生年金 (法人負担) | 約45,000円 | 報酬額に応じて、会社が別途支払う分。会社が毎月納付。 |
| 住民税 (預り金) | 前年の年収が360万円であると想定した場合の住民税 | 約13,000円 | 報酬から天引きし、会社が毎月市区町村へ納付。 |
| 家賃 | 小規模オフィスを想定 | ~100,000円 | 自宅兼用なら按分可能。飲食店や美容室などの店舗型事業では、立地や広さにより、10万円~数十万円となります。 |
| 通信費 | インターネット・電話 | 5,000~10,000円 | 使用量により変動 |
| 水道光熱費 | 電気・水道・ガス | 3,000~10,000円 | 使用量により変動 |
| 税理士顧問料 | 記帳代行・月次報告・相談 | ~30,000円 | 月額契約。 ※決算報酬(年1回)は別途発生するケースが多い。 |
| その他 | 消耗品・ソフト使用料 | ~10,000円 | 会計ソフト・文具など |
| 合計 | 493,000円~ | ||
※実際の保険料率や源泉税額は、地域・年度・年齢・扶養状況によって変動します。
✅ 用語の補足解説
■ 源泉所得税(預り金)とは?
会社が役員や士業などに報酬を支払う際に、「一部を差し引いて税務署に納める」仕組みです。
これは「会社が税金を預かって納める」役割をしているという意味で、「預り金」と呼ばれます。ただし、会社の口座からお金が出ていくので、キャッシュフロー上は“支出”と考えてよいです。
■ 社会保険料(本人負担・法人負担)の違い
本人負担(預り金):社長の報酬から天引きされる金額で、健康保険・厚生年金の一部です。
法人負担:同じく健康保険・厚生年金のうち、会社が負担する分。これは経費扱いになります。
→ 両方を合わせて、会社が毎月または、半年に1回まとめて納付します。
■ 住民税(特別徴収)
住民税は、前年度の所得をもとに市区町村から通知され、6月〜翌年5月まで毎月支払う仕組みです。会社は毎月の給与から天引きし、翌月10日までに各自治体へ納付します。
→給与計算の実務では、源泉所得税と同様に預り金として処理し、会社がまとめて納付します。
✅専門家からのアドバイス
「経費に入らない出費こそ、資金繰りには重要」
社会保険料の本人負担や源泉所得税は、帳簿上では経費にならなくても、会社の現金が出ていく“隠れ固定費”です。
キャッシュベースでの支出を正確に把握することで、創業初期の資金ショートを防げます
役員報酬を30万円とした場合、月に30万円が出て行くだけと思いがちですが、実際のキャッシュアウト(現金支出)はそれ以上になります。
💰 実際に会社が出すお金の内訳(例:役員報酬30万円の場合)
| 区分 | 金額(円) | 説明 |
| 手取り額 | 約236,500円 | 社会保険料(本人負担)と源泉所得税を差し引いた後の金額 |
| 源泉所得税 | 約5,500円 | 報酬から天引きして、会社が翌月10まで、または半年に1回に税務署へ納付 |
| 社会保険料 (本人負担分・預り金) | 約45,000円 | 報酬から天引きし、会社が法人分とあわせて毎月納付 |
| 社会保険料 (法人負担分) | 約45,000円 | 会社の経費として負担する分 |
| 住民税 | 約13,000円 | 前年の年収が360万円であることを想定。毎月納付 |
| 合計 | 約344,500円 |
💡ポイント解説
・社長には 約23万円しか入らないのに、会社は月34.4万円を支出しています。
・源泉所得税や社会保険料の本人負担分も、会社がいったん預かって納付する必要があるため、「支給額=支出額」ではありません。
・この構造を理解していないと、資金繰りで「足りない」「こんなに出ていくと思わなかった」という事態になりがちです。
・役員報酬は“額面”ではなく、“会社の総支出”で判断するのが資金繰りの基本です。
「役員報酬=30万円」と考えるだけでなく、その30万円を出すのに、実際はいくらの現金が出ていくのか”を冷静に見積もることが大切です。
2-2. 従業員1名(給与:額面25万円)を雇用した場合にかかる固定費用
従業員を雇うと、月給25万円を支払うだけで済むわけではありません。
実際には、社会保険料(会社負担分)や雇用保険、給与計算にかかる税理士費用の加算、オフィスの使用量増加分など、さまざまなコストが追加で発生します。
特に創業初期は、こうした「見えにくい固定費の増加」が資金繰りを圧迫することもあるため、雇用前に実際の支出額を把握しておくことが非常に重要です。
以下は、従業員1名、給与月25万円とした場合の主な費用項目と、その目安金額です。
| 費用項目 | 内容 | 金額目安(円) | 備考 |
| 給与(支給額) | 従業員1名 (額面25万円) | 約197,625円 | 社会保険料・雇用保険・源泉所得税・住民税を差し引いた手取り(※扶養なし・前年の年収300万円想定) |
| 源泉所得税 (預り金) | 給与25万円に対する源泉所得税 | 約4,000円 | 会社が給与から差し引き、税務署へ納付。※翌月10日まで or 年2回(納期特例届出済みの場合) |
| 社会保険料 (預り金) | 健康保険・厚生年金 (本人負担) | 約37,000円 | 給与から差し引いた本人分。会社が法人負担分と合わせて毎月納付 |
| 社会保険料 | 健康保険・厚生年金 (法人負担) | 約37,000円 | 給与額に応じて、会社が別途支払う分。会社が毎月納付。 |
| 住民税 (預り金) | 前年の年収が300万円であると想定した場合の住民税 | 約10,000円 | 給与から天引きし、会社が毎月市区町村へ納付。 |
| 雇用保険料 (預り金) | 雇用保険 (本人負担) | 1,375円 | 給与から差し引いた本人分。会社が法人負担分と合わせて年1回納付。 |
| 雇用保険料 | 雇用保険 (会社負担) | 約2,250円 | 給与額に応じて、会社が別途支払う分。会社が年1回納付。 |
| 通勤手当 | 実費・定期代 | 5,000〜15,000円 | |
| 税理士報酬加算 | 給与計算等 | 3,000円~ | 従業員追加に伴う顧問料加算(人数加算) |
| オフィスコスト | 人数に応じた水道光熱費・通信費等 | ~10,000円 | 人数が増えることで発生する間接費の増加分 |
| 合計 | 307,250円~ | ||
※実際の保険料率や源泉税額は、地域・年度・年齢・扶養状況によって変動します。
※雇用保険料の支払は年1回、1年分をまとめて支払います。
✅ 用語の補足解説
■ 雇用保険料(本人・法人負担)
雇用保険とは、従業員が失業した際の給付や再就職支援、育児・介護休業給付などを受けられる公的保険制度です。
雇用保険料は、従業員の給与から天引きする本人負担分と、会社が追加で支払う法人負担分に分かれています。
保険料率は業種によって異なりますが、2025年現在、一般の事業で本人0.6%、会社0.95%程度が標準的です。
→雇用保険料は毎月徴収されますが、実際の納付は年に一度「年度更新」時(6月〜7月)にまとめて清算されます。
※なお、社長1人だけの会社(法人代表者)では、雇用保険に加入することはできません。
雇用保険の対象は「労働者」に限られており、社長は原則としてその対象外です。
従業員に25万円を支給すると聞くと、「月25万円の支出」と誤解されがちですが、実際には社会保険・雇用保険・住民税・通勤手当・間接費などが積み上がり、会社の支出は月31万円以上になるのが現実です。
しかも、源泉税や保険料などは会社が一度に立替納付する形となるため、資金繰りにはシビアに効いてきます。
特に創業期は、売上よりも「固定費の総額」を正確に把握しておくことが、資金ショートによる倒産リスクを防ぐ最大の対策です。
3.年に1、2度/数年に1度かかる「スポット費用」の種類と目安
会社を運営するうえでは、毎月の固定費用に加えて、決算や法定手続きのタイミングで「スポット的に」発生する費用も避けて通れません。
これらは毎月発生するものではないため、つい見落としがちですが、支払額が大きくなることも多いため要注意です。
特に決算期(年度末)や年末調整の時期、設立から数年ごとに発生する更新手続き費用など、資金に余裕がない時期に重なると、資金繰りに悪影響を与えるリスクもあります。
ここでは、4月設立・3月決算の法人をモデルに、代表的なスポット費用の種類と目安金額をご紹介します。
✅ 年に数回かかるスポット費用とその発生タイミング
(公的手続き)
| 費用項目 | 発生時期 | 金額目安(円) | 備考 |
| 法人税の納税 | 3月決算の場合5月末 | 業績に応じる。 最低70,000円(均等割) | 赤字でも法人税の均等割りの支払が発生。 |
| 決算報酬(税理士) | 毎年決算後~申告期 (5月末) | 100,000~200,000円 | 顧問契約の範囲・規模により変動。毎月の顧問料とは別契約として請求されるのが一般的。 |
| 消費税の納税 | 3月決算の場合5月末 又は、中間納付あり | 業績に応じる。 | 課税事業者のみ。 顧客から預かった消費税を納める。 |
| 消費税の申告費用 (税理士) | 毎年決算後~申告期 (5月末) | 50,000円 | 毎月の顧問料とは別契約として請求されるのが一般的。 |
| 償却資産税の納税 | 通常納期は4回 第1回6月30日 第2回9月30日 第3回1月5日 第4回3月2日 | 資産に応じる。 | 1月31日までに申告を行った償却資産税の納税は6月以降 |
| 労働保険 (雇用・労災) | 7月10日まで | 52,500円 ※月給25万円の従業員を1名雇用している場合。 | 従業員負担分と会社負担分をまとめて支払。 ※一人社長の場合なし |
| 社会保険の算定基礎届対応 | 毎年7月 | ~20,000円 | 専門家に依頼する場合費用が発生 |
| 年末調整(所得税の還付) | 12月~1月の給与支払時 | 扶養家族の有無や保険料控除、住宅ローン控除などの内容によって異なる | 徴収しすぎた所得税の調整 |
| 年末調整 | 毎年12月~1月 | 15,000円~ | 人数に応じて加算 |
| 償却資産税の申告費用(税理士) | 毎年1月頃 | 15,000円~ | 税理士へ依頼する場合。資産数に応じ加算あり。 |
| 給与支払報告書の提出(税理士) | 毎年1月頃 | 顧問契約内 or 数千円加算 | 全従業員分を市区町村へ提出。 |
| 法定調書合計表の提出 | 毎年1月頃 | 顧問契約内 or 数千円~数万円加算 | 税理士報酬や外注費があると提出義務あり |
※労働保険料の計算において、年間賃金総額は、月給25万円 × 12ヶ月 = 3,000,000円で計算しています。
「税理士顧問契約があっても、すべてのサービスが含まれているとは限りません」
この一覧にあるような税務関連業務は、顧問契約の中に含まれることもありますが、決算書作成や消費税申告、年末調整などは“別料金”として扱われるケースが非常に多いのが実情です。
特に注意すべき点は以下の通りです。
■ 顧問料とは別に発生しやすい業務と費用
・決算報酬・消費税申告報酬:毎月顧問契約していても、年に1回の決算作業は別途10万〜20万円前後が一般的です。
・年末調整・法定調書・給与支払報告書:従業員の数に応じて、人数加算あり
・償却資産税の申告:固定資産を所有していれば必須だが、税理士契約に含まれていないことも
■ 法人税・消費税は「赤字でもゼロにならない」点に注意
法人税は、赤字の場合であっても最低限の「均等割(=最低7万円)」の納税義務があります。
消費税は、顧客から預かった消費税を納める仕組みのため、赤字であっても納税義務が発生することがあります。
■年末調整の還付=会社からの“一時的な立替払い”になる点に注意
まず、年末調整とは、1年間に給与から天引きしてきた源泉所得税の過不足を精算する手続きです。
従業員一人ひとりの扶養家族や保険料などを年末にまとめて確認し、本来納めるべき税額とのズレがあれば、還付または追加徴収を行います。
ここで見落としがちな“会社のキャッシュの動き”
年末調整の結果、還付金が発生した場合は、その金額を会社がいったん自社の資金で立て替えて支給します。
このお金は最終的に、翌年1月以降に納付する源泉所得税から相殺(控除)される仕組みですが、還付のタイミングと税金の控除タイミングに“時差”があるため、会社のキャッシュが一時的に減少するという点に注意が必要です。
特に、従業員数が多い場合や扶養控除・保険料控除が多く適用される場合は、還付金の総額が数十万円〜百万円単位になることもあり、資金繰りに影響を与えるケースもあります。
✅ 年に1.2度かかるスポット費用とその発生タイミング(その他)
| 項目 | 発生時期 | 金額目安(円) | 備考 |
| 商工会議所・法人会等の年会費 | 毎年加入日 or 事業年度に応じて | 5,000〜30,000円 | 加入任意。支払月は加入先により異なる |
| ドメイン・サーバー更新料 | 毎年1回 (契約更新月) | 1,000〜20,000円 | ホームページ・メールアドレス利用時 |
| 年額契約をしているクラウドサービス等 | 毎年1回 (契約更新月) | 10,000円~ | 会計ソフト・Google Workspace・Adobe等 |
| 保険料 | 毎年1回 (契約更新月) | 10,000〜50,000円以上 | 火災保険・PL保険・賠償責任保険など |
「税金以外にも“毎年確実にかかる支出”はたくさんある」
事業運営では、税金や社会保険だけでなく、いわゆる“管理系コスト”や“契約更新系の支出”も、確実に毎年発生します。
これらは、見積書・請求書ではなく「自動更新型」の引き落としで発生するケースが多いため、資金繰り上の盲点になりがちです。
■ よくある見落とし・注意点
・クレジットカードで自動課金されるため気づきにくい
→ 特に複数のクラウド契約がある場合、「年額請求×複数件」が同時に来ると痛手になります。
・年会費の支払月がバラバラ
→ 商工会議所や各種団体は、入会月ベースの請求であることが多く、「いつ来るかわからない支払い」になりやすい。
・火災保険やPL保険などは義務でなくても“万が一の備え”として推奨
→ 特に事業所を借りている場合は、貸主側が加入を義務付けていることもあるため、更新漏れは契約違反となる可能性も。
税務以外の費用も“事業を回すための必要経費”として認識し、可視化・平準化しておきましょう。
✅ 数年に1度かかるスポット費用とその発生タイミング
| 項目 | 発生時期 | 金額目安(円) | 備考 |
| 登記関連費 | 2〜10年ごと | 登録免許税 10,000〜30,000円+司法書士報酬 | 役員変更、本店移転、増資、目的変更など |
| 定款変更費用 | 必要に応じて | 登録免許税 10,000〜30,000円+司法書士報酬 | 商号・目的・機関設計などの変更時に発生 |
| 社用車の車検費用 | 2年ごと (新車は3年後) | 50,000〜150,000円 | 法人名義の車両に必須/整備費・税金・保険含む |
| 事務所の賃貸契約更新料 | 2〜3年ごと | 家賃1か月分が一般的 | 更新事務手数料・保証会社更新料が別途発生する場合も |
| パソコン・業務用機器の買替 | 3〜5年 | 50,000〜300,000円/台 | 法人向けPC、プリンター、iPad等の老朽化対応 |
| 社内規程・就業規則の作成・改訂 | 3〜5年 | 50,000〜150,000円(社労士依頼時) | 法改正・人員体制変更に合わせて改訂する必要あり |
「突発ではなく“周期的に来る出費”として、今から備える」
表にあるような支出は、1回の金額は大きくなりがちですが、予測できるものが多く、事前に準備すれば慌てず対応できます。
これらはすべて「いずれ必ず来る支出」であり、「忘れた頃にやってくる経費」です。
■ 見落としやすい注意ポイント
・登記費用や定款変更費用は、“何かを変えたい”ときに必ず発生
例:商号・本店移転・役員交代・増資・事業目的追加など
数万円〜十数万円の想定外出費になるため、都度資金準備が必要です。
・賃貸更新料は、定期的にまとまった支出となるうえ、最近では“家賃値上げ”の交渉が入ることもあります。
特に都市部では、更新時に「家賃1か月分の更新料」+「更新事務手数料」+「保証会社の更新料」が 同時に発生し、1回の更新で数十万円規模の支出になるケースも少なくありません。
さらに、近年では物価上昇やエリア再開発の影響で「次回からは月額家賃を引き上げたい」といった申し出があることもあり、資金繰りだけでなく契約条件の見直しリスクにも備えておく必要があります。
・社用車・備品の更新は“壊れてから”では遅い
創業時に導入したPCやタブレットは、3〜5年で一斉にガタが来ることも多く、まとめて出費 になるリスク大。
数年に1回の出費は、支払頻度が低い分、発生時のインパクトが大きいです。
特に創業3〜5年目は、「買い替え・更新・見直し」が一気に重なる傾向にあるため、中期経営計画や資金繰り表の中に“長期イベント”として組み込んでおくことが重要です。

4.1年分のランニングコストが丸わかり!支払スケジュール表(株式会社・3月決算の場合)
前章まで解説してきたように、会社を設立すると、毎月の固定費に加えて、年に1〜2回だけ発生するスポット費用も数多く存在します。
これらをきちんと把握していないと、予期せぬタイミングで資金繰りが厳しくなることも。
特に創業初期は、
「決算のタイミングで大きな支出があることを知らなかった」
「年に1回の費用を見落としていて、資金が足りなかった」
といったケースが少なくありません。
そこでこの章では、3月決算の株式会社をモデルに、
年間に発生するランニングコストを「月別・費目別」にまとめた完全スケジュール表を掲載しています。
📌 この表でわかること
・毎月かかる費用(家賃・役員報酬・社保など)
・年1回・数年に1回のスポット費用(決算料・登記費用など)
・どの月に、いくらくらい現金支出があるかの目安
事業計画や資金繰り表を立てる際の「土台」として、ぜひ活用してください。
✅ 年間支払スケジュール(完全版)
前提:3月末決算
役員1名(役員報酬300,000円)
従業員1名(給与250,000円)※残業なし・賞与なし
源泉所得税は納期の特例の届出済み
📌固定費…【固】と表記。給与・社会保険・顧問料・通信費・家賃など、毎月一定額発生する費用
📌スポット費用…【ス】と表記。決算・年末調整・社会保険手続き・労働保険など、年に数回だけ発生する一時的な費用
| 月 | 費用種類 | 内容 | 金額目安(円) | 備考 |
| 4月 | 固 | 役員報酬(支給額) | 約236,500円 | |
| 固 | 給与(支給額) | 約197,625円 | ||
| 固 | 社会保険料(本人負担+会社負担) (役員・従業員分) | 約164,000円 | ||
| 固 | 住民税(役員・従業員分) | 約23,000円 | 前年の年収による。※本年と同水準とする | |
| 固 | 税務顧問料 | 30,000円~ | ||
固 | 家賃・水道光熱費・通信費等 | 150,000円~ | 事業内容や規模による | |
| 4月合計 | 801,125円~ | |||
| 5月 | 固 | 役員報酬(支給額) | 約236,500円 | |
| 固 | 給与(支給額) | 約197,625円 | ||
| 固 | 社会保険料(本人負担+会社負担) (役員・従業員分) | 約164,000円 | ||
| 固 | 住民税(役員・従業員分) | 約23,000円 | 前年の年収による。※本年と同水準とする | |
| 固 | 税務顧問料 | 30,000円~ | ||
| 固 | 家賃・水道光熱費・通信費等 | 150,000円~ | 事業内容や規模による | |
| ス | 法人税の納税 | 最低70,000円 (均等割) | 業績に応じる。 | |
| ス | 決算報酬(税理士) | 100,000~ 200,000円 | 顧問契約の範囲・規模により変動。 | |
| ス | 消費税の納税 | 業績に応じる。 | 前税期間の確定消費税額に応じて中間納付あり。(2月決算の場合は10月末) | |
| ス | 消費税の申告費用 (税理士) | 消費税の申告がある場合のみ (50,000円) | 毎月の顧問料とは別契約として請求されるのが一般的。 | |
5月合計 | 971,125円~ | |||
| 6月 | 固 | 役員報酬(支給額) | 約236,500円 | |
| 固 | 給与(支給額) | 約197,625円 | ||
| 固 | 社会保険料(本人負担+会社負担) (役員・従業員分) | 約164,000円 | ||
| 固 | 住民税(役員・従業員分) | 約23,000円 | 前年の年収による。※本年と同水準とする | |
| 固 | 税務顧問料 | 30,000円~ | ||
| 固 | 家賃・水道光熱費・通信費等 | 150,000円~ | 事業内容や規模による | |
| ス | 償却資産税の納税(第1回) | 資産に応じる。 | 全4回に分けて納税 | |
| 6月合計 | 801,125円~ | |||
| 7月 | 固 | 役員報酬(支給額) | 約236,500円 | |
| 固 | 給与(支給額) | 約197,625円 | ||
| 固 | 社会保険料(本人負担+会社負担) (役員・従業員分) | 約164,000円 | ||
| 固 | 住民税(役員・従業員分) | 約23,000円 | 前年の年収による。※本年と同水準とする | |
| 固 | 税務顧問料 | 30,000円~ | ||
| 固 | 家賃・水道光熱費・通信費等 | 150,000円~ | 事業内容や規模による | |
| ス | 労働保険料(本人負担+会社負担) | 52,500円 | ※月給25万円の従業員を1名雇用している場合。 1年分をまとめて納付 | |
| ス | 社会保険の算定基礎届対応(専門家) | ~20,000円 | 専門家に依頼する場合費用が発生 | |
| ス | 源泉所得税(納期の特例) | 約57,000円 | 会社が預かった所得税1月~6月分を納付 | |
| 7月合計 | 920,625円~ | |||
| 8月 | 固 | 役員報酬(支給額) | 約236,500円 | |
| 固 | 給与(支給額) | 約197,625円 | ||
| 固 | 社会保険料(本人負担+会社負担) (役員・従業員分) | 約164,000円 | ||
| 固 | 住民税(役員・従業員分) | 約23,000円 | 前年の年収による。※本年と同水準とする | |
| 固 | 税務顧問料 | 30,000円~ | ||
| 固 | 家賃・水道光熱費・通信費等 | 150,000円~ | 事業内容や規模による | |
| 8月合計 | 801,125円~ | |||
| 9月 | 固 | 役員報酬(支給額) | 約236,500円 | |
| 固 | 給与(支給額) | 約197,625円 | ||
| 固 | 社会保険料(本人負担+会社負担) (役員・従業員分) | 約164,000円 | ||
| 固 | 住民税(役員・従業員分) | 約23,000円 | 前年の年収による。※本年と同水準とする | |
| 固 | 税務顧問料 | 30,000円~ | ||
| 固 | 家賃・水道光熱費・通信費等 | 150,000円~ | 事業内容や規模による | |
| ス | 償却資産税の納税(第2回) | 資産に応じる。 | 全4回に分けて納税 | |
| 9月合計 | 801,125円~ | |||
| 10月 | 固 | 役員報酬(支給額) | 約236,500円 | |
| 固 | 給与(支給額) | 約197,625円 | ||
| 固 | 社会保険料(本人負担+会社負担) (役員・従業員分) | 約164,000円 | ||
| 固 | 住民税(役員・従業員分) | 約23,000円 | 前年の年収による。※本年と同水準とする | |
| 固 | 税務顧問料 | 30,000円~ | ||
| 固 | 家賃・水道光熱費・通信費等 | 150,000円~ | 事業内容や規模による | |
| ス | (消費税の中間納付(3月決算の場合)) | 業績に応じる。 | 前税期間の確定消費税額に応じて中間納付あり。 | |
| 10月合計 | 801,125円~ | |||
| 11月 | 固 | 役員報酬(支給額) | 約236,500円 | |
| 固 | 給与(支給額) | 約197,625円 | ||
| 固 | 社会保険料(本人負担+会社負担) (役員・従業員分) | 約164,000円 | ||
| 固 | 住民税(役員・従業員分) | 約23,000円 | 前年の年収による。※本年と同水準とする | |
| 固 | 税務顧問料 | 30,000円~ | ||
| 固 | 家賃・水道光熱費・通信費等 | 150,000円~ | 事業内容や規模による | |
| 11月合計 | 801,125円~ | |||
| 12月 | 固 | 役員報酬(支給額) | 約236,500円 | |
| 固 | 給与(支給額) | 約197,625円 | ||
| 固 | 社会保険料(本人負担+会社負担) (役員・従業員分) | 約164,000円 | ||
| 固 | 住民税(役員・従業員分) | 約23,000円 | 前年の年収による。※本年と同水準とする | |
| 固 | 税務顧問料 | 30,000円~ | ||
| 固 | 家賃・水道光熱費・通信費等 | 150,000円~ | 事業内容や規模による | |
| ス | 年末調整(所得税の還付) | 扶養家族の有無や保険料控除、住宅ローン控除などの内容によって異なる。 | 徴収しすぎた所得税の調整 | |
| 12月合計 | 801,125円~ | |||
| 1月 | 固 | 役員報酬(支給額) | 約236,500円 | |
| 固 | 給与(支給額) | 約197,625円 | ||
| 固 | 社会保険料(本人負担+会社負担) (役員・従業員分) | 約164,000円 | ||
| 固 | 住民税(役員・従業員分) | 約23,000円 | 前年の年収による。※本年と同水準とする | |
| 固 | 税務顧問料 | 30,000円~ | ||
| 固 | 家賃・水道光熱費・通信費等 | 150,000円~ | 事業内容や規模による | |
| ス | 年末調整報酬(税理士) | 15,000円~ | 人数に応じて加算 | |
| ス | 給与支払報告書の提出(税理士) | 顧問契約内 or 数千円加算 | 全従業員分を市区町村へ提出。 | |
| ス | 法定調書合計表の提出(税理士) | 顧問契約内 or 数千円~加算 | 税理士報酬や外注費があると提出義務あり | |
| ス | 償却資産税の申告費用(税理士) | 15,000円~ | 税理士へ依頼する場合。資産数に応じ加算あり。 | |
| ス | 源泉所得税(納期の特例) | 所得税7月~12月分から、年末調整で還付した分を相殺した金額 | 会社が預かった所得税7月~12月分を納付 | |
| ス | 償却資産税の納税(第3回) | 資産に応じる。 | 全4回に分けて納税 | |
| 1月合計 | 831,125~ | |||
| 2月 | 固 | 役員報酬(支給額) | 約236,500円 | |
| 固 | 給与(支給額) | 約197,625円 | ||
| 固 | 社会保険料(本人負担+会社負担) (役員・従業員分) | 約164,000円 | ||
| 固 | 住民税(役員・従業員分) | 約23,000円 | 前年の年収による。※本年と同水準とする | |
| 固 | 税務顧問料 | 30,000円~ | ||
| 固 | 家賃・水道光熱費・通信費等 | 150,000円~ | 事業内容や規模による | |
| 2月合計 | 801,125円~ | |||
| 3月 | 固 | 役員報酬(支給額) | 約236,500円 | |
| 固 | 給与(支給額) | 約197,625円 | ||
| 固 | 社会保険料(本人負担+会社負担) (役員・従業員分) | 約164,000円 | ||
| 固 | 住民税(役員・従業員分) | 約23,000円 | 前年の年収による。※本年と同水準とする | |
| 固 | 税務顧問料 | 30,000円~ | ||
| 固 | 家賃・水道光熱費・通信費等 | 150,000円~ | 事業内容や規模による | |
| ス | 償却資産税の納税(第4回) | 資産に応じる。 | 全4回に分けて納税 | |
| 3月合計 | 801,125円~ | |||
| 契約更新月 | ス | その他、維維持費(年1回支払) (年会費・ドメイン・サーバー・クラウドサービス・保険料等) | 30,000円~ | |
| 年間合計 | 9,963,000円~ | |||
しかし、実際の経営ではこれだけでは済みません。
売上に応じて発生する変動費(仕入原価・外注費・広告費・販売手数料など)や、融資を受けている場合は毎月の返済も資金計画に含める必要があります。
つまり、事業計画や資金繰りを考えるときは、「固定費 + 変動費 + 融資返済 」を上回る売上の確保が基本です。
思ったよりお金がかかる」と後から慌てないためにも、この記事の内容をベースに、ご自身の事業に合わせた具体的な資金計画を立てることが、起業成功への第一歩となります。
5.まとめ|ランニングコストを把握することが、起業成功の第一歩
会社を設立すると、たとえ売上がゼロでも確実に発生する費用(ランニングコスト)があります。
本記事では、4月設立・3月決算の法人をモデルに、「毎月の固定費」と「年に数回のスポット費」を月別に整理し、1年間の維持コストを一覧化しました。
特に創業初期は、売上が安定しない中で、
✅ 社会保険料の立替
✅ 年末調整での還付金支出
✅ 決算時の税理士報酬や法人税・消費税の納付
など、「まとまった現金支出」が発生しやすいタイミングが重なります。
✅この記事の“押さえておくべき”ポイント
・固定費とスポット費の違いを理解することで、支出の予測精度が高まる
・顧問契約をしていても、決算報酬や年末調整は別費用となるケースが多い
・源泉所得税や社会保険料など、「預り金」であっても会社がいったん立替える現金支出がある
・固定費の合計は、役員1名+従業員1名の小規模法人でも月70〜80万円前後、年間約1,000万円近くになるケースもある
✅今すぐできる3つのアクション
1.自社の支出スケジュールを“可視化”してみましょう
→ 記事内の「年間支払スケジュール表」をベースに、自社の数字でシミュレーションする。
2.変動費・融資返済も含めた資金繰り計画を立てましょう
→ 固定費に目が行きがちですが、売上に連動する費用や借入返済も考慮が必要です。
3.予期せぬ支出に備え、キャッシュを確保しましょう
→ 突発的な支出や、税金・保険料の納付に備えた余裕ある資金計画を。
毎月・毎年、どれだけの現金支出があるのかを正確に把握しておくことは、経営における重要な準備の一つです。
さらに、年間でどれくらいの費用がかかるのかを知っておくことで、必要な売上や利益の目標もより明確になります。
「いつ・いくら売上を立てればよいか」を逆算できれば、資金ショートのリスクも未然に防ぐことができます。
ぜひこの記事の内容を、自社の資金計画と売上計画の土台として活用してください。

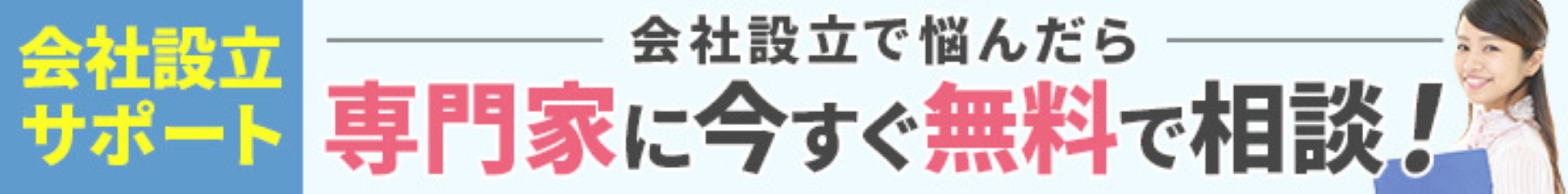
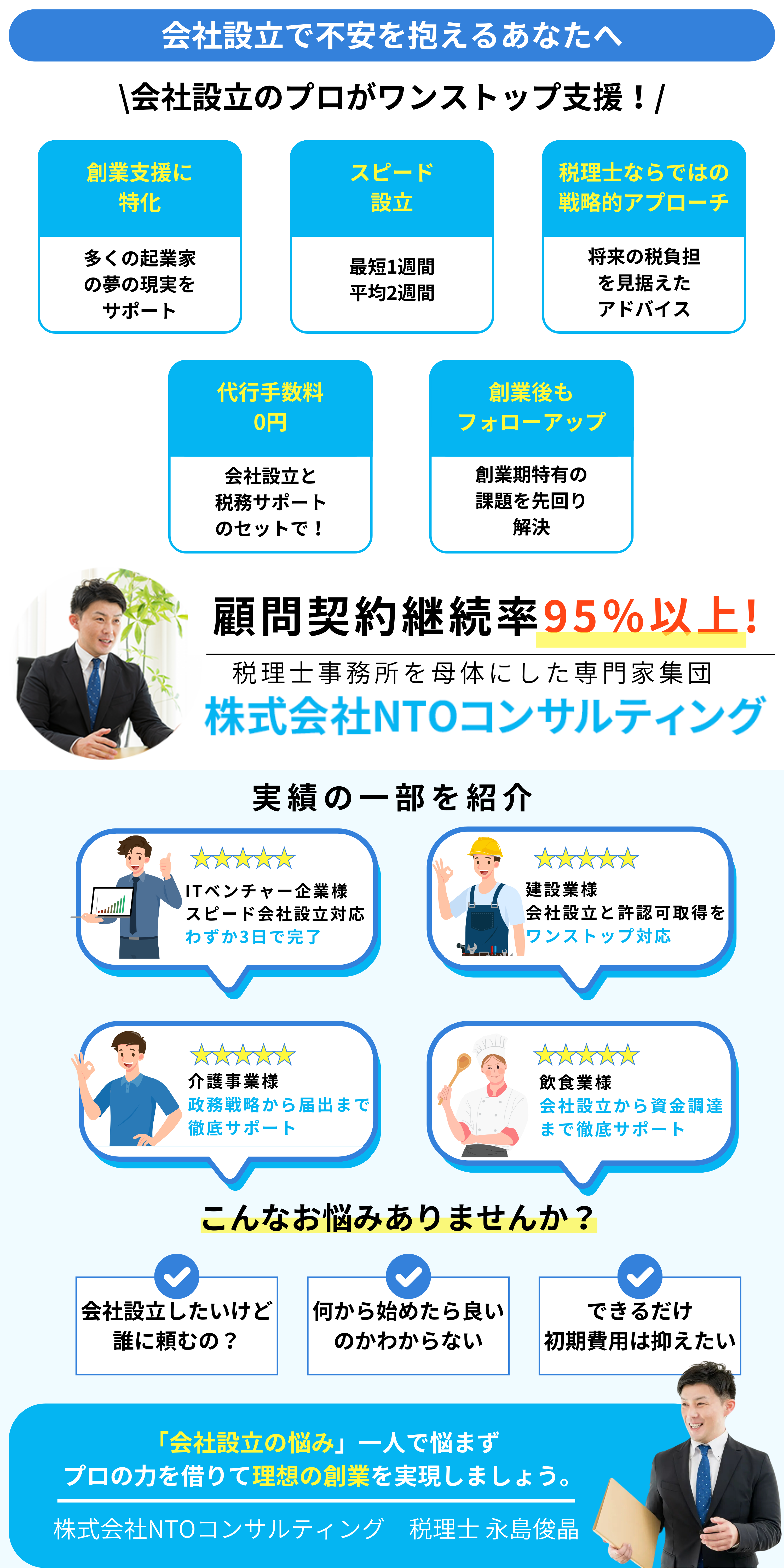
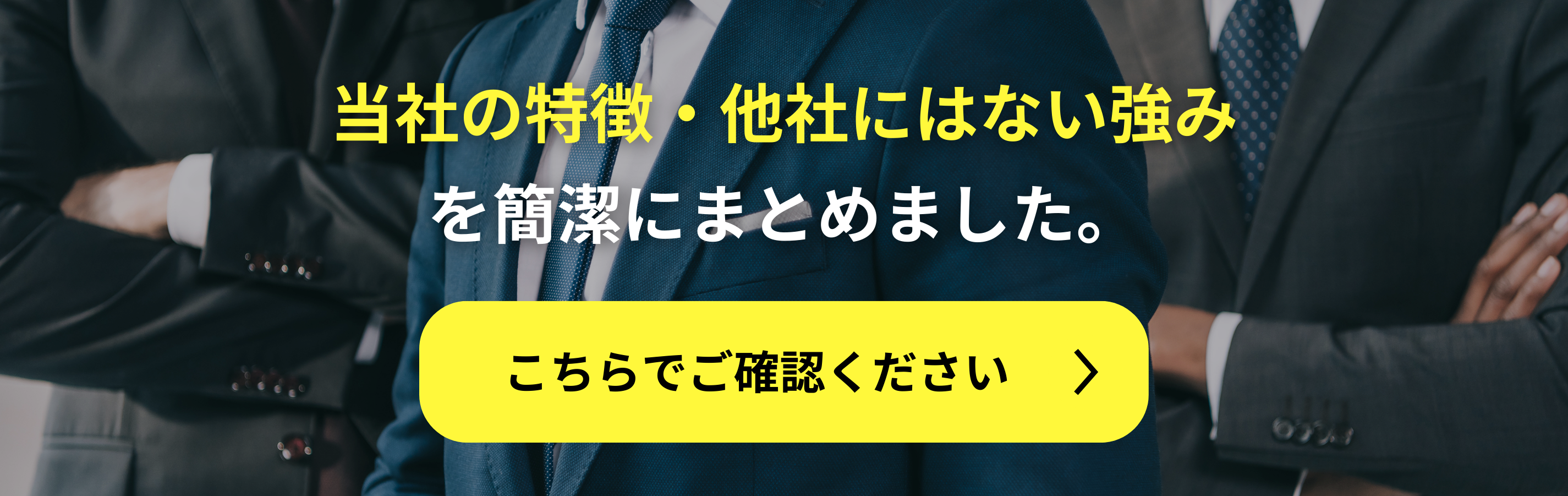
コメント