
「家族に給料を払えば経費になる」は本当?
「妻に経理を任せてるし、子どもにも発送を手伝ってもらってる」
「家族に払うお給料なんて、当然経費にできるでしょ?」
―そう考えている方は要注意です。
実は、家族への給与は原則として経費になりません。
税務署は「身内への給与=名目だけの支出では?」と厳しく見ているため、何も知らずに経費計上してしまうと、税務調査で否認され、ペナルティが発生することもあります。
ですが、ご安心ください。
きちんと条件を満たせば、家族への給与を全額経費にできる特例制度が存在します。
それが、「青色専従者給与」です。
正しく手続きを行い、妥当な金額を設定すれば、節税効果が期待できます。
この記事では、青色専従者給与の基本的な仕組みから、手続き方法、注意点までを、現役税理士がわかりやすく解説していきます。
目次
1.青色専従者給与とは?
青色専従者給与とは、個人事業主が「青色申告」をしている場合に限り、一定の条件を満たす家族に支払う給与を必要経費として認める特例制度です。
この制度を利用することで、家族に対して支払った給与を経費として所得から差し引くことができ、事業主の所得が分散され、結果として所得税・住民税の節税効果が期待できます。
ただし、この制度の利用には厳格な条件と手続きが設けられており、要件を満たさなければ一切経費として認められません。
そのため、制度を正しく理解し、適切に活用することが重要です。
※補足※ なぜ家族への給与は原則経費にできないのか?
税務上、家族などの「生計を一にする親族」への給与は、基本的に経費として認められていません。
なぜならば、「本当は働いていないのに、形だけで給与を払っている」ようなケースが多く見られるからです。
たとえば、家族に実際の仕事を頼んでいないのに、帳簿上だけ給与を出して節税しようとするようなケースです。
こうした“見せかけだけの支出(仮装経費)”を防ぐために、家族への給与は、特別な制度を使った場合に限って経費として認められることになっています。
その特別な制度が、今回解説する 「青色専従者給与」 なのです。
2.経費にできる?できない? 青色専従者給与のチェックポイント
では、具体的にどのような条件を満たせば、家族への給与が「青色専従者給与」として経費に認められるのでしょうか?
実は、この制度には要件があり、どれか一つでも欠けていると、経費として認められないリスクがあります。
ここからは、青色専従者給与を経費にするために必要な条件を具体的に確認していきましょう。
制度には、実際に家族が働いているか、金額が妥当か、きちんと届出されているかなど、満たさなければならない条件がいくつもあります。
「つい何となく」で進めてしまうと、あとから否認される可能性もあるため、事前にポイントを押さえておくことが大切です。
以下に、要件をわかりやすくまとめた早見表をご用意しましたので、ぜひチェックしてみてください。
| 条件内容 | 必要なポイント |
|---|---|
| ①青色申告をしていること | 「所得税の青色申告承認申請書」を提出して青色申告を行っていること。 |
| ②青色専従者の要件を満たすこと | ・生計を共にしている親族 ・12月31日時点で15歳以上 ・申告する年のうち6か月以上専従している (学生や他の仕事をしていないこと) |
| ③「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出しているか | 税務署へ「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出が必須 |
| ④給与額が妥当であるか | 相場と業務内容に見合った金額であること |
| ⑤実際に届出どおり支払っているか | 銀行振込など証拠が残る支払い方法が推奨 |
それぞれ詳しく解説していきます。
①青色申告をしていること
青色専従者給与は、「青色申告」をしている個人事業主だけが利用できる特例制度です。
白色申告ではこの制度を使うことができませんので、まずは「青色申告承認申請書」を税務署に提出し、承認を受ける必要があります。
青色申告承認申請書の提出期限は、原則として開業日から2か月以内です。
たとえば、1月1日に開業した場合は、3月1日までに提出しなければなりません。既に事業を始めている方が翌年から青色申告に切り替える場合は、その年の3月15日までが期限となります。
青色申告をすることで、専従者給与のほかにも最大65万円の青色申告特別控除や、30万円未満の固定資産の一括償却など、さまざまな節税効果が得られます。
まだ白色申告のままの方は、できるだけ早く青色に切り替えることをおすすめします。
補足:白色申告にも似た制度はある?
青色専従者給与は青色申告者のみが使える制度ですが、白色申告にも「事業専従者控除」という似たような仕組みがあります。
これは、一定の条件を満たす家族(配偶者や親族)が事業を手伝っている場合に、所得から一定額を控除できる制度です。
ただし、控除額には上限があり、配偶者の場合は最大86万円、それ以外の親族は最大50万円までしか認められません。
また、実際の給与額に関係なく、この上限額が固定で適用されるため、青色専従者給与のように柔軟に金額を決めることはできません。
つまり、白色申告でも一定の控除は可能ですが、節税効果や自由度の面では青色申告の方が圧倒的に有利です。
そのため、本格的に事業を行うなら、青色申告への切り替えを検討する価値があります。
②専従者の対象要件を満たすこと
青色専従者給与を支払うには、その対象となる家族が「青色専従者」としての要件をすべて満たしている必要があります。
以下の3つが主な条件です。
(1)その年の12月31日時点で15歳以上であること
→ 年齢要件により、中学生以下の子どもは対象になりません。
(2)その年を通じて6か月を超えて、もっぱらその事業に従事していること
→ ここでいう「従事」とは、日常的・継続的に仕事を手伝っていることを意味します。
夏休みや繁忙期だけの手伝いでは「専従」とは認められません。
また、他にパートや会社勤めなどをしている場合は、原則として「専従」とは見なされません。
事業に専念している状態が必要なため、他の仕事と掛け持ちしていると専従性が否定される可能性が非常に高くなります。
(3)実際に事業に関与していること(名義だけではない)
→ 税務署は「形だけ給与を払っている」ような名目だけの専従者には厳しく対応します。
きちんと実態があることを示すためには、仕事内容の記録(日報やシフト表)、業務指示書、作業の証拠などを保管しておくことが重要です。
※その年とは:1月1日から12月31日までの暦年を意味し、確定申告で適用される期間を指します。
税務ではこの期間を基準に要件を判断します。つまり、その年に青色専従者給与を経費にしたい場合、その年内にすべての要件を満たしていなければなりません。
この3つの要件をすべて満たしていなければ、たとえ給与を支払っていたとしても、経費として認められません。
専従者として扱うかどうかを決める際には、実態と継続性が何よりも重視されます。
③「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出していること
青色専従者給与を経費にするためには、「青色事業専従者給与に関する届出書」をあらかじめ税務署に提出しておく必要があります。
この届出をしていなければ、いくら実際に家族が働いていても、その給与を経費として認めてもらうことはできません。
この届出書は、事業主が「誰に」「どれだけの金額を」「どのような業務で」支払うのかを事前に明確にしておくための書類です。
税務署は、この届出書に基づいて専従者給与の妥当性を確認するため、未提出の場合は即座に否認の対象となります。
提出期限は以下のいずれか早い日です。
・事業開始から2か月以内
・その年の3月15日まで
たとえば、1月に開業した場合は、3月15日ではなく3月1日までに届出書を提出する必要があります。
この届出は「一度出せば終わり」ではなく、毎年内容に変更がある場合(例:支給額の変更、専従者の追加・削除)があれば、その都度、再提出が必要です。
なお、金額の変更があるのに届出を怠った場合、変更後の給与額は経費にできなくなるため、十分な注意が必要です。
④給与額が妥当であるか
支払う給与の金額が、実際の業務内容や勤務時間に見合っていることが重要です。
税務署は、給与の妥当性について特に厳しく審査します。
たとえば、同じ作業内容で一般のアルバイトに支払うよりも明らかに高い金額を家族に支払っていた場合、「名目だけの経費ではないか?」と疑われ、経費として認められない可能性があります。
給与額を決める際には、以下の点を参考にしましょう。
・同業種・同規模の事業者の給与水準(求人サイトや厚労省の統計など)
・作業内容や役割に対する一般的な相場
・その人が実際に何時間、どのような業務をしているか
また、家族だからといって特別扱いをするのではなく、第三者に支払う場合と同様の基準で金額を設定するのが原則です。
税務署に否認されないためには、「誰が・どのような業務を・どの程度やっているか」に対して妥当な報酬を支払っていることを、帳簿や業務記録などで裏付けられるようにしておく必要があります。
⑤実際に届出どおり支払っているか
青色専従者給与を経費として認めてもらうには、「届出書に書いた金額通りに、実際に支払っていること」が必要です。
つまり、「帳簿上に書いただけで、実際には支払っていない」ようなケースでは、経費としては認められません。
また、届出書に記載した金額の“範囲内”で支払うことも要件です。
届出額より少ない支払いであれば、実際に支払った金額までは経費として認められますが、届出額を超えて多く支払った場合には、超過分は原則として経費にできませんので注意してください。
【税務署に否認されないための3つのポイント】
以下のような点に注意して、きちんと「支払の事実」を残しておきましょう。
・銀行振込で支払うのがベスト:振込記録が証拠になります。
・現金払いをする場合は、出金伝票や領収書を必ず残す:口頭での説明は通りません。
・勤務実態の証拠も保管する:勤務日報やタイムカードなどをセットで保管しておきましょう。
💡 補足:金額変更や未払い時の注意点
● 金額の増額は変更届の提出が必要
年の途中でも変更届は提出できますが、増額には「相当の理由」が必要です。
例:資格取得により業務が増えた/他の従業員退職により業務が集中した など
正当な理由なく増額すると「利益操作」と見なされ、否認リスクがあります。
● 一時的に未払いとなる場合の取扱い
資金繰りの都合など「やむを得ない理由」があり、帳簿に明確に記載され、数か月以内に実際の支払いが行われていれば、経費として認められる可能性があります。
ただし、長期間放置された場合や勤務実態の記録が不十分な場合は、否認される可能性が高くなります。
青色専従者給与は「きちんと働いていること」と「実際に支払っていること」が大前提。そしてもうひとつ重要なのが「いくら支払うか」という金額の設定です。
続く第3章では、税務上のリスクを避けつつ、節税効果を最大化するための給与額の決め方を詳しく解説します。
3.青色専従者給与はいくらが最適?節税効果を最大化するための決め方
結論:節税額と家族の税負担のバランスが重要
青色専従者給与の金額は、「節税になるから高く設定すればよい」というものではありません。
むしろ、金額次第では家族の税負担が増えたり、経費として認められなかったりするリスクがあります。
事業主と専従者それぞれの所得税や住民税、事業税などを総合的にシミュレーションした上で、最適な金額を設定することが重要です。
青色専従者給与を決める手順と考え方
💡 前提として
本章では、配偶者を青色専従者とするケースを想定して解説しています。子どもや親族を専従者にする場合は、適用される控除制度や条件が異なるため、個別に確認することをおすすめします。
以下のステップで検討するのがおすすめです。
(1)年間38万円以上を目安に、仮の給与額を設定する
(2)事業主の利益を計算し、290万円以下になるかを確認する(→個人事業税が非課税になるライン)
(3)事業主と専従者の税率が近くなるように調整する(→税負担の総額を減らせる)
それぞれ詳しく解説していきます。
(1)年間38万円以上を目安に、仮の給与額を設定する
この金額は、配偶者控除の基準額です。
配偶者控除は年間最大38万円が所得控除として認められますが、専従者給与として38万円を超えて支給すると、この控除は使えなくなる代わりに、その給与を必要経費として事業の利益から差し引くことができます。
たとえば、妻に給与として年間40万円を支払えば、配偶者控除は受けられませんが、40万円を必要経費として計上できます。
(2)事業主の利益を計算し、290万円以下になるかを確認する
事業主の所得が年間290万円を超えると、個人事業税(都道府県税)が課税されます。
専従者給与を支払った後の利益が290万円以下であれば、事業税の負担を回避できる可能性があります。
たとえば、売上が700万円で、経費が300万円、専従者給与を120万円とした場合、利益は280万円となり、事業税の対象外になります。
ただし、無理に利益を削ると金融機関の評価に影響したり、資金繰りが厳しくなったりするため、事業全体のバランスも考慮することが必要です。
(3)事業主と専従者の税率が近くなるように調整する
所得税は収入が多いほど税率が高くなる仕組みです(累進課税)。
そのため、収入の多い事業主の所得を専従者給与として移すことで、低い税率で課税される専従者側に所得を分散できます。
たとえば、事業主の所得が500万円で、専従者の所得が0円の場合、200万円を専従者に支払えば、事業主の所得は300万円に減り、専従者の所得は200万円になります。
それぞれが比較的低い税率で課税されるため、世帯全体の税負担が軽減される可能性があります。
(4)その他検討しておきたい2つのポイント
節税の効果を最大限に活かすために、以下の点もあわせて検討しましょう。
■住民税・所得税の課税ライン
年収110万円を超えると住民税、160万円を超えると所得税の納税義務が発生。
このライン以下に抑えれば、配偶者の納税負担をゼロにできる。
■源泉徴収の発生ライン(月額8万8,000円)
これを超えると源泉徴収の手間が発生。
手間を避けたいなら、月額8万8,000円以下で調整するのもひとつの方法。
※2025年12月以降変更の可能性大。
実際の金額設定については、家族構成や所得状況によって最適解が変わるため、具体的なシミュレーションは税理士などの専門家に相談することを強くおすすめします。
4.まとめ|青色専従者給与を正しく活用して、家族への給与も節税に
結論から言えば、「家族に給料を払えば経費になる」というのは誤解であり、正しい制度の理解と手続きが必要不可欠です。
青色専従者給与は、きちんと要件を満たせば、家族への給与を全額経費にできる特例制度です。
しかし、要件を満たしていない場合や、届出を怠っている場合には、税務署から否認されてしまうリスクが高く、ペナルティが発生することもあります。
本記事では、
・青色専従者給与の基本的な仕組み
・経費として認められるための条件と手続き
・税務署に否認されないための注意点
・節税効果を最大化するための給与額の決め方
を、現役税理士の視点から具体的に解説しました。
特に重要なのは、「形式」ではなく「実態」です。
家族が実際に事業に従事していること、その対価として妥当な金額を、届出通りに支払っていることが問われます。
💡専門家に相談することで、リスクを抑えながら最大限の節税効果を得ることができます。
「本当にうちの金額で大丈夫?」「届出の内容に間違いはない?」と感じた方は、税理士に相談することをおすすめします。
制度を正しく使えば、家族の協力も事業の力に、そして節税にもつながる。
この機会に、青色専従者給与を最大限に活用していきましょう。

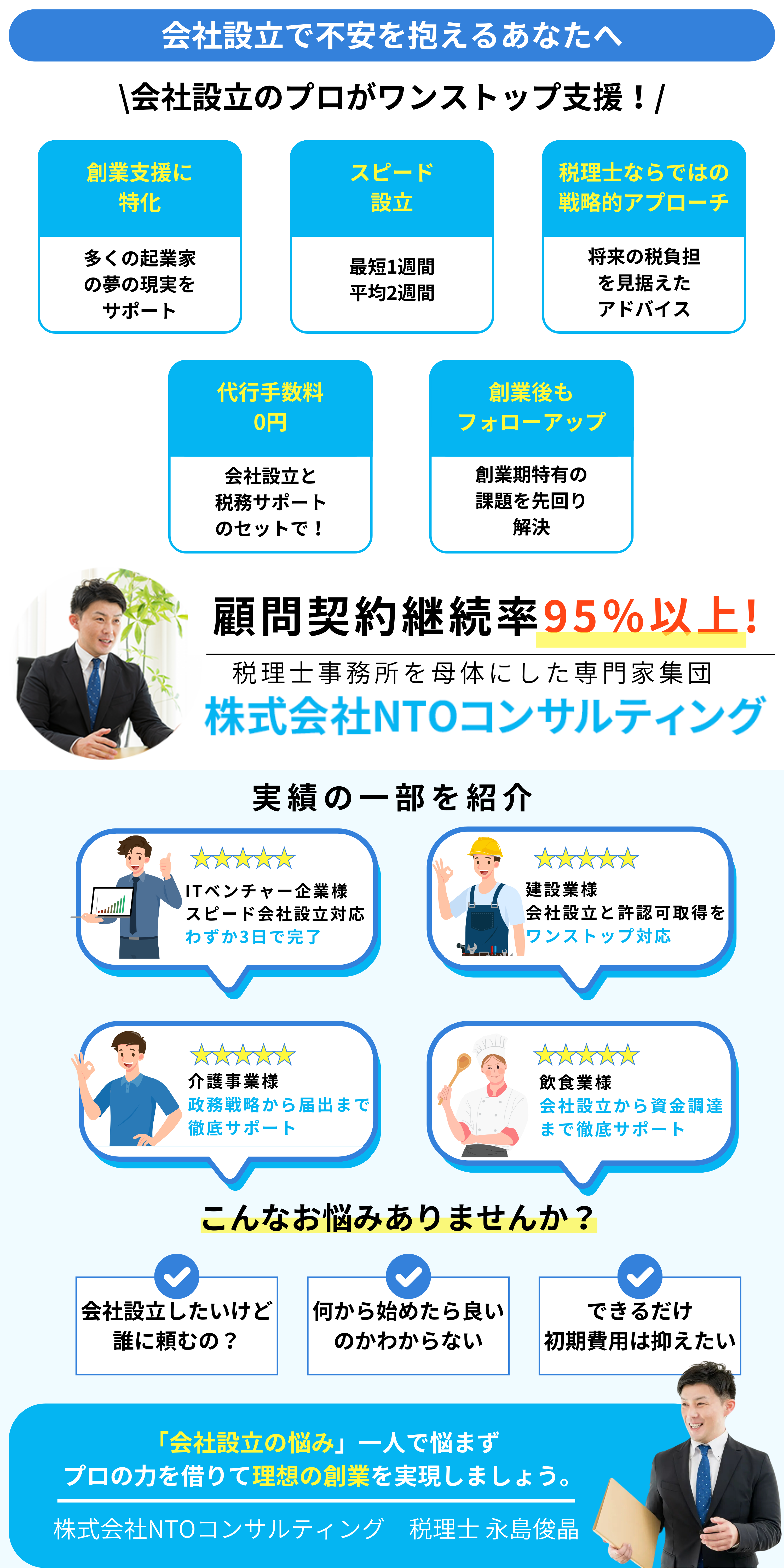
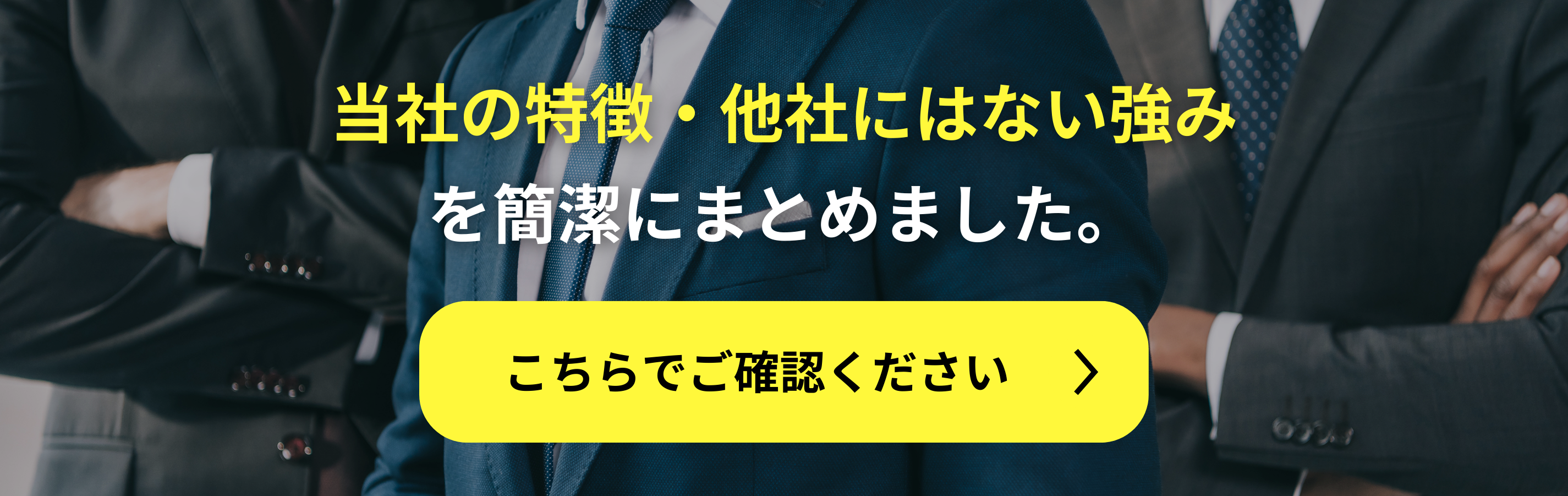
コメント