
「起業したいけど、どうやって資金を集めればいいの?」
そんな不安を感じている方にこそ、この記事は役立ちます。
結論から言えば、資金調達には大きく分けて5つの方法があり、
その中でも「日本政策金融公庫の融資」「信用保証協会付きの銀行融資」「補助金」の3つが、特に中小企業・個人事業主には現実的で実践しやすい手段です。
自己資金だけでは心もとない…。でも、無理な借入れや失敗した補助金申請でつまずきたくない…。
そんな起業家・事業者のために、この記事では 5つの資金調達方法の全体像から、実際に使える“鉄板の3つ”までを、専門家視点で丁寧に解説します。
それぞれの特徴や難易度、メリット・デメリットを整理しながら、あなたの事業に最適な資金調達手段を一緒に見つけていきましょう。
1.5つの資金調達の方法
資金調達の方法は、大きく分けて5つの種類に分類されます。
それぞれの特徴や難易度、メリット・デメリットを正しく理解し、自社の状況に合った手段を賢く選ぶことが重要です。
以下に、各資金調達方法の特徴や難易度、メリット・デメリットを一覧にまとめました。ぜひ参考にしてください。
【資金調達方法】
| 資金調達の種類 | 具体的な方法 | 調達額の目安 | 難易度 |
|---|---|---|---|
1-1.融資を受ける | ・日本政策金融公庫からの融資 ・保証協会付き銀行融資 ・プロパー融資 ・ビジネスローン | ~1,000万円 | ★★★ |
| 1-2.出資を受ける | ・エンジェル投資家からの出資 ・ベンチャーキャピタルからの出資 | 数百万円~数億円 | ★★★★★ |
| 1-3.資産を売却する | ・ファクタリング ・リースバック | 数十万円~数千万円 | ★★ |
| 1-4.補助金・助成金を活用する (おすすめ) | ・小規模事業者持続化補助金 ・ものづくり補助金 ・キャリアアップ助成金 など | 数百万円 | ★★★★ |
| 1-5.クラウドファンディングを活用する | 代表的なクラウドファンディングプラットフォーム ・CAMPFIRE(キャンプファイヤー) ・READYFOR(レディフォー) ・Makuake(マクアケ) | 数十万円~数百万円 | ★★★★★ |
※難易度は★1~5で表しています。★の数が多いほど、難易度の高い資金調達方法です。
それぞれ詳しく解説していきます。
1-1.融資を受ける:返済義務はあるが最も一般的な手段(おすすめ)
銀行や日本政策金融公庫などの金融機関から融資を受ける方法です。
返済義務があるものの、最も多くの事業者が活用しているスタンダードな資金調達方法と言えます。
ただし、融資を受けるには、返済能力を示すための事業計画書などの各種資料を作成し、審査をクリアしなければなりません。
金融機関からの融資には、大きく分けて次の4つの種類があります。
①日本政策金融公庫からの融資
②保証協会付き融資
③プロパー融資
④ビジネスローン
それぞれの特徴を理解し、状況に応じて最適な選択をしましょう。
①日本政策金融公庫からの融資
日本政策金融公庫は、個人事業主を始めとした小規模事業者や、中小企業、創業期の融資に最も積極的な金融機関です。
「なんとか融資をしたい」という姿勢で相談に乗ってくれるのが特徴です。
・創業融資に積極的
・融資実行まで1カ月とスピードが速い
・無担保・無保証人で借入ができる
日本政策金融公庫のデメリット
・資金調達金額に限度がある
一般的に800万円前後。数千万円、数億円単位での資金調達が必要な場合には適さない。
▶日本政策金融公庫の創業融資|保存版完全ガイド
②保証協会付き銀行融資
民間の金融機関(地方銀行や信用金庫)から融資をうける資金調達の方法の一つです。
保証協会付き銀行融資とは、万が一返済ができなくなってしまった時に信用保証協会という機関が代わりに銀行へ返済をしてくれる制度で、銀行にとってはリスクが低く、創業間もない事業者にとっては融資が受けやすくなるというものです。
・銀行との付き合いができ、今後も相談に乗ってもらえる
・借入の実績をつくることで信頼を得ることができ今後の借入の際に有利になる可能性もある
保証協会付き銀行融資のデメリット
・銀行内の融資審査と保証協会の融資審査の両方を通さないといけない
・申込から融資実行まで2カ月以上かかる
・保証人が必要
・金利の他に保証料の負担が発生する
▶保証協会付き融資とは?プロパー融資との違いを比較解説!
③プロパー融資
プロパー融資とは、銀行が信用保証協会の保証をつけず、独自の判断で行う融資です。
信用保証協会をつけず銀行が直接、融資を行います。
銀行が全額リスクを負うため、審査は非常に厳しくなりますが、その分、条件に柔軟性があり、大きな資金調達も可能です。
メリットも大きいですが、審査が極めて難しく単に業歴が長いだけでは受けることができません。
銀行にとってもリスクの高い融資のため、会社の財務状況など会社の信用度を示す必要があります。
・融資額の上限金額がない(事業としての信用力や財務内容に応じて決まる)
・プロパー融資を受けたという実績が会社の信用力になる
プロパー融資のデメリット
・審査が厳しい
・返済期間が短い
▶プロパー融資とは?信用保証協会付き融資との違いを比較解説!
④ビジネスローン
ビジネスローンとは、無担保・無保証人で借入が可能な資金調達方法です。
審査が非常にスピーディで、早いものでは即日融資を受けることができますが、金利が高い傾向にあり、資金繰りを圧迫し経営に悪影響を及ぼすリスクがあります。
可能な限り、ビジネスローンではなく、日本政策金融公庫や、信用保証協会付き融資の利用がおすすめです。
・無担保・無保証で借り入れが可能
・融資条件が優しい
・審査スピードが早く早いものでは即日で融資受けられる
ビジネスローンのデメリット
・金利が高い(2%~15%)
・今後銀行で融資を受ける際に影響がある可能性がある
1-2.出資を受ける:返済不要で成長を加速できる選択肢
出資は返済不要で資金を得られる反面、経営への影響も大きくなる方法です。
エンジェル投資家や、ベンチャーキャピタル(VC)から資金を出してもらう方法です。
将来的に大きく成長する見込みのある事業や、短期間で事業を拡大しやすいビジネスモデルに向いています。
投資家とのネットワークやアドバイスを得られる点も魅力ですが、経営に口出しされるリスクもあります。
ただし、出資を受けるには事業の成長性や独自性が求められ、資金調達までのハードルは高めです。
出資には、主に次の2つの方法があります。
①エンジェル投資家
②ベンチャーキャピタル(VC)
それぞれの特徴を理解し、状況に応じて最適な選択をしましょう。
①エンジェル投資家
エンジェル投資家とは、元経営者や実業家から出資を受けることによる資金調達の方法です。
返済義務のない資金を調達することができます。
個人投資家は出資をすることで株式を保有し、成長したときに売却をし利益を得たり、次世代の起業家支援を目的としています。
ベンチャーキャピタルとの違いは、調達できる資金の額が数百万円から数千万円と少額です。
資金面のサポートに加えて、これまでの豊富なビジネス経験に基づくアドバイスや人脈の紹介など、経営者にとって貴重な支援を受けられるのが大きな特徴です。
ただし、エンジェル投資家から出資を受けるには、魅力的な事業内容と将来の成長性が必要不可欠であり、実際に出資を受けられるのはごく一部の限られた企業にとどまります。
・出資金には利息を払う必要や返済の義務がない
・エンジェル投資家の多くは引退した経営者や実業家。豊富な経験や知識からアドバイスが受けられる
エンジェル投資家のデメリット
・経営干渉される可能性がある
・事業の独自性や成長性が期待できないと資金調達は難しい
②ベンチャーキャピタル(VC)
べンチャーキャピタルとは、投資会社から出資を受けることによる資金調達の方法です。
出資を受けるには、ベンチャー企業やスタートアップ企業など、大きな成長が見込まれる未上場の企業であることが必要です。
出資を受ける企業は、返済義務のない出資を受けることができ、融資限度額以上の資金調達額ができます。
出資を行った投資会社は、企業がまだ未上場の内に出資をし株式を買い、その企業が上場したり成長をした時に株式や事業を売却することで利益を得ることを目的としています。
・出資金には利息を払う必要や返済の義務がない
・数億円規模の融資限度額以上の資金調達ができる
・経営に関するアドバイスやサポートが受けられる
ベンチャーキャピタルのデメリット
・ベンチャーキャピタルの経営方針に従わなくてはならない
・成長が見込めないと判断された場合出資金の早期回収が行われる可能性がある
・事業の独自性や成長性が期待できないと資金調達は難しい
・審査が厳しい
1-3.資産を売却する:スピーディーだが一時的な手段
手持ちの資産を売却することで、短期間で資金を得られる手段ですが、継続的な資金調達には向かず、長期的には経営基盤に影響を及ぼす可能性があります。
売掛金や遊休不動などを売却し、現金化することで資金を得る方法です。
手続きが比較的シンプルで、急な資金ニーズにも対応しやすいため、スピーディーな資金調達手段として有効です。
ただし、この資金調達を行うためには、まず売却可能な資産を保有していることが前提です。
そのため、創業期の資金調達では、選択肢として現実的ではないでしょう。
また、資産を現金化する際には、利用する手段や業者によって、費用が掛かる点にも注意が必要です。
資産を売却して資金調達する方法には、主に次の2種類があります。
①ファクタリング
②リースバック
それぞれの特徴を理解し、状況に応じて最適な選択をしましょう。
①ファクタリング
ファクタリングとは売掛債権をファクタリング会社に買い取ってもらうことで資金調達をする方法です。
売掛債権をファクタリング会社に買い取ってもらうと、売買手数料を引いた金額が振り込まれ、売掛債権を早期に現金化することができます。
この方法は、資産を処分するのではなく、将来入ってくるはずの資金を前倒しで受け取るイメージに近いため、急ぎの資金調達手段として有効です。
ただし、手数料がかかることに注意が必要です。
自社とファクタリング会社のみで行う2社間ファクタリングと、自社と取引先とファクタリング会社とで行う
3社間ファクタリングがあります。
・最短、即日で資金調達ができる
・担保や保証人なして資金調達ができる
・自社の業績や財務状況にかかわらず資金調達ができる
ファクタリングのデメリット
・ほかの資金調達方法と比べると手数料が高い(2社間ファクタリングが10%~30%、3社間ファクタリングでは1%~10%)
・3社間ファクタリングを行う場合取引先からの信用落ちてしまう可能性がある
・危険なファクタリング業者もある
▶資金調達の最終手段!ファクタリングの正しい活用法
②リースバック
リースバックとは、自社が保有する不動産や設備などの資産をいったん売却し、売却後もその資産をリース(賃貸)という形で使い続けることで資金を調達する方法です。
資産を手放しつつも、業務には支障なく引き続き使用できるため、資金繰りが厳しいときや急な資金ニーズがある場合に活用されることがあります。
売却後はリース料(賃料)を継続的に支払う必要がある点には注意が必要です。
・短期間で使い道が自由なまとまった資金の調達が可能
・担保や保証人なして資金調達ができる
・信用力の低い事業者でも利用しやすい
・売却後もその事業を継続できる
リースバックのデメリット
・長期的にはコストが割高になる可能性がある(賃料が一般的な相場より高く設定されることが多い)
・売却価格が相場より低くなることが多い
・売却後の自由度が下がる(改修工事などが自由に出来なくなる)
1-4.補助金・助成金を活用する:返済不要の“もらえる資金”(おすすめ)
補助金・助成金は、返済の必要がない“もらえるお金”として、事業者にとって非常に魅力的な資金調達手段です。
採択されるためには準備や申請の手間がかかりますが、活用できれば事業の立ち上げや拡大を強力に後押ししてくれます。
条件に合致し、しっかりと申請書を作り込めば、数十万円〜数百万円、時には1,000万円超の資金が「返済不要」で受け取れることもあります。
ただし、審査に通るためには、事業の目的や具体的な計画、見込まれる成果などを丁寧に書き上げる必要があり、一定の時間と労力がかかります。
ただし、補助金の多くは「後払い制度」です。
つまり、まずは自己資金で事業を実施し、その後に経費精算という形で補助金が支給されます。
そのため、採択されても、最初に必要な資金を準備できないと事業が進められない可能性があるため、注意が必要です。
・返済不要でもらえるお金(自己資金の負担を軽減)
・新規事業や設備投資の後押しになる
・採択されることで金融機関や取引先からの信用が得られる(事業の健全性や将来性が公的に認められる)
補助金のデメリット
・審査をクリアしなければもらえない
・原則後払いのため先に支払いが必要
・入金まで時間と手間がかかる
・用途が厳格に制限され、自由に使えない
【主な補助金・助成金の紹介】
■ 小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)
小規模事業者が、販路開拓や業務効率化などを目的とした取り組みに対して支給される補助金です。
機械装置、チラシ作成、店舗改装、広告宣伝など、比較的幅広い経費が対象になるため、初めて補助金を申請する方にも取り組みやすい制度です。
【対象】商業・サービス業:5人以下、製造業その他:20人以下の小規模事業者
【補助額】上限50万円〜200万円(申請枠による)
【補助率】2/3(※申請枠により異なる)
【ポイント】採択率が比較的高く、汎用性のある使いやすい補助金
■ ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)
中小企業が新製品・新サービスの開発や、生産プロセスの改善などに取り組む際に活用できる補助金です。
機械設備の導入やシステム構築、試作品開発など、比較的高額な投資に対応している点が特徴です。
【対象】中小企業・小規模事業者(業種により細かな条件あり)
【補助額】100万円~2,000万円
【補助率】1/2~2/3(条件による)
【ポイント】高額な設備投資や開発費用を“返済不要”でまかなえる点が最大の魅力です。
■ キャリアアップ助成金
キャリアアップ助成金は、非正規雇用労働者(パート・アルバイト・契約社員など)を正社員化するなどの処遇改善を行った事業者に対して支給される助成金です。
人材確保や定着率向上を目的とする事業者にとって、費用負担を軽減しながら働きやすい職場環境づくりを進められるメリットがあります。
【対象】有期雇用・パート・アルバイトなど非正規雇用の労働者を雇用している事業者
【代表的なコース】正社員化コース(例:有期→正社員に転換)
【支給額の例】正社員化1人あたり最大57万円(条件により加算あり)
【ポイント】採用活動や従業員の定着支援にもつながるため、「人に投資する経営」を進めたい中小企業にとって有効な制度です。
1-5.クラウドファンディングを活用する:共感を資金に変える方法
クラウドファンディングは共感と応援を資金に変える、新しい資金調達の形です。
クラウドファンディングとは、インターネットを通じて不特定多数の人に資金の提供を呼びかけ、事業趣旨に賛同した人から資金を集める資金調達の方法です。
支援者には商品やサービスの提供によるリターンや金銭的リターンがあります。
製品開発、地域活性、社会貢献などとの相性が良く、資金調達と同時にプロモーション効果も期待できます。
一方で、魅力的なページ作成や事前の戦略、集客努力が必要です。
・融資のような条件や厳しい審査がなくどのような企業でも資金調達ができる可能がある
・資金調達と同時に宣伝することができる
・商品やサービスに需要があるのかテストマーケティングができる
クラウドファンディングのデメリット
・資金が集まるとは限らない。(成功率平均30%)
・準備や広報に時間と手間がかかる
・クラウドファンディングのプラットフォームへの手数料が発生する(20%前後)
・商品サービスを盗用される可能性がある
【主なクラウドファンディングのプラットフォームの紹介】
■ CAMPFIRE(キャンプファイヤー)
日本最大級のクラウドファンディングプラットフォーム
個人の挑戦から社会課題、商品開発まで、幅広いジャンルに対応
■ READYFOR(レディフォー)
社会貢献型に強いクラウドファンディングプラットフォーム
医療・福祉・教育・地域活性など、非営利プロジェクトに強く、その分、審査が比較的厳しく、信頼性重視の傾向がある
■ Makuake(マクアケ)
新商品・先行販売に特化したEC型のクラウドファンディングプラットフォーム
家電・ガジェット・食品など、製品の先行販売に強い。集客力が高い為、資金調達だけでなくPRや販路拡大にも有効活用できる。

2.超実践的! 中小企業・個人事業主が実践すべき資金調達3選
これから資金調達を考える、中小企業、個人事業主にとってまず検討すべき方法は以下の3つです。
2-1.日本政策金融公庫からの融資
2-2.保証協会付き銀行融資
2-3.補助金の活用
これらは、再現性が高く、実践しやすく、かつ調達後の経営に悪影響を与えにくいという点で、非常に有効な選択肢です。
以下、事例を交えてそれぞれ詳しく解説します。
2-1.日本政策金融公庫からの融資:創業期の「最初の一歩」に最適
創業期の資金調達は、まず日本政策金融公庫からの融資を検討しましょう。
なぜなら、創業期の資金ニーズに応じた制度が豊富に揃っており、しかも審査姿勢が“前向き”だからです。
特に、事業実績のない人でも、「創業計画書」をしっかり書き込めば、無担保・無保証での融資を受けられる可能性が高い点は大きなメリットです。
【日本政策金融公庫からの融資を検討すべき人】
・創業したばかり、またはこれから開業する予定の人
・まずは100万円~1,000万円くらいを目安に資金が必要な人
・リスクを最小減に抑えて資金調達したい人
【注意点】
・高額融資(1,000万円超)を狙うには、自己資金比率や実績が問われるためハードルが高い
・事業計画書の内容が甘いと審査に落ちることもあるため、専門家にアドバイスをもらうのがおすすめ。
とくに初めての申請では、自分では気づけない“落とし穴”を指摘してもらえるので、成功率が大きく変わります
【実例】
飲食店を開業した40代男性
→ 自己資金400万円+公庫融資995万円で開業。融資実行まで約1か月。
→ 事業計画書の作り込みと、面談時の想いの共有がポイントとなり、無担保・無保証で融資を受けられることに。
日本政策金融公庫の創業融資について詳しくはこちらの記事で解説しています。
▶日本政策金融公庫の創業融資|保存版完全ガイド
2-2.保証協会付き銀行融資:銀行との“信頼関係”を築きたい人向け
保証協会付き融資は、民間の銀行から借入する際に、信用保証協会の保証をつけて行う方法です。
銀行にとっては「貸倒リスクが減る」、事業者にとっては「銀行融資が通りやすい」というWin-Winの関係が成り立つ仕組みです。
特に、自治体の制度融資と組み合わせれば、金利や保証料の一部が補助されることもあり、条件的にもかなり優遇されるケースがあります。
事業をしていく上では、銀行とのお付き合いは必ず必要になります。
日本政策金融公庫の融資を受けた後には銀行からの融資を受けることをお勧めします。
【保証協会付き銀行融資を検討すべき人】
・既に日本政策金融公庫からの融資を受けており、追加融資が必要な人
・将来、銀行との太い取引を考えている
【注意点】
・融資実行までに2〜3か月かかることも。「急ぎの資金」には不向き
・銀行審査+保証協会審査の“二重チェック”があるため、書類の完成度がかなり重要
・保証料が別途発生するため、実質的な金利は少し割高になることも
銀行選びのコツ:おすすめは信用金庫
保証協会付き融資を検討するなら、金融機関の選び方も重要です。結論から言うと、おすすめは「信用金庫」です。
保証協会付き融資は、都市銀行・地方銀行・信用金庫・信用組合など、さまざまな金融機関が窓口となっています。
しかし、金融機関によって姿勢やスタンスが大きく異なります。
都市銀行や地方銀行は株式会社であり、利益を重視する傾向があります。
特に都市銀行は大企業との取引が中心であり、中小企業への融資には慎重です。
創業間もない事業者にとっては、審査のハードルが高く、実際に断られるケースも少なくありません。
一方、信用金庫は“地域密着型”の金融機関です。
地域の中小企業や個人事業主を主な顧客としており、相互扶助の精神をもとに運営されています。
地域の事業者の成長を応援する立場から、比較的親身に相談に乗ってくれる傾向が強く、創業期の融資にも柔軟に対応してくれることが多いです。
【実例】
ペットサロンを開業した50代男性
→ 自己資金100万円+公庫融資650万円+保証協会付き銀行融資310万円で開業。
→ 事業計画書の作り込みと、徹底した面談対策により未経験から1,000万円近くの資金調達に成功。
保証協会付き融資について詳しくはこちらの記事で解説しています。
▶保証協会付き融資とは?プロパー融資との違いを比較解説!
2-3. 小規模事業者持続化補助金:販路拡大に活用できる“もらえる資金”
補助金の活用は、返済不要で“もらえるお金であるため、事業成長のアクセルになります。是非、積極的に活用したい制度です。
中でも、小規模事業者持続化補助金は、創業間もない事業者でも使える、おすすめの補助金です。
補助上限額は原則50万円〜200万円(枠によって異なる)で、補助率は対象経費の2/3。
例えば、75万円のチラシ制作費を使った場合、そのうち50万円までが補助されるイメージです。
対象となる経費の幅が広く、以下のような施策に活用できます。
・生産販売拡大のための鍋、オーブン、冷凍庫、冷蔵庫
・新たなサービス提供のための製造・試作機
・特殊印刷プリンター、3Dプリンター
・販路拡大のためのチラシ・パンフレット
・郵送によるDMの発送
・新聞、雑誌等への商品・サービスの広告
・看板
・ホームページ、ECサイトの構築
・動画作成
・WEB広告費
・SNSに係る経費
・店舗改装、バリアフリー工事
・移動販売を目的とした車の内装、改造工事
・新たな包装パッケージにかかるデザイン費用
【小規模事業者持続化補助金を検討すべき人】
・売上アップのために、販路開拓や業務効率化の取組を検討している人
【注意点】
・補助金は後払いです。まず自己資金で支払い→実績報告→精算という流れになるため、資金繰りに余裕がないと活用しにくい
・書類(経営計画書・事業計画書)は数字だけでなく“ストーリー性”も重要。
読み手(審査員)が納得できる計画に仕上げる必要があります
・申請タイミングや対象経費の使い方など、細かなルールが多い
→ ルールを守らないと不採択や返金対象になることも
専門家のサポートがおすすめ
持続化補助金は採択率が50%前後と言われる中、しっかり準備すれば十分チャンスがあります。
ただし、「何をどこまで書けばいいのか」「どこに独自性を出せばいいのか」といったポイントが曖昧なまま書き始めると、時間ばかりかかって失敗しやすいのも事実。だからこそ、補助金申請に慣れた専門家に一度チェックしてもらうだけでも、通過率は格段に上がります。
特に、「自分の事業のどこが強みか」「どう表現すれば伝わるか」といった整理は、第三者の視点が入ると非常に有効です。
【実例】
ラーメン店を営む30代男性
→ 「他店との差別化を図りたい」「仕入れコストも抑えたい」と考え、自家製麺への切り替えを検討
→ 小規模事業者持続化補助金を活用し、小型製麺機とミキサー、作業台など必要な機材を導入
→ 麺の太さや食感を調整できるようになり、メニューにオリジナリティが生まれる
→ 店頭やSNSで「自家製麺はじめました」と打ち出したところ、常連が増え、新規客の来店もアップ
→ 仕入れコストも月3万円ほど削減でき、利益率の改善にもつながった
3.専門家が教える資金調達のコツ
3-1.自己資金を用意しましょう
自己資金は多ければ多いほど資金調達の成功率は上昇します。
事業に必要な資金の1/3を目標に自己資金を用意しておきましょう。
1/3の資金の準備が難しい場合は、株や保険を解約して資金を集めたり、
事業に必要な資金を抑えてスモールスタートをすることによって自己資金割合を高めることを検討しましょう。
3-2.易度の低い順から検討しましょう
1章では、様々な資金調達の方法を紹介しました。
それぞれメリット・デメリットがありますが、基本的には難易度の低い順から挑戦をしてみてください。
迷った時は、目的や資金が調達できるまでの時間を確認し検討してみてください。
3-3.しっかりとした事業計画書を作成しましょう
融資を受けるにも、補助金を獲得するにもためには審査を通過する必要があります。
審査を通過するためには、売上や事業計画の実現性の高い事業計画書を作成する必要があります。
まずは、日本政策金融公庫の創業計画書のフォーマットを活用して作成してみてください。
3-4.賢く組み合わせて活用しましょう
①起業時は自己資金と融資の組み合わせで
自己資金だけで事業ができることに越したことはありませんが、少しでも資金に不安がある場合は、起業時に金融機関からの融資を受けておくことをお勧めします。
起業時は、まだ売上などの実績がないため、計画だけで融資を申しこむことができるからです。
仮に、自己資金だけで事業をスタートし予定よりも売上が伸びず、資金繰りが厳しくなってきた頃に、融資を申込しても、赤字という実績ができてしまっている為、融資を受けることは困難になります。
②融資を受けて手元資金に余裕ができたら補助金に挑戦
融資を受けて手元資金に余裕ができたら、新たな事業や新たな投資のために補助金に挑戦してみましょう。
補助金は基本的に後払いになりますので、手元資金から先に支払いが必要になります。
融資を受け手元に余裕があるときに挑戦してみましょう。
もちろん補助金は審査がありますので、必ずもらえるものではありませんが、
資金が後から戻ってくる可能性があると考えると新たな事業や投資に挑戦しやすくなります。
3-5.専門家を活用しましょう
どの資金調達方法も、審査や自身の事業内容の魅力を伝える必要があります。
そのための事業計画書の作成や手続きは、実際に事業をしながらではとても大変です。
また融資については、一度申込をして失敗してしまうと約半年間は再申し込みが難しいとされています。
効率的に資金調達をするためにも専門家の活用をお勧めします。
資金調達や事業計画作成の支援をしている専門家としては、「認定支援機関」という機関があります。
認定支援機関とは、専門的知識、実務経験がある金融機関や税理士などが、中小企業経営力強化支援法に基づき国から認定を受けている機関です。
中小企業の経営に関する悩みや相談にのり、現状の課題や改善のアドバイス、事業計画の作成、資金調達の支援などを行い、経営力強化を行うことを目的としています。
中小企業は認定支援機関において経営相談などのサポートが受けられます。
4.まとめ
今回は資金調達の方法を紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか?
まとめると以下のようになります。
2.中小企業や個人事業主は
●「日本政策金融公庫の融資」
●「保証協会付き融資」
●「補助金」から検討してみてください。
3.資金調達のコツを抑えて効率よく資金調達しましょう。
資金調達の方法はたくさんありますが、実際に活用できるものは限られています。
正しく理解し、効率よく資金調達をして事業をスタートしていきましょう。

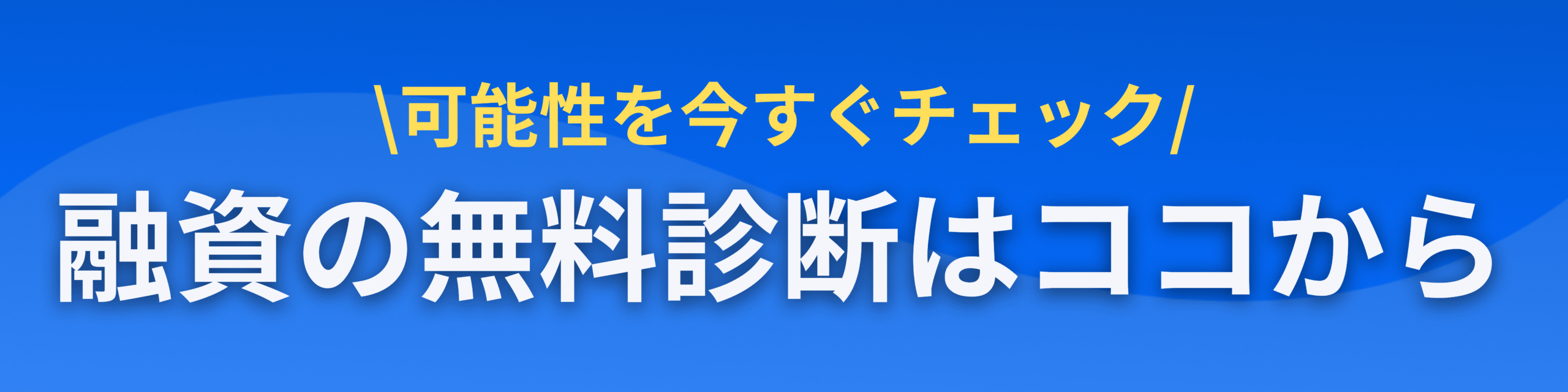

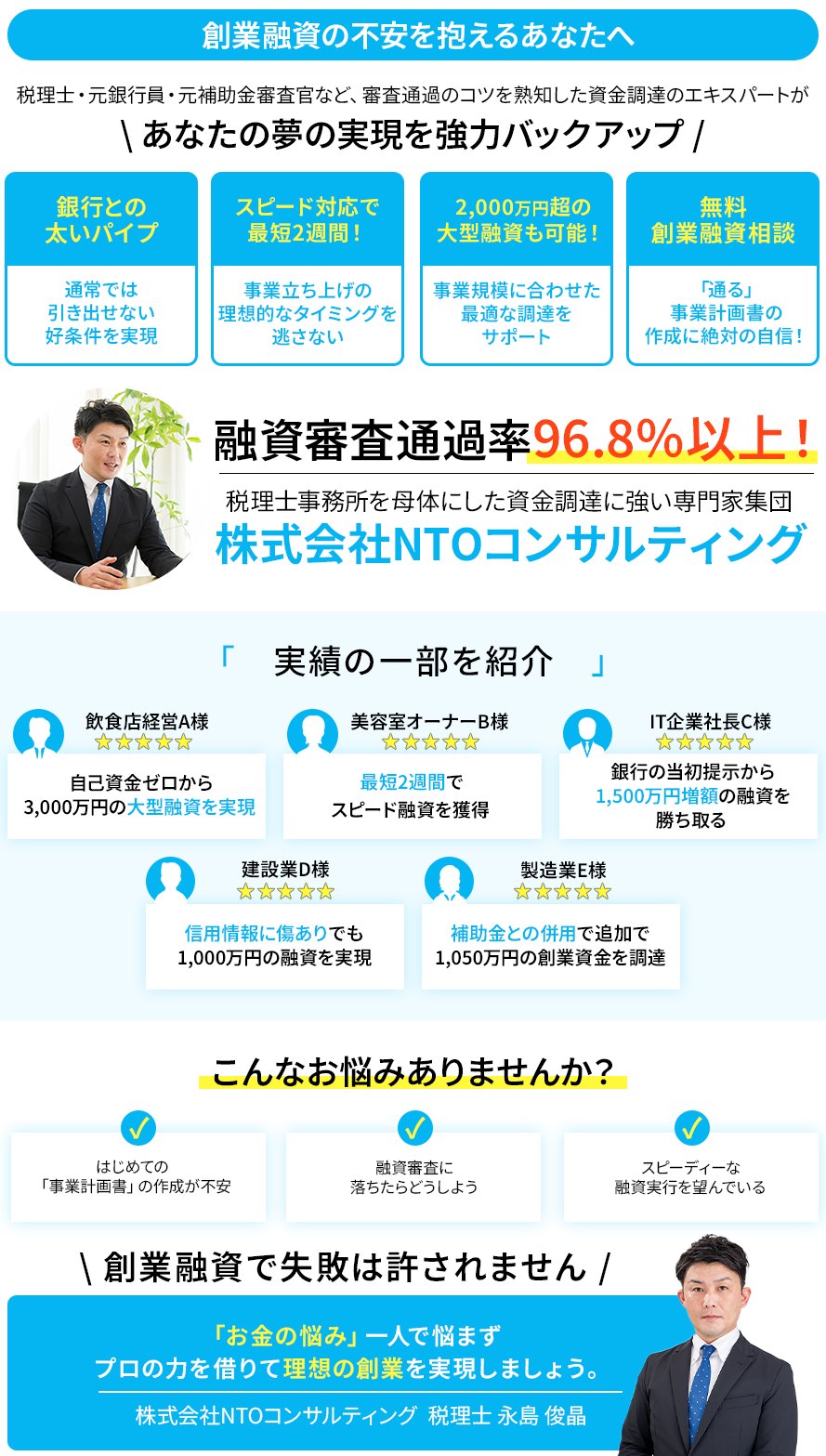
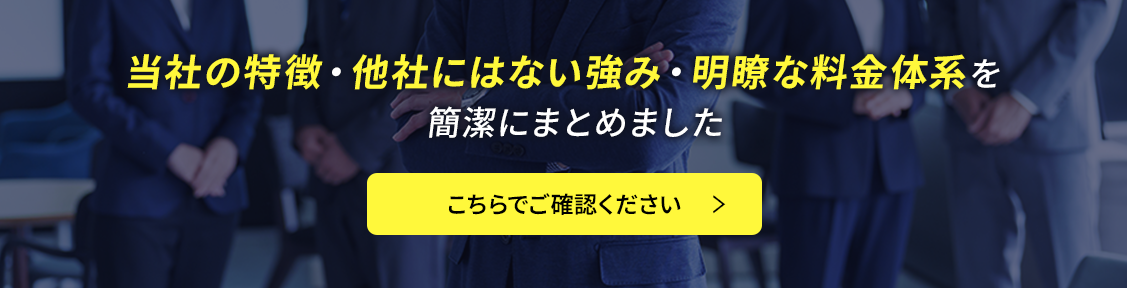
コメント