
「融資の審査結果が減額回答だった。なぜ?」その疑問にお答えします。
融資の審査結果は、0か100ではありません。
中には、減額回答といったケースも存在し、これは決して珍しいものではありません。
融資の審査において、全額否決のケースでは、決定的な原因が存在していることが多いです。
しかし、減額回答の場合、その理由がわかりにくいケースが多いのです。
具体的な原因を特定するためには、金融機関からのフィードバックが重要ですが、ほとんどの金融機関はその理由を教えてくれることはありません。
そこで今回は、なぜ全額否決でも全額回答でもなく減額回答となったのか、その理由について考えられる原因を漏れなく解説します。
この記事を読んで、思い当たる原因を見つけてみてください。
2章では、減額回答となってしまった場合の対処法として次に取るべき行動についても解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
1.融資が減額回答となってしまう10の理由
融資が減額回答となってしまった時に考えられる理由は次の通りです。
減額となる理由の大前提として、この事業なら、最低限これだけ資金があれば事業をスタートさせられることが出来ると判断されているということを覚えておいてください。
つまり、希望額が大きすぎたということになります。
複数の理由が要因で減額回答となってしまうケースも多いため、1つに絞らず、複数の理由に該当する可能性を加味して、ご自身の状況に当てはめてみてください。
【融資が減額回答となってしまう10の理由】
1-1.設備投資が大きすぎる
1-2.運転資金の確保期間が長い
1-3.事業計画書がいい加減
1-4.融資希望額に対して自己資金が少ない
1-5.融資枠をオーバーしてしまう
1-6.複数の会社を経営している
1-7.取引先が一社に依存している
1-8.前回融資を受けてからまだ日が浅い
1-9.決算を2期終えていない
1-10.FC(フランチャイズ)事業である
それぞれ詳しく解説していきます。
1-1.設備投資が大きすぎる
事業規模や同業種と比べ、設備投資が大きすぎると減額される可能性があります。
金融機関は、様々な情報を持ち合わせており、設備投資額の相場を知っているためです。
| 専門家からのアドバイス |
| グレードの高すぎる機械や車両、内装工事などにお金をかけすぎていませんか? 事業が始められなければ、元も子もありません。 必要最低限の投資規模に見直すようにしましょう。 |
1-2.運転資金の確保期間が長い
運転資金の確保期間が長いと減額されます。
売上が確保できるか心配だからと、運転資金を6カ月や1年分、融資で確保しようとしていませんか?
業種や事業内容によっても異なりますが、売上高の3カ月分が目安です。
それ以上長い期間分は減額されてしまいます。
| 専門家からのアドバイス |
| 融資の審査担当者は、業種ごとに必要な運転資金の一般的な目安を知っています。 無駄に長い期間の運転資金を借りようとすると、「軌道に乗るまで時間がかかる」つまり、事業に対して売上が確保できる自信がないというマイナスのアピールをしていることになってしまうため注意が必要です。 |
1-3.事業計画書がいい加減
事業計画書が、いい加減だと減額されてしまいます。
いい加減に作成すれば、必ずボロがでます。
また、事業計画書は、良く見せようと思えば、いくらでも良く見せられるものです。
しかし、金融のプロから見れば、とんでもない事業計画となっているケースも多いのです。
売上一つにしても、「なぜこの売上があげられるのか?」という根拠の説明が求められます。
少し大げさですが、スタッフ一人で切り盛りしている飲食店に、1日、数百人ものお客様を入れて運営することは不可能ですよね。
お店の規模やスタッフの人数等も加味した上で整合性の取れる事業計画を作成できなければ、融資は減額となってしまいます。
| 専門家からのアドバイス |
| 融資の審査を有利にする事業計画書の書き方にはコツがあります。 この事業計画書のでき次第で、大きく希望額に近づけることが可能です! ご自身での作成が難しい場合は、専門家に相談がおすすめです。 |
1-4.融資希望額に対して自己資金が少ない
融資希望額に対して自己資金が少ないと減額されてしまいます。
もし、想定より売上が上がらなかった場合は、自己資金から返済をしなければならないからです。
融資額が大きければ、その分返済額も大きくなります。
自己資金が少なければ、その返済が難しく、金融機関からすれば返済されないリスクが高くなるため融資額の減額と言った判断になります。
| 専門家からのアドバイス |
| 預金だけでなく、退職金や保険の解約返戻金、株式や投資信託なども現金化することで自己資金とすることができます。 何を自己資金とすることができるかを見極め、自己資金割合を何割以上にするか判断が必要になります。 一般的には、3割以上自己資金があれば問題ないです。 可能な限り自己資金を増やすか、それが難しければ借入金額を減らす対策をしましょう。 |
1-5.融資枠をオーバーしてしまう
既に融資を受けており、新たな借入によってその融資枠を超えてしまう場合、融資枠内に合わせて減額となることがあります。
例えば、元々の融資枠が2,000万円、既に1,500万円借り入れてる状態で、追加で1,000万円の融資を申し込んだ場合、融資枠が2,000万円ですので、500万円に減額されるということになります。
| 専門家からのアドバイス |
経営力向上計画の認定を受けることで、融資枠を拡大させることが出来ます。 所定の計画書を作成し、国の認定を受けた事業者は、税金や金融の支援を受けることができるものです。 経営力向上計画について詳しくはこちら |
1-6.複数の会社を経営している
複数の会社を経営しており、既に一つの会社で融資を受けている場合、別の会社で融資の申込をしても減額される可能性があります。
複数の会社を経営している場合でも、代表が同一の場合、融資の枠は一つなのです。
前述した融資枠の考え方と同様で、例えば、元々の融資枠が2,000万円のところ、既に法人Aで1,500万円を借り入れている状態で、法人Bで1,000万円の融資を申し込んだ場合、法人Bでは500万円までしか融資を受けられないということになります。
これは、新たな法人を通して、本来融資が受けられない会社にお金を回す「迂回融資」を避けるためです。
これから成長が期待できる法人に融資をしたのに、実際は業績の悪い法人に融資金が流れてしまっていた、仕舞いには、2社とも返済不能に陥ってしまった!なんてことになっては金融機関は困るからなのです。
複数の会社を経営している場合、このような理由で減額されている可能性があります。
| 専門家からのアドバイス |
| 自分だけでなく、親族が同じ銀行と取引がある場合も同様です。 全く異なる事業を配偶者が営んでいる場合でも、融資の結果に影響を及ぼす可能性があります。 |
1-7.取引先が一社に依存している
取引先が一社に依存している場合、融資が減額される可能性があります。
特に、建設業や運送業、製造業などで多くみられるケースです。
その一社の取引先が大企業であるなど事業基盤がしっかりしていれば問題ありませんが、事業基盤が脆弱である場合、その取引先に万が一のことがあれば、共倒れしてしまうリスクが高いため、融資の減額に繋がります。
| 専門家からのアドバイス |
| 一社に依存しない、新たな販売ルートの開拓の戦略を立てるようにしましょう。 売上の一社依存は厳しく見られてしまいます。 具体的には、集客用ホームページの作成、新規営業先リストの作成など、販路開拓への取組を実行しているアピールをすると良いでしょう。 |
1-8.前回融資を受けてからまだ日が浅い
前回の融資から日が浅いと融資の減額、または融資を断られる可能性が高くなります。
融資が受けられる金額は、既存の融資を返済した分が目安となります。
具体的に、何か月以上空けなければならないといった決まりはありませんが、一つの目安として既存の借り入れの3分の1から2分の1以上返済を終えている状態が望ましいとされています。
| 専門家からのアドバイス |
| ただし、直近で大きな売上に繋がる取引が決まったなど、前向きな事情がある場合は、その点を考慮してもらえる可能性があります。 実際の契約書などを用意し、金融機関の担当者に相談するようにしましょう。 |
1-9.決算を2期終えていない
決算を2期終えていないと、融資の減額、または融資が断られる可能性があります。
融資の審査をする上で、過去の実績と現在の実績を比べて、状況が改善しているかどうかを分析しています。
決算が1期しかない場合は、数値の良し悪しを判断することができないため、多くの金融機関は決算が2~3期終わるまで様子を見る事が多くなります。
| 専門家からのアドバイス |
| 決算を終えていなくとも、直近分までの試算表を提出したり、今後の事業の具体的な数値計画を示すことで、満額の融資を獲得できる可能性があります。 決算を2期終えていないからとあきらめるのでなく、可能な限りの準備を整えて融資審査に挑むようにしましょう。 |
1-10.FC(フランチャイズ)事業である
全くの未経験者がフランチャイズに加盟して事業を開始しようとしていたり、フランチャイズ本部の業績が悪い場合、融資の減額または融資を断られることがあります。
| 専門家からのアドバイス |
| フランチャイズ本部から提示される損益シミュレーションを鵜呑みにするのではなく、ご自身の経験やスキル等を踏まえた独自の事業計画を立て、事業の実現性をアピールしましょう。 |
複数の理由が要因で、減額となっているケースも多いため、あらゆる可能性を考慮してみてください。

2.減額回答を受けた時に、次に検討すべき3つの選択肢
もし、融資が減額回答となってしまったとしても、そこであきらめるのはまだ早いです。
次に検討すべき行動の選択肢は、次の3つが考えられます。
減額回答となってしまった理由に応じて次の行動を検討していきましょう。
2-1.他の金融機関で追加融資にチャレンジ
2-2.資金計画を見直してスモールスタートをする
2-3.経営力向上計画の認定を受け、融資枠を拡大する
それぞれの選択肢について解説します。
2-1.他の金融機関で追加融資にチャレンジ
融資が減額回答となってしまったら、 別の金融機関で追加融資の申込をしましょう。
ただし、必ず日本政策金融公庫で減額回答だった場合は、銀行や信金などの民間の金融機関へ、銀行や信金などの民間の金融機関で減額回答だった場合は、日本政策金融公庫へ行くようにしましょう。
銀行や信金など民間の金融機関の場合、基本的に、金融機関内での審査の他、信用保証協会が審査をします。
そのため、A銀行で減額回答だったからとB銀行へ行ったとしても、ただ窓口が変わっただけで、信用保証協会が審査することに変わりなく、意味がないのです。
また、追加融資の申込を進める前に、減額されてしまった原因を究明し、改善するようにしましょう。
原因が自分ではわからない、どのように改善したらよいかわからない場合は、専門家に相談がおすすめです。
2-2.資金計画を見直してスモールスタートをする
減額となる理由の前提は、希望額が大きすぎというところにあります。
融資のプロから見て、この事業内容なら、最低限これだけ資金があれば、事業をスタートできると判断されているのですから、その指摘を信用して事業を小さくスタートするのも一つの選択肢と言えます。
具体的には、機械や設備のグレードを下げたり、中古を検討する、内装工事を簡易的なものにするなどの方法が考えられます。
無理にたくさん借りて、返済負担が大きくなってしまうより、小さくスタートして、事業が安定してから追加融資にチャレンジするなど、少しずつ規模を拡大していくという方法も検討しましょう。
2-3.経営力向上計画の認定を受け、融資枠を拡大する
融資の減額理由が、融資の枠に関係している場合、経営力向上計画の認定を受けることで、融資の枠を拡大することが出来ます。
経営力向上計画とは、人材の育成や、コスト管理等のマネジメントの向上、設備投資など、自社の経営力を向上する計画のことで、所定の計画書を作成し、国の認定を受けた事業者は、税金や金融の支援を受けられる制度です。
この金融支援の中の一つに、銀行や信金等、民間の金融機関の融資枠を拡大できる支援制度があります。
その他にも日本政策金融公庫で低金利融資を受けることができたり、税制の優遇、補助金の審査で有利になるなど、大変魅力的な優遇措置を受けることができます。
今後事業を拡大していきたいと考える経営者にとって、欠かせない制度ですので、これを機会に申請を検討してみてください。
ただし、計画書を作成し、審査を受ける必要があります。
また、申請から認定まで30日ほど時間がかかるなどの注意点があります。
3.まとめ
融資の審査結果が減額回答となるのは、次の10の理由が考えられます。
1-1.設備投資が大きすぎる
1-2.運転資金の確保期間が長い
1-3.事業計画書がいい加減
1-4.融資希望額に対して自己資金が少ない
1-5.融資枠をオーバーしてしまう
1-6.複数の会社を経営している
1-7.取引先が一社に依存している
1-8.前回融資を受けてからまだ日が浅い
1-9.決算を2期終えていない
1-10.FC(フランチャイズ)事業である
ただし、複数の理由が要因で減額回答となってしまうケースも多く、複数の理由に該当する可能性を加味して、ご自身に当てはめてみてください。
減額回答を受けた場合は、その理由をしっかりと理解し、次のステップを検討することが重要です。
他の金融機関での追加融資、資金計画の見直し、経営力向上計画の認定など、さまざまな選択肢があります。
これらを駆使して、事業のスムーズなスタートと持続的な成長を目指しましょう。
どの選択肢を選ぶにしても、融資の専門家のサポートを受けることで、より確実に次のステップを踏むことができます。
この記事を参考に、自社の状況に合った最適な行動を選び、成功に向けて進んでください。

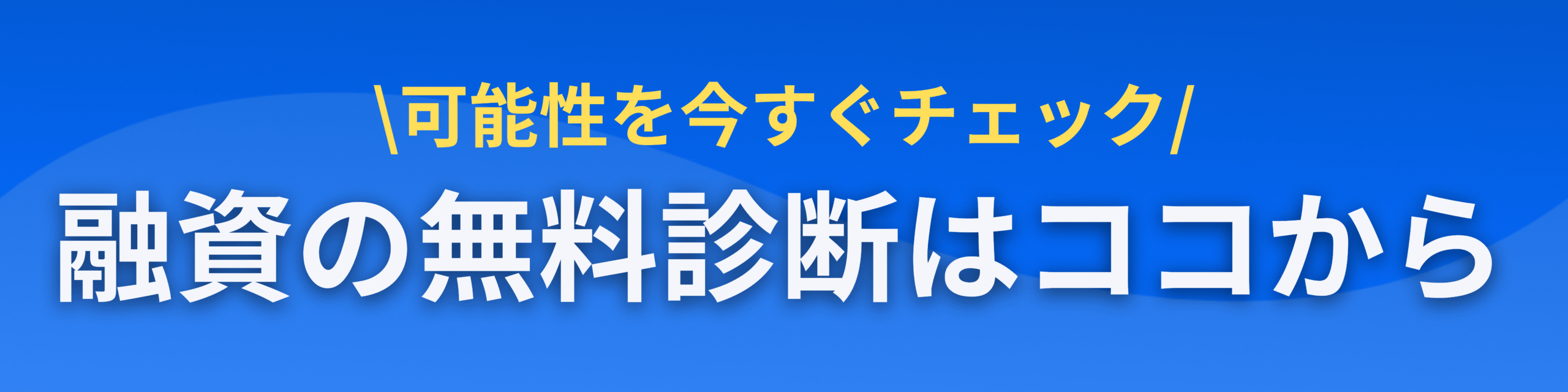

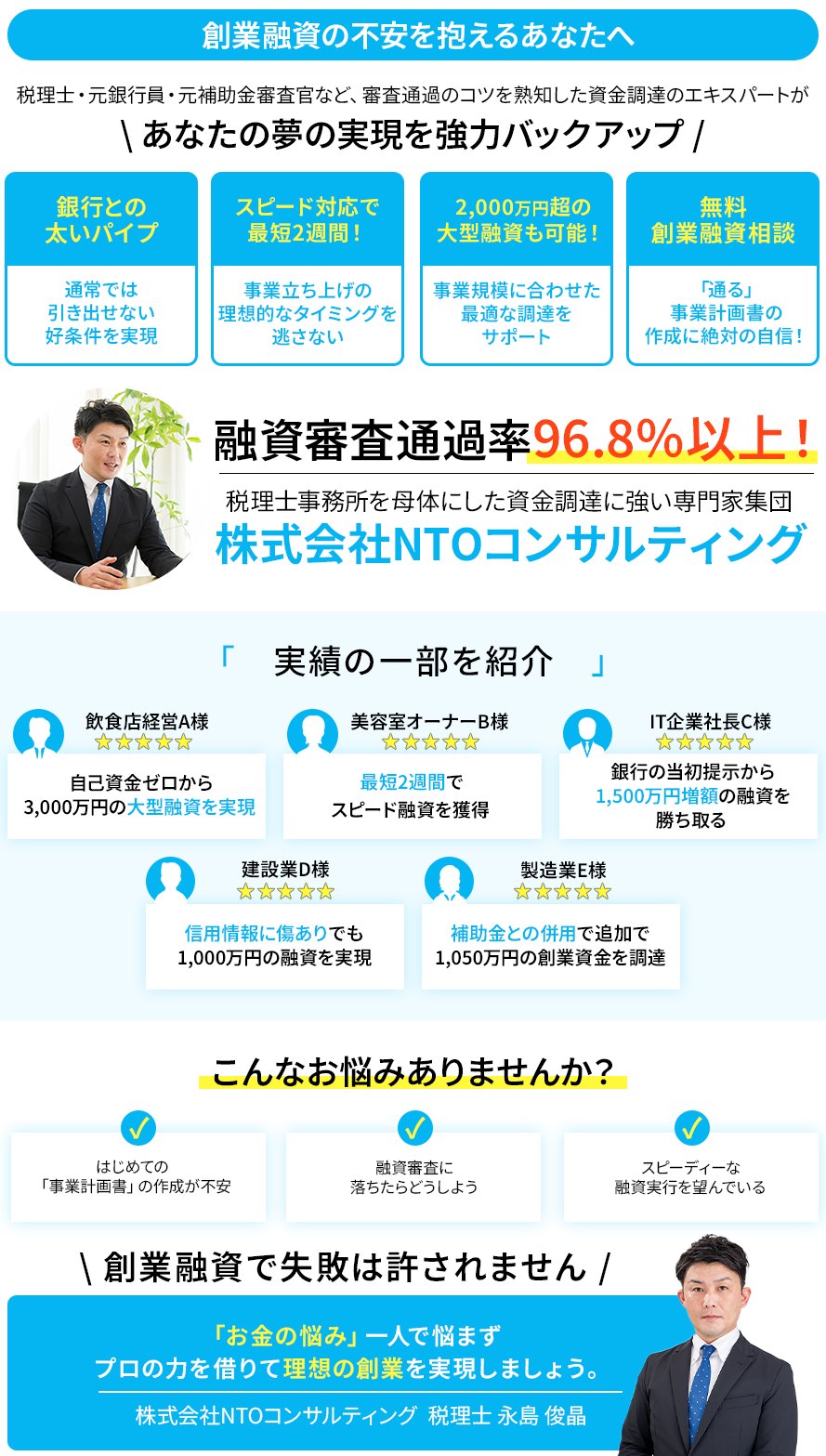
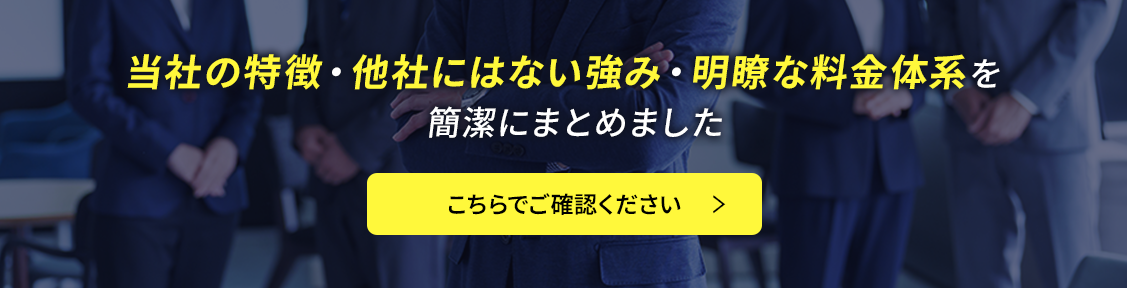
コメント