
「合同会社だと、融資は難しいって本当?」
そんな不安をお持ちではありませんか?
実際、インターネット上では「合同会社は信用力が低いから融資が通らない」といった声も散見されます。
しかし、これは誤解です。
合同会社であっても、金融機関から融資を受けることは可能です。
審査では、会社の“形態”ではなく、“中身”──つまり、事業の実現性や代表者の経験、自己資金などが重視されます。
本記事では、「合同会社でも十分に融資を受けられる」という事実を前提に、合同会社におすすめの資金調達方法と成功率を高める3つの戦略を具体的に紹介していきます。
目次
1. 合同会社だから融資が不利?そんな心配はもう不要!
結論:合同会社でも融資は十分に受けられます。会社形態は審査に影響しません。
金融機関が融資の審査をする際、合同会社か株式会社かという「法人の種類」だけを見て判断することはありません。
確かに、合同会社は知名度が低いと言った点から、信用力が低いと言われることはありますが、融資に関しては、合同会社と株式会社とで審査に有利・不利と言ったことはありません。
むしろ、次のようなポイントが重視されます。
・代表者の過去の経験や業績
・自己資金の有無
・売上見込みや収支計画が明確な事業計画書
・面談での受け答え
つまり、“合同会社だから”という理由で融資を断られることは基本的にありません。
株式会社でも、上記のポイントが抑えられていなければ当然、融資を受けることは難しいでしょう。
※補足※ 合同会社は「出資」には制限があることに注意
ひとつ補足をしておくと、合同会社は株式を発行できないため株式が関係する、ベンチャーキャピタルなどの出資を受けることができません。
資金調達の選択肢が株式会社に比べて少ないという点は、理解をしておきましょう。
このため、外部から大規模な出資を受けたい場合や、将来的に上場を目指す場合は、株式会社を設立する、株式会社への会社形態の変更も選択肢の一つとして検討しておくとよいでしょう。
2. 合同会社が使えるおすすめ資金調達方法3選
合同会社でも利用できる現実的な資金調達手段は豊富にあります。融資だけでなく、返済不要の補助金・助成金まで視野に入れることで、必要な資金を柔軟に確保できます。
2-1. 日本政策金融公庫|創業時の強い味方
日本政策金融公庫(通称:公庫)は、政府が100%出資する金融機関で、これから創業する方や創業間もない中小企業・小規模事業者への融資を積極的に行っています。
特に注目したいのが「新規開業資金」という制度です。一般的に創業融資とも言われています。
これは、創業前または創業後間もない事業者向けに用意された制度で、以下のような特徴があります。
✅ 日本政策金融公庫「新規開業資金(創業融資)」の主な特徴
| 項目 | 内容 |
| 融資元 | 日本政策金融公庫 |
| 対象者 | 創業前または創業後おおむね2期以内(税務申告2回未満)の事業者 |
| 融資限度額 | 制度上の融資限度額は7,200万円(うち運転資金は4,800万円) ※実際の融資額は1,000万円未満となるケースが多い |
| 金利 | 2.5%前後 |
| 返済期間 | 設備資金:最大20年(うち据置期間5年以内) 運転資金:最大10年(うち据置期間5年以内) |
| 担保・保証人 | 原則不要 |
| 申込から融資実行までの期間 | スムーズにいけば1ヶ月以内 |
| ポイント|創業期の資金調達は「日本政策金融公庫」が第一選択 |
創業期の最大の課題は「営業実績がないことによる資金調達の難しさ」です。 日本政策金融公庫の創業融資について詳しくはこちら |
2-2. 保証協会付き融資&制度融資の活用術
「銀行融資はハードルが高い」
そう感じる創業者や、まだ実績の浅い合同会社経営者にとって、最初の資金調達先として検討すべきが「信用保証協会付き融資」と、そこに自治体の支援が加わる「制度融資」です。
両者は、信用保証協会が“公的な保証人”として融資を後押しする仕組みであり、創業期の金融機関との取引において強力なサポートとなります。
✅ そもそも「保証協会付き融資」とは?
保証協会付き融資とは、信用保証協会が“公的な保証人”となって、金融機関からの融資を受けやすくする制度です。
創業したばかりの企業は、営業実績が乏しく、金融機関から見ると「返済能力が未知数」と判断されやすいため、銀行からの直接融資(=プロパー融資)を受けるのは非常に難しいのが現実です。
そこで、信用保証協会が間に入って保証を引き受けることで、金融機関にとっての貸倒リスクを軽減し、創業者でも融資を受けやすくする――これが「保証協会付き融資」の大きな役割です。
💡注意:信用保証協会が代わりに返済してくれた場合でも、それで返済義務が消えるわけではありません。借り手(事業者)は、その後、信用保証協会に対して弁済額を返済していく必要があります。
✅ さらに支援が手厚い「制度融資」とは?
保証協会付き融資に、地方自治体による支援(利子補給・保証料補助など)が加わったものが、「制度融資」と呼ばれます。
これは自治体・金融機関・信用保証協会の三者が連携して運用する地域密着型の融資制度であり、創業支援に特化した枠などの優遇制度も設けられています。
✅ 保証協会付き融資の主な特徴
| 項目 | 内容 |
| 融資元 | 銀行や信用金庫などの民間の金融機関 |
| 保証人 | 各都道府県の「信用保証協会」 |
| 保証の役割 | 返済ができなくなった場合、保証協会が立て替え(代位弁済)する。 ただし、その後、借主は保証協会に対して返済義務を負う |
| 融資限度額 | 制度上の融資限度額は無担保:8,000万円/有担保:2億8,000万円 ※実際は、制度や企業による |
| 金利 | 1.5%前後(制度融資の活用で補助が受けられることもあり。) |
| 保証料 | 1.5%前後(制度融資の活用で補助が受けられることもあり。) |
| 返済期間 | 5~10年 |
| 申込から融資実行までの期間 | 1ヶ月半~2ヶ月 |
| ポイント|制度融資は“地域差”と“相談先選び”がカギ |
✅ 制度融資は地域で内容が異なる ✅ 相談先は「信用金庫」がおすすめ 保証協会付き融資について詳しくはこちら 制度融資について詳しくはこちら |
2-4. 補助金・助成金|返済不要の“もらえる支援”を活用しよう
融資と違い、補助金や助成金は返済の必要がない資金支援制度です。
条件を満たせば国や自治体から受け取ることができ、創業初期の資金負担を軽減する強力な手段になります。
ただし、補助金と助成金には明確な違いがあるため、それぞれの特徴を理解したうえで、目的や状況に応じて活用することが重要です。
✅ 補助金とは?
補助金は、国や自治体が一定の事業活動に対して支給する審査型・競争型の支援金です。
申請すれば必ずもらえるわけではなく、審査を通過し「採択」される必要があります。
【代表的な補助金の例】
| 補助金名 | 目的 | 対象となる経費の例 | 補助額・補助率 |
| 小規模事業者持続化補助金 | 販路開拓や業務効率化などの取組を支援 | 機械装置費・広報費・WEBサイト関連費・展示会等出展費・旅費・新商品開発費・借料・委託、外注費 | 50万円~250万円 補助率2/3 |
| ものづくり補助金 | 新的な製品開発や設備投資を通じて、生産性向上や事業革新を図る取組を支援 | 機械装置、システム開発費・運搬費・技術導入費・外注費・専門家経費・知的財産権等関連経費・クラウドサービス利用費・原材料費・海外旅費・通訳翻訳費・広告宣伝、販売促進費 | 750万円~3,000万円 補助率1/2~2/3 ※従業員数や利用する枠による |
| IT導入補助金 | ITツールの導入により、業務効率化や売上向上を支援 | 在庫管理システム・決済ソフト・会計ソフト・受発注ソフト・PC、ハードウェア・ネットワーク監視システム等 | 5万~450万円 補助率1/2~2/3 ※従業員数や利用する枠による |
| 自治体独自の補助金 | 創業・事業承継・空き家対策など | 制度により異なる | 制度により異なる |
| ポイント|補助金は「後払い」&「期間限定」、情報収集がカギ! |
| 補助金は、原則として「後払い」制度です。 採択されたあと、いったん自費で事業を実施し、完了後に実績報告を行ってはじめて補助金が支給されます。つまり、自己資金の準備が前提となる資金調達方法です。 また、補助金はいつでも申請できるわけではなく、公募期間が年に数回と限られているため、タイミングを逃さないよう注意が必要です。 また、補助金は通年でいつでも申し込めるわけではありません。 |
✅ 助成金とは?
助成金は、主に雇用や労務に関する取り組みに対して条件を満たせば原則受け取れる支援金です。
補助金と異なり、決められた予算の枠を競争する審査ではなく「要件に該当しており、必要な申請を申請をすれば」ことが基本です。
【代表的な助成金の例】
| 助成金名 | 対象となる取組 | 支給額(例) |
| キャリアアップ助成金 | 正社員化、処遇改善の取組 | コースによる |
| 両立支援助成金 | 育児・介護と仕事の両立支援制度の導入 | コースによる |
| ポイント|補助金と助成金、それぞれの使い方を知っておこう |
補助金は“競争型”のため、しっかりとした事業計画書の作成が必要です。 ✅ どこに相談すればいい? |

3. 合同会社の融資成功率を高める!先手必勝の3つの戦略
融資の審査は、会社の形態によって左右されるものではありません。
初めに解説したように、下記のようなポイントが重視されます。
・代表者の過去の経験や業績
・自己資金の有無
・売上見込みや収支計画が明確な事業計画書
・面談での受け答え
ここでは、合同会社の融資成功率を高める、3つの戦略を解説していきます。
3-1.事前準備:自己資金と経験の証明がカギ
融資審査では、まず「自己資金の額」と「これまでの準備・経験」が見られます。
自己資金は、開業資金の3分の1以上が目安とされ、資金をどう積み上げてきたかも評価対象です。
また、これまでの職歴や業界での経験なども問われます。
✅準備すべきこと
・自己資金は、通帳に毎月積み立てた履歴を残す(突発的な入金はNG)
・事業での経験を積む(長ければ長いほど有利)
| 専門家からのアドバイス |
| 創業融資では、自己資金=本気度として評価されます。 コツコツと準備してきた形跡を通帳の履歴などでみせることで、プラスの評価に繋がります。 |
3-2. 事業計画書の精度が融資の可否を左右する
事業計画書は、融資審査の最重要書類です。
特に合同会社では「簡単に作れた会社」に見られないように、しっかりとした数字とストーリーを含めた事業計画書が必要です。
✅作成時のポイント
・売上・経費・利益は根拠を明記(例:集客方法、仕入先、原価)
・ターゲット・競合・差別化ポイントを明示する
・なぜこの事業をやるのか(起業理由)も簡潔に伝える
| 専門家からのアドバイス |
「この人はちゃんと考えている」と思わせる構成が重要です。 数字だけでなく、「どのようにして顧客を獲得し、売上をつくるか」が伝わる事業計画を作成しましょう。 創業計画書の書き方について詳しくはこちらで解説しています。 ▶日本政策金融公庫の創業計画書の書き方11ステップ!審査を通すためのテクニックを完全公開! |
3-3.面談対策:信頼される人柄と誠実な説明を
金融機関の面談では、書類には表れない経営者の“姿勢”が見られます。
どんなに計画書がよくできていても、説明が不十分だったり、答えに詰まってしまったりすると、「この人で大丈夫か?」と不安を抱かれてしまいます。
✅面談時に心がけること
・計画の内容は自分の言葉で説明できるようにしておく
・質問には簡潔・正直に答える
・リスクへの備え(最悪のシナリオに対する対応策)も用意しておく
・専門用語は避ける
| 専門家からのアドバイス |
| 面談は「説得」ではなく、「信頼してもらう場」です。 例え、痛いところを突かれても、嘘をつかず、弱点も認めたうえで「こう対処します」と言える人の方が、信頼されやすくなります。 融資の面談対策について詳しくはこちらで解説しています。 |
不安なときは、専門家のサポートを活用!
これらの準備をしっかり行えば、合同会社でも十分に融資は受けられます。
ただ、初めての融資で「本当にこれで大丈夫?」と感じる方も多いはずです。
そんなときは、創業融資に詳しい専門家に相談するのも一つの手。
事業計画書のチェックや面談対策など、融資成功率を高めるサポートを受けることができます。
創業支援や融資支援に強い税理士などへの相談がおすすめです。
4.まとめ|合同会社でも融資は十分可能。まずは「準備」から
「合同会社は融資に不利」というのは誤解です。
審査で重視されるのは、会社の“形態”ではなく、“中身”──つまり、代表者の経験、自己資金、事業計画の実現性、そして面談での対応力です。
本記事では、合同会社でも活用できる代表的な資金調達方法として、以下の3つを紹介しました。
・日本政策金融公庫の創業融資:実績がなくても将来性で勝負できる公的融資
・保証協会付き融資・制度融資:創業者の強い味方になる自治体連携型の仕組み
・補助金・助成金:返済不要の資金支援で、創業時の負担を軽減
そして、融資成功のカギを握る3つの戦略として、
・自己資金と経験の準備
・根拠ある事業計画書の作成
・面談での誠実な対応
を解説しました。
次にやるべきアクションは?
✅まずは自己資金を「見える形」で準備
✅事業計画書の骨子をつくってみる
✅不安があれば、専門家に相談してみる
特に初めて融資にチャレンジする方は、税理士などの創業支援に強い専門家の力を借りることで、融資成功率は大きく高まります。
「合同会社だから…」とあきらめず、一歩を踏み出してみましょう。あなたの挑戦を応援しています。

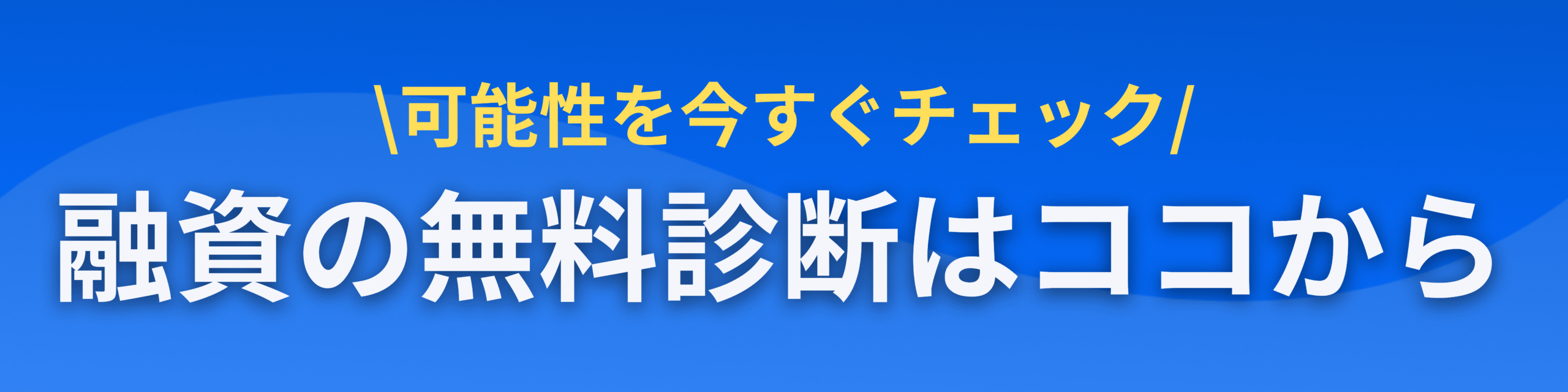

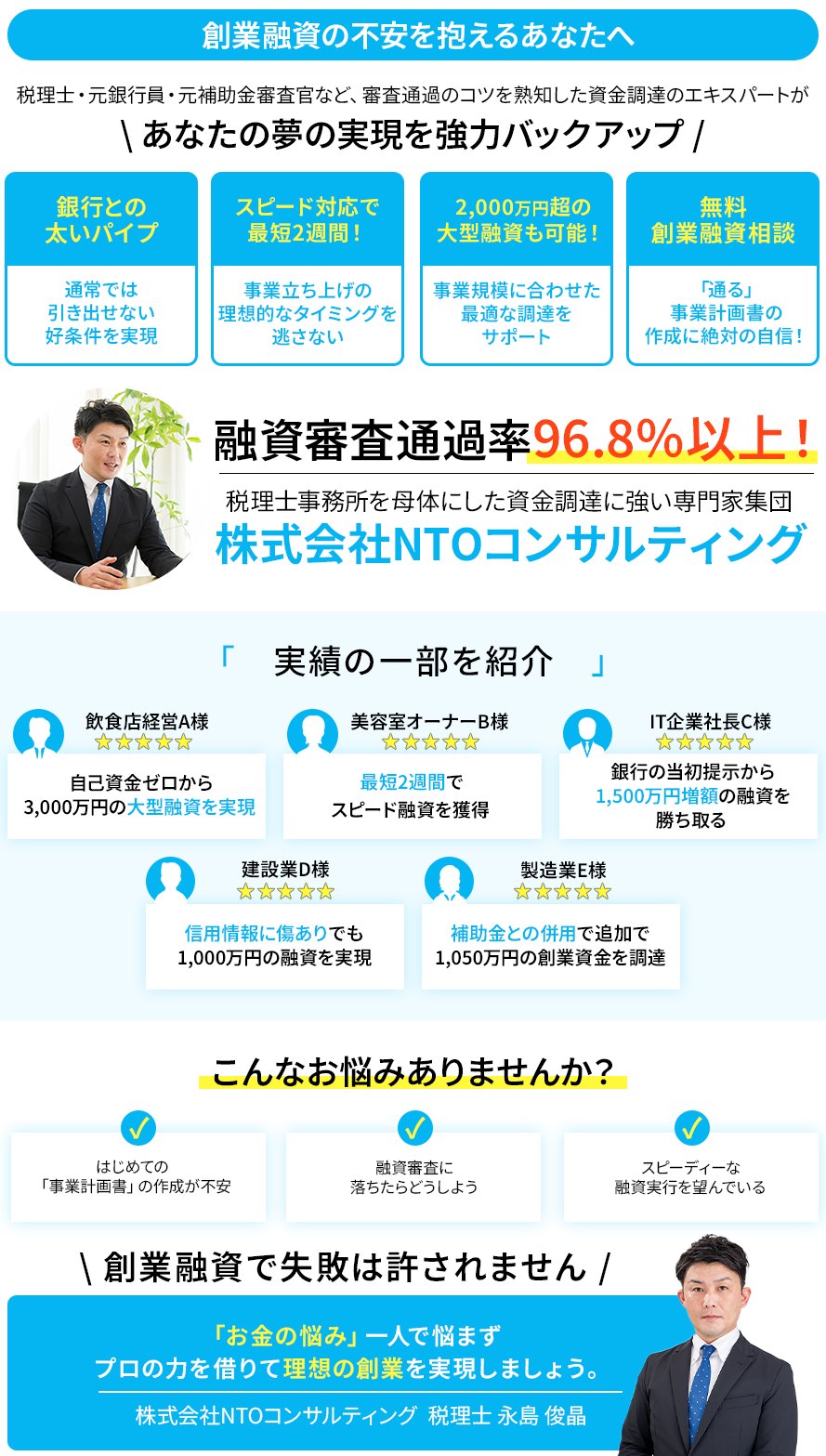
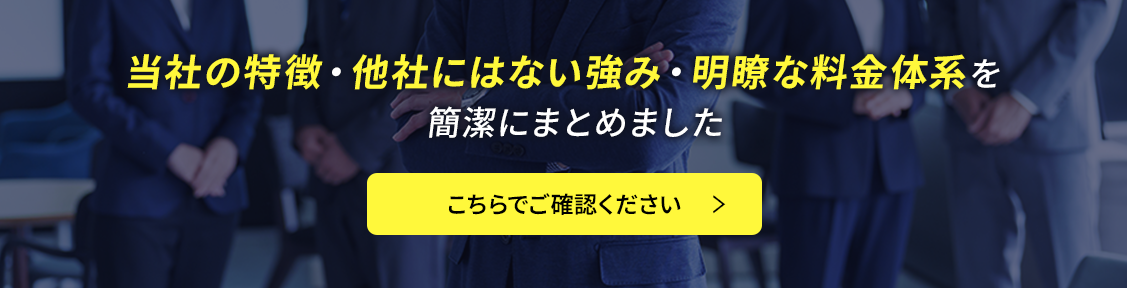
コメント