
会社設立は「専門家と一緒に進める」のが成功の近道です。
結論からお伝えすると、会社設立は、専門家と相談しながら進めるべきです。
なぜなら、設立手続きには法務・税務・労務など複雑な要素が絡み、ひとつでも抜け漏れがあると、思わぬトラブルや損失につながるリスクがあるからです。
とはいえ、
・「何から始めればいいのかわからない」
・「どの専門家に、いつ相談すればいいの?」
・「自分でやれることと、頼むべきことの区別がつかない」
―そんな不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、専門家と連携して会社設立をスムーズに進めるための具体的なスケジュールと、社長がやるべきタスク一覧を時系列でわかりやすく解説します。
この記事を読むことで…
・設立に必要な手続きの全体像が把握できる
・各ステップで何をすべきか、誰に頼むべきかが明確になる
・設立後にやるべきことまで含めて、行動の見通しが立つ
つまり、設立準備から開業後まで「今やるべきこと」が明確になり、自信をもって起業の一歩を踏み出せるようになります。
それではさっそく、会社設立のスケジュールを見ていきましょう。
目次
1. 専門家と進める!会社設立スケジュール
まずは、会社設立における全体の流れを押さえておきましょう。
下記は専門家と連携しながら進めた場合の、基本的なステップです。
✅ 会社設立スケジュール表
| ステップ | 内容 | 誰がやる? | 期間の目安 |
|---|---|---|---|
| 1 | 会社の概要を決める | 社長 | 1〜3日 |
| 2 | 各種専門家に相談 | 社長・専門家 | 1〜2日 |
| 3 | 会社印の作成 | 社長 | 2〜3日 |
| 4 | 会社設立書類の作成・登記申請 | 専門家・社長 | 1週間程度 |
| 5 | 登記完了・法人設立 | 登記申請~1週間前後 |
ステップ1:会社の概要を決める(1~3日)
➡︎ 手続きの全体像の出発点になる。
会社設立の第一歩は、「会社の基本情報」を決めることから始まります。
これは定款の作成や登記申請、銀行口座の開設、さらには融資や補助金申請にまで影響する、非常に重要なステップです。
とはいえ、この段階ですべてを完璧に決める必要はありません。
まずは下記のような項目について、自分なりのイメージを持っておくことで、後の専門家との打ち合わせが格段にスムーズになります。
| ✅ 事前に考えておきたい項目 | |
| 会社の設立形態 | 株式会社or合同会社 |
| 会社名(商号) | 株式会社〇〇/合同会社〇〇など |
| 事業目的(事業内容) | 何を、誰に、どのように提供するか |
| 本店所在地 | 自宅?事務所?レンタルオフィス? |
| 資本金額 | 自己資金をベースとした現実的な金額 |
| 役員構成 | 代表者のみ?他にも取締役を置く? |
| 事業年度 | 決算はいつ? |
| 会社設立希望日 | 土日は法務局閉庁日のため、設立登記申請 |
これらを紙やメモアプリに一度書き出してみましょう。
不明な点や迷うところがあっても大丈夫です。
そうした部分こそ、専門家に相談して判断を仰ぐポイントです。
また、建設業や飲食業などの許認可が必要な事業を始める場合は、所在地や資本金の要件が絡むこともあるため、早めに相談しておくと安心です。
ステップ2:専門家に相談する(1〜2日)
➡︎まずは税理士に相談するのが、最も効率的なスタートです。
会社を設立する際には、登記を行う司法書士、許認可の申請を担当する行政書士、設立後の税務や資金調達をサポートする税理士など、さまざまな専門家の力を借りる必要があります。
中でも、まず最初に相談するなら、会社設立全般の知識を持つ「税理士」がおすすめです。
・どの法人形態が最適か(株式会社か合同会社か)
・節税の視点での資本金や役員構成のアドバイス
・創業融資や補助金など、資金調達に関する計画
・設立後すぐに必要になる税務署への届出や経理体制の整備
さらに、税理士は他士業とのネットワークを持っていることが多く、必要に応じて司法書士や行政書士などをスムーズに紹介してもらうことも可能です。
複数の専門家を自分で探してスケジュールを調整する手間が省けるため、効率的に準備を進められます。
なお、税務手続きは設立後すぐに必要になる重要業務です。どのみち専門家の支援が必要になるので、早いうちから信頼できる税理士に相談しておくと、設立後の運営も安心です。
ステップ3:会社印の作成(2〜3日)
➡︎ 必要な印鑑を早めに準備すれば、後の手続きがスムーズに進みます。
会社名が決まったら、法人用の印鑑(いわゆる「会社印」)の作成に進みましょう。
この印鑑は、登記申請・銀行口座開設・契約書の締結など、会社運営に欠かせないアイテムです。
✅ 会社印にはどんな種類があるの?
法人の場合、通常は次の3点セットで作成することが多いです。
| 印鑑の種類 | 用途 |
| 実印 | 登記・契約書など重要書類に使用 |
| 銀行印 | 法人口座の開設、銀行手続きに使用 |
| 角印(社印) | 請求書・見積書・納品書などに使用 |
✅ 作成費用と納期の目安は?
費用:代表者印1本で3,000円〜10,000円程度
3点セットだと5,000円〜15,000円程度が相場です(材質によって価格が変わります)
納期:ネット注文であれば早ければ即日発送〜2営業日程度で届きます
早めに印鑑を作っておくと、登記書類の準備や銀行口座の開設がスムーズに進むため、会社名が決まり次第すぐに取りかかりましょう。
ステップ4:会社設立書類の作成・登記申請(1週間程度)
➡︎ 専門家に任せることで、ミスのない登記申請が実現できる
会社を正式に設立するには、法務局に登記申請を行うための書類一式を整える必要があります。
このステップは法律的な要件も多いため、司法書士などの専門家に依頼するのが一般的です。
また、このタイミングで「資本金の払い込み」も完了しておく必要があります。
| 書類名 | 内容 | 誰が作成する? |
| 定款 | 会社の基本ルール | 専門家(社長と相談しながら) |
| 設立登記申請書 | 法務局に提出する登記申請書類 | 専門家 |
| 印鑑届 | 法人実印の登録に使用 | 専門家が準備、社長が押印 |
| 資本金の払込証明書 | 資本金の入金を証明する書類 | 専門家が作成、 社長が通帳コピーを提出 |
✅ 専門家に依頼する場合の流れ
会社概要のヒアリング
会社名・所在地・資本金などを専門家とすり合わせます。定款の作成・認証
社長と相談をしながら専門家が定款を作成、認証手続きを行います。
※合同会社の場合は、定款の認証は不要。資本金の払い込み
社長が自ら資本金を入金し、通帳コピーを提出します。登記書類の作成・確認
司法書士がすべての書類を作成し、社長が確認・押印します。法務局への登記申請
司法書士が代理で申請を行い、登記完了までは約1週間です。
✅ 資本金の払い込みとは?
「資本金の払い込み」とは、登記申請前に会社の出資者(発起人)が、決めた資本金を実際に入金することをいいます。
会社設立前は法人名義の口座が存在しないため、代表者の個人口座に入金するのが一般的です。
【手順】
1.自分の個人口座を用意する(通帳のある口座がベター)
2.発起人全員が資本金を入金
3.通帳の表紙・表紙裏・入金が記載されたページのコピーを保存
4.その内容をもとに専門家が「払込証明書」を作成する
※この手続きが済んでいないと、登記が受理されません。
※登記後は速やかに法人名義の口座を開設し、資本金を移すのが一般的です。
ステップ5:登記完了・法人設立(登記申請~1週間前後)
➡︎ 登記完了で会社が誕生!ここから事業スタートの準備が本格化します。
法務局への登記申請が受理され、不備がなければ通常は申請から約1週間程度で登記が完了します。
登記が完了すると、いよいよ会社が“法的に成立”した状態となります。
しかしここからが本番です。
会社としての活動を本格的に始めるためには、法人名義の銀行口座の開設、資金調達、税務署等への各種届出、契約手続きなど、次のステップへ進む必要があります。
これらの手続きの多くで必要になるのが、以下の2つの書類です。
・履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
・法人印鑑証明書
これらの書類は、登記完了の翌時以降、法務局の窓口・または郵送で取得が可能になります。
会社の設立日ではありませんので注意してください。
💰 ここまでにかかる会社設立費用のまとめ
会社設立には、「登記に必要な法定費用」と「専門家への報酬」が発生します。
株式会社か合同会社かによって費用が大きく異なるため、比較しながら検討しましょう。
✅ 株式会社の場合
| 項目 | 費用の目安 | 備考 |
| 登録免許税 | 最低15万円 | 資本金×0.7%、最低15万円 |
| 定款認証手数料 | 3万円~5万円 | 資本金額によって異なる |
| 司法書士報酬 | 5~10万円 | 相場 |
| 合計 | 約25万円~ |
✅ 合同会社の場合
| 項目 | 費用の目安 | 備考 |
| 登録免許税 | 最低6万円 | 資本金×0.7%、最低6万円 |
| 定款認証手数料 | 不要 | |
| 司法書士報酬 | 5~10万円 | 相場 |
| 合計 | 約11万円~ |
次のステップへ|登記完了後にもやるべきことがたくさんあります
登記が完了し、会社が正式に設立されると、「これでひと安心」と思いたくなるかもしれません。
しかし、会社の設立はゴールではなくスタートです。
実際には、登記完了後にも重要な手続きや準備が数多く残っています。
たとえば、税務署への届出、社会保険の手続き、法人名義の銀行口座の開設、資金調達の準備など、やるべきことは目白押しです。
次章では、登記後すぐに必要となる「会社設立後の手続きスケジュール」について、時系列でわかりやすく解説していきます。
ここをしっかり押さえておくことで、事業をスムーズにスタートさせることができます。

2. 会社設立後の手続きスケジュール
会社設立登記が完了すると、晴れて法人が誕生します。
しかし、これで終わりではありません。
登記完了後にも、事業を始めるためにやるべき手続きが数多くあります。
以下のように、やるべきことを時系列で整理することで、スムーズに事業を立ち上げることができます。
法人を設立しただけでは、事業は始められません。この章では、設立後のタスクを時系列で整理しています。
✅ 会社設立後の手続きスケジュール表
| ステップ | 内容 | 誰がやる? | 目安時期 |
| 1 | 各種届出の提出(税務・社会保険・労働関係など) | 社長/税理士 | 設立後すぐ〜2週間以内 |
| 2 | 法人口座の開設 | 社長 | 登記完了後〜 |
| 3 | 資金調達の準備・申込 | 社長/税理士 | 登記後〜1ヶ月以内が目安 |
| 4 | 現場の準備 | 社長 | 登記後~ |
| 5 | 本格的な事業スタート | 社長 |
ステップ1:各種届出の提出
➡︎ 会社設立後すぐに必要な「官公庁への手続き」は一気に済ませましょう。
登記が完了したら、すぐに税務署・自治体・年金事務所・労働基準監督署・ハローワークなどに対して、必要な書類を提出する必要があります。
これらの手続きは提出期限が定められているため、早めに取りかかることが重要です。
業種によっては、許認可の申請や、届出が必要となります。忘れずに進めていきましょう。
✅ 主な届出一覧(法人設立後)
| 提出先 | 届出書類の例 | 誰が対応? | 期日 |
|---|---|---|---|
| 税務署 | 法人設立届出書 | 税理士 または社長 | 設立登記から2ヶ月以内 |
| 青色申告の承認申請書 | 税理士 または社長 | ①最初の事業年度終了の日の前日 ①②のいずれか早い日 | |
| 給与支払事務所等の開設届出書 | 税理士 または社長 | 事務所開設日から1カ月以内 | |
| 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 税理士 または社長 | 特例を受けようとする時のみ提出(必須ではない) | |
| 都道府県税事務所 | 法人設立届 | 税理士 または社長 | 設立登記から1ヶ月以内 |
| 市区町村 | 法人設立届 | 税理士 または社長 | 設立登記から1ヶ月以内 |
| 年金事務所 | 健康保険・厚生年金の新規適用届 | 社長 | 事実発生から5日以内 |
| 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 社長 | 事実発生から5日以内 | |
| 労働基準監督署 | 労働保険関係成立届 | 社長 | 労働者を雇用した日から10日以内 |
| 労働保険概算保険料申告書 | 社長 | 労働者を雇用した日から50日以内 | |
| ハローワーク | 雇用保険適用事業所設置届 | 社長 | 労働者を雇用した日から10日以内 |
| 雇用保険被保険者資格取得届 | 社長 | 労働者を雇用した日の翌月10日まで(入社都度) |
💡注意
これらの届出は、提出が遅れると税務上の優遇を受けられなくなったり、保険証の発行が遅れたり、後から追って納付や修正が必要になるなど、思わぬトラブルにつながることがあります。
税理士と顧問契約を結んでいれば一括でサポートしてもらえるので、起業後の負担を大きく減らすことができます。
ステップ2:法人口座の開設
➡︎ 資金の管理・取引の基盤となる、法人の“財布”を整える
法人の口座開設の申込をしましょう。
法人の口座開設には、一定の審査があり、1~2週間程度時間がかかります。
口座開設には、以下の書類が必要です。
・登記事項証明書(登記簿謄本)原本
・定款
・法人印鑑証明書
・会社実印・銀行印
・代表者の本人確認書類
・代表者の印鑑証明書
・会社の事業内容が分かる資料(パンフレットやHPを印刷したものなど)
※詳しくは、各金融機関へ確認してください。
最近では、法人の口座開設審査が厳しくなっており、事業の実態が説明できないと断られるケースもあります。あらかじめ事業概要書やホームページなど、説明できる資料を用意しておくと安心です。
法人口座の選び方や開設方法について詳しくはこちらの記事で解説しています。
▶法人の銀行口座開設ロードマップ【全4フェーズ】
ステップ3:資金調達の申込
➡︎ 「必要ない」と思っても、資金には余裕を持って備えるのが正解です。
「自己資金で足りているから大丈夫」と思っていても、事業を安定して運営していくには、手元資金に“余裕”を持っておくことが非常に重要です。
会社は、売上が出なくても、家賃や人件費、仕入れなどの固定費が発生します。
キャッシュが尽きた瞬間、黒字でも会社は倒れてしまいます。
特に、融資を前提に開業を考えている方は、早めの準備が必須です。
以下のようなケースに該当する場合は、設立後ではなく、設立前〜設立と並行して専門家に相談しながら資金調達の準備を進めるのが望ましいでしょう。
・融資の実行を待ってから開業したい(資金が入らないと動けない)
・店舗の内装工事や設備投資に多額の初期費用がかかる予定
・採用や広告など、開業前に一定の運転資金が必要になる
・自己資金だけでは不安で、資金に“余白”を持たせておきたい
融資の審査や着金に想定以上の時間がかかることもあるため、早期の行動が経営の安定に直結します。
創業時に活用できる主な資金調達制度は以下の通りです。
✅ 創業時に活用できる主な資金調達制度
| 制度名 | 概要 |
| 日本政策金融公庫「新規開業資金」 (創業融資) | 政府系金融機関の実施する、代表的な創業支援制度。無担保・無保証人で最大7,200万円。 |
| 銀行や信金が窓口となる「信用保証協会付き融資」(制度融資) | 地方自治体+民間金融機関の連携による創業支援型融資。 利子補給や保証料補助がある場合も。 |
✅ 専門家のサポートで成功率アップ
創業融資や補助金の審査は、書類の完成度と内容の現実性が重視されるため、独力で準備すると見落としや誤解も起きやすくなります。
そのため、資金調達に不安がある場合は、税理士などの専門家に相談して、早めに準備を進めるのがポイントです。
融資に通るかどうかは「準備段階」で決まると言っても過言ではありません。
専門家のサポートがあれば、申請書類の完成度が上がり、融資成功の可能性も高まります。
日本政策金融公庫の創業融資について詳しくはこちら
▶日本政策金融公庫の創業融資|保存版完全ガイド
ステップ4.営業開始を見据えた“現場の準備”を進める
➡︎ スムーズな事業のスタートのために、設立と並行して“現場の準備”を進めましょう。
実際に営業を開始するためには、事業の現場を動かすための実務的な準備も欠かせません。
ここでは「営業開始のための具体的な準備項目」を整理しておきます。
✅ 営業開始までに整えておきたい実務準備リスト
| 分野 | 準備内容 | 補足・ポイント |
| オフィス・店舗関連 | 賃貸契約・内装工事・看板・什器など | 工期のかかるものは早めに発注 |
| 設備・IT環境 | パソコン・ネット回線・プリンター・POSシステムなど | パソコンが必要な場面は意外と多い。業務用に1台は用意を。 |
| 業務ツール | 請求書・見積書の雛形、契約書テンプレートの整備など | 初回取引で慌てないために、ひな形を事前に準備。業種に合った契約書は専門家のチェックを受けると安心。 |
| 資金管理体制 | 法人クレジットカード・会計ソフト・経理業務 | 事業とプライベートを明確に分ける。口座・カード・現金の使い分けルールを最初に決めておく。 |
| 人材・労務 | 採用活動、雇用契約書、就業規則の整備など | 雇用を予定している場合は、トラブル防止のためにも社労士のサポートを受けるのがおすすめ。 |
| ブランディング | ロゴ、名刺、封筒、会社案内、HP・SNS開設など | 名刺やHPは信用づくりの基本。営業や融資の場面でも効果を発揮します。 |
※注意ポイント
飲食業、美容業、医療・福祉、旅館業などは「店舗設備が整ってから」でないと営業許可が出ません。
開業スケジュールを立てる際は、「許可取得にかかる期間」も見越して、設立前から保健所や専門家に相談しておくのが鉄則です。
ステップ5:本格的な事業スタート
➡︎準備が整ったら、いよいよ営業開始! でも“完璧”じゃなくて大丈夫です。
法人登記が完了し、届出や資金調達、設備や人材の準備も整ったら、いよいよ本格的な営業活動のスタートです。
ここまでの準備がしっかりできていれば、初日からスムーズに事業を進められるはずです。
ただし、どれだけ準備をしても、実際に動き出せば“想定外”の出来事はつきものです。
むしろ、それが普通。
完璧を目指すよりも、「まずやってみて、必要に応じて改善する」くらいの柔軟さが成功への近道になります。
営業開始直後は、こんな点に意識を向けてみましょう。
・お客様の反応や売上データを見ながら、柔軟に方向修正する
・資金繰りや日々の実績を記録し、経営状況を“見える化”する
「設立」はゴールではなく、ビジネスのスタートラインです。
準備は大切ですが、最初から完璧を求めすぎず、一歩ずつ改善していく姿勢が成功を引き寄せます。
あなたのビジネスが、確かなスタートを切れることを心より願っています。
3. まとめ|「今やるべきこと」がわかれば、会社設立はこわくない
会社設立は、手続きそのものも大事ですが、「いつ・何を・誰と進めるか」を整理しておくことが成功への第一歩です。
この記事では、
・会社設立の全体スケジュール
・専門家との連携のポイント
・設立後に必要な届出や準備
・営業開始に向けてやるべき実務タスク
を時系列で整理してご紹介してきました。
特に重要なのは、「登記が完了したら終わり」ではなく、そこからがスタートだという意識です。
会社をスムーズに立ち上げるためには、資金調達や労務・IT環境など、さまざまな準備を並行して進めていく必要があります。
✅ 記事を読んだあなたが、今できるアクション
・まずは、会社の基本情報(名称・所在地・資本金など)を書き出してみる
・会社設立に詳しい専門家(特に税理士)に相談してみる
・営業開始に向けて必要な準備リストを、自分の事業にあわせてチェックする
完璧な準備は必要ありませんが、正しい順番で、必要なことを抜け漏れなく進めることが、後の安心と成功につながります。
会社設立は、人生の大きな一歩。
あなたの新しいスタートが、力強く、そして確かなものになるよう応援しています。

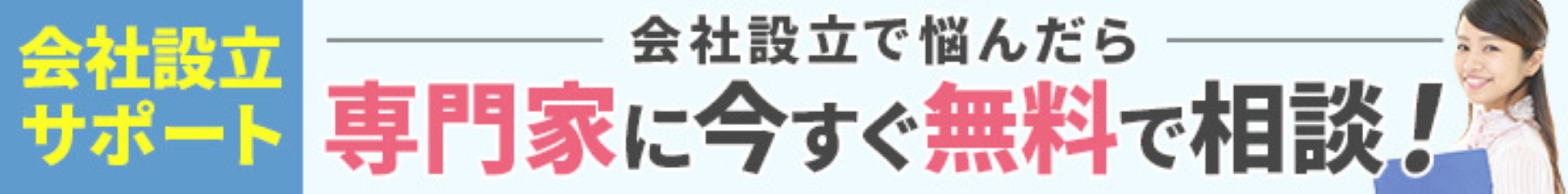
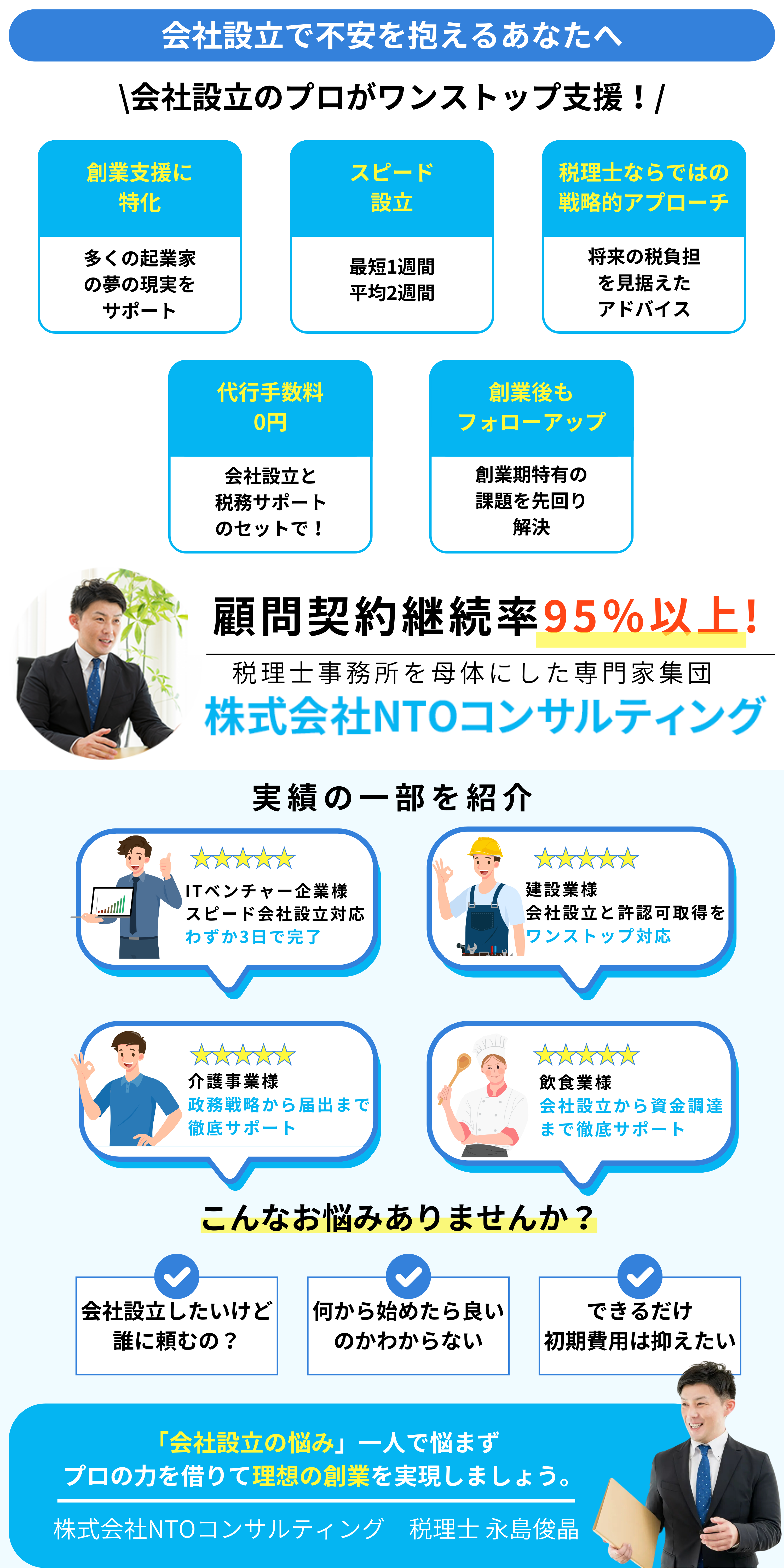
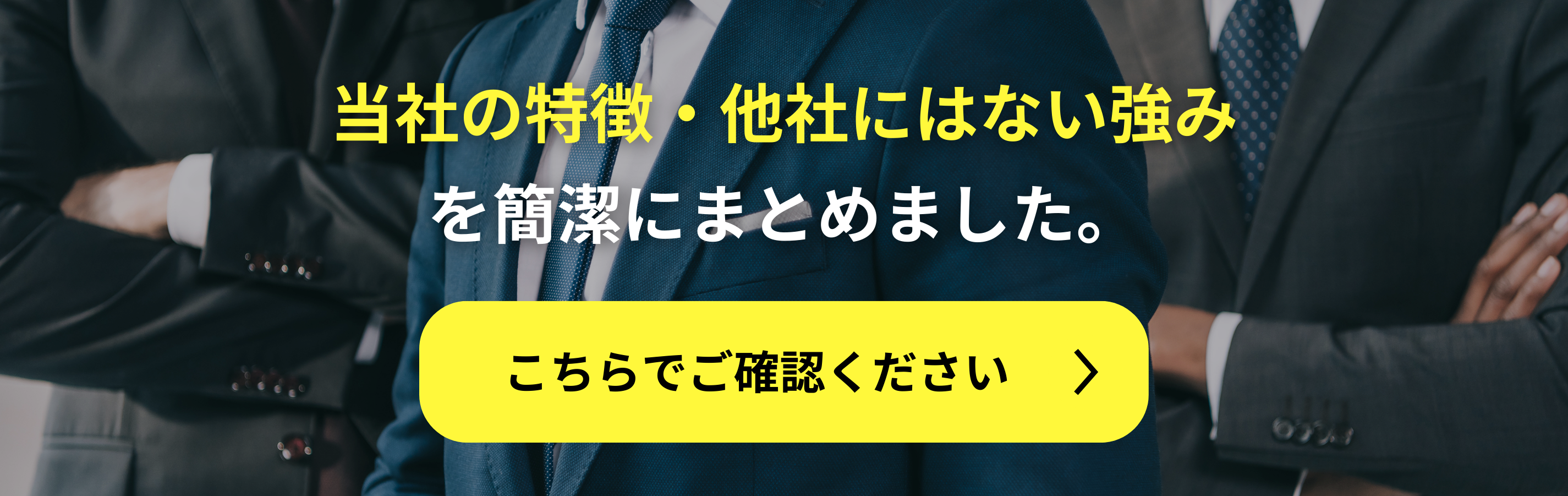
コメント