
「会社設立の“目的”って、何を書けばいいの?どこまで書けばいいの?」
多くの方がなんとなくスルーしがちなこの項目。実は、設立後の融資・許認可・営業活動すべてに影響する、最も重要な要素のひとつです。
この「目的」があいまいだったり、不備があると、
・許認可が取得できず営業を開始できない
・融資の審査で不利になる
・銀行口座の開設を断られる
といった深刻なトラブルにつながる可能性があります。
さらに、あとから修正しようと思っても、「定款変更」や「登記変更」といった手続きが必要になり、時間も費用もかかってしまいます。
だからこそ、最初に正しく、将来を見据えて「目的」を設定することが不可欠です。
この記事では、「会社の目的とは何か?」という基本から、事業内容の記載で失敗しないためのポイント、そして業種別の具体的な記載例まで、実務で役立つ内容をわかりやすく解説します。
「とりあえずそれっぽく書いておく」では済まされない“会社の土台”について、いま一度しっかり確認しておきましょう。
目次
1.会社設立の「目的」とは?──なぜそんなに重要なのか?
会社を設立する際、「会社の目的(=どんな事業をする会社か)」を必ず決めて、定款に記載しておく必要があります。
この目的は、法務局に登記され、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)にも載るため、「この会社は何をする会社か」を示す公式な情報として扱われます。
この「目的」が不明確だったり適切でない場合、次のような重大な支障が出る可能性があります。
・許認可が取得できず、事業を開始できない
例:「建設業」「人材紹介業」「古物商」などは、定款に正確な目的が記載されていなければ、申請自体が受け付けられない場合もあります。
・銀行口座の開設や融資で不利になる
目的が抽象的すぎたり多すぎたりすると、「何をしている会社なのか」が不明確になり、銀行側から敬遠されるケースがあります。
・あとから修正するには、費用も時間もかかる
目的の追加・変更には、株主総会での定款変更決議+登記申請が必要です。
所要期間は通常1〜2週間、費用は登録免許税3万円+専門家報酬で総額5〜6万円程度になることも。
だからこそ、「目的」は設立時点でしっかりと検討し、将来の事業展開も見据えて、正しく・無駄なく・漏れなく記載することがとても大切です。
「会社の目的」は、登記のための形式的なものではなく、将来の事業活動にも大きな影響を与える“会社の土台”です。
だからこそ、内容には慎重な検討が必要です。では、実際に「目的」を決める際には、どんな点に注意すべきなのでしょうか?
2.事業目的を決めるときの3つの実務ポイント
ここからは、「会社の目的」を記載するときに押さえておきたい3つの実務的なポイントを紹介します。
・将来の事業展開を見越して書くこと
・書きすぎないこと
・許認可のために必要な表現があること
これらを知らずに記載してしまうと、あとで手続きのやり直しや、融資・口座開設の足かせになってしまうことも。設立後に後悔しないために、必ずチェックしておきましょう。
2-1.将来の事業も含めて記載する
今すぐ始める事業だけでなく、将来的に展開を検討している事業もあらかじめ目的に含めておきましょう。
なぜなら、あとから追加すると定款変更・登記手続きが必要になり、余計な手間とコストが発生するからです。
(例)カフェを開業予定、ゆくゆくは自家製の焼き菓子をネット販売したいと考えている。
→「インターネットを利用した通信販売業」も記載しておく。
【補足】定款にない事業をすると罰則はある?
罰則はありませんが、実務上は要注意です。
法律上、定款に記載されていない事業を行っても違法にはなりませんが、融資・許認可・補助金等の申請などで支障が生じるリスクが高いです。
・銀行融資の審査で「登記目的にない=実体不明」と判断され、否決される
・許認可の申請で「目的記載が必須」とされ、申請が通らない
・補助金や助成金の審査で「対象外」とされ、不採択になる
・契約や法人登記に関わる行政手続きで、やり直しを求められることがある
2-2.“書きすぎ”はNG──10個以上は要注意
将来的に展開を検討している事業は目的に入れておくべきと前述しましたが、将来を見越してあれもこれもと盛り込みすぎるのも考えものです。
事業目的を書きすぎると「何をしている会社かわからない」と判断され、銀行や取引先からの信用を損なうリスクがあります。
金融機関の法人口座開設・融資審査においても、「目的の多さ」は警戒項目の一つです。
多くても7〜8個程度に収め、「主軸となる業務内容」が明確になるように心がけましょう。
2-3.許認可が必要な業種は、正確な文言が命
許可や登録が必要な事業を始める場合は、申請先が求める表現で事業目的を定款に記載する必要があります。
そして、この記載ルールは行政庁によって異なることがあるため、注意が必要です。
たとえば同じ「建設業」でも、都道府県ごとに指定されている表記が違う場合があります。
目的の書き方が不適切だと、許可申請が通らず、開業時期が遅れてしまうこともあるのです。
そのため、申請前に必ず所管の行政庁の要件を確認し、少しでも不安があれば専門家に相談することをおすすめします。
【許認可が必要な業種の一例】
・建設業
・人材派遣業
・人材紹介業
・古物の売買
・飲食店
・酒類の販売
・不動産業
・運送業
・介護事業
・民泊、簡易宿泊所
3.【業種別】目的記載の事例集
ここでは、さまざまな業種において実際によく使われている「目的」記載の具体例をご紹介します。
それぞれの業種で必要な記載や、許認可に対応した文言なども含めて紹介していますので、ご自身の事業にあわせてカスタマイズしてお使いください。
◆ IT・Web関連業
将来の展開も見据えて、周辺業務も含めておくのがおすすめです。
・ホームページの企画、制作及び運営
・ソフトウェアの開発、販売及び保守
・インターネット広告業
・クラウドサービスの提供
・各種コンテンツの企画及び配信
・上記に付帯関連する一切の業務
◆ 小売業・EC(ネットショップ)
物販系ビジネスでは、実店舗+オンライン販売両方を記載しておくと、将来の展開にも対応しやすくなります。
・食品、衣料品、日用品雑貨の販売及び輸出入
・インターネットを利用した通信販売業
・古物営業法に基づく古物の売買
・オリジナル商品の企画及び販売
・上記に付帯関連する一切の業務
◆ 飲食業
店舗展開だけでなく、キッチンカー・食品開発・フランチャイズ化なども見据えておくと◎。
・飲食店の経営
・移動販売車による飲食物の提供
・食品の製造、加工及び販売
・食品の企画及びプロデュース業務
・フランチャイズチェーンシステムの構築及び運営
・上記に付帯関連する一切の業務
◆ 建設業
建設業の許可申請には、定款に適切な目的記載が必要不可欠です。
・建築工事の設計、施工及び請負
・内装仕上工事業
・土木工事業
・建築資材の販売及び輸出入
・住宅リフォーム業
・上記に付帯関連する一切の業務
◆ 美容・健康関連
・美容院及び理容院の経営
・エステティックサロンの運営
・パーソナルトレーニングジムの経営
・健康食品・サプリメントの販売
・美容機器の販売及びレンタル
・上記に付帯関連する一切の業務
◆介護事業
介護保険法や障害者総合支援法に基づく事業は、行政庁の指定する文言を正確に記載することが重要です。
・介護保険法に基づく訪問介護事業
・介護保険法に基づく居宅介護支援事業
・通所介護(デイサービス)及び短期入所生活介護事業
・障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業
・高齢者向け住宅及び有料老人ホームの運営
・福祉用具の貸与・販売事業
・上記に付帯関連する一切の業務
◆不動産業
宅地建物取引業の免許申請や建物賃貸業を想定し、事業形態に応じて柔軟に構成するのがポイントです。
・不動産の売買、賃貸、仲介及び管理
・不動産の企画、開発及びコンサルティング業務
・建物のリフォーム及びリノベーションの企画、設計、施工
・宅地建物取引業
・不動産に関する各種情報提供サービス業
・上記に付帯関連する一切の業務
「上記に付帯関連する一切の業務」は、忘れずに最後に入れるようにしましょう。
この文言を入れておくと、定款に記載していない事業でも関連する事業であれば出来るようになります。
ここで紹介した事業目的の文言は、あくまで参考例です。
特に許認可が必要な事業を行う場合は、申請先ごとに求められる表現や要件が異なることがあるため、必ず事前に専門家に相談することをおすすめします。
定款の文言が不適切だと、申請が受理されず、開業スケジュールが遅れるなどのリスクもあるため、慎重な対応が重要です。
3.まとめ|「会社の目的」は“設立の土台”──正しく記載して、トラブルを防ごう
会社設立において「目的」の記載は、ただの形式ではなく、今後の
・許認可の取得
・銀行口座の開設
・融資の審査
・補助金・助成金の審査
など、あらゆるビジネスの土台となる極めて重要な要素です。
もし不明確な記載や記載漏れがあると、「許認可が通らない」「融資が否決される」「あとから修正費用がかかる」など、事業運営に支障が出る深刻なリスクがあります。
本記事では、
・「目的」とは何か、その重要性
・書くときの3つの実務ポイント(将来性・書きすぎNG・許認可文言)
・IT業、飲食業、建設業など業種別の具体例
を紹介しました。
✅ あなたの次のアクションは?
・今すぐ、自社の「目的」案を見直してみましょう
・書き方に不安がある方は、専門家に相談するのが安心です
将来の事業展開まで見据えた“無駄なく・漏れなく・正確な目的記載”で、安心してスタートを切りましょう!

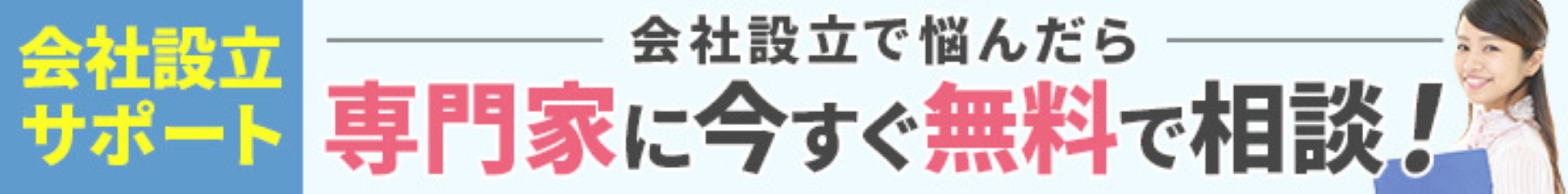
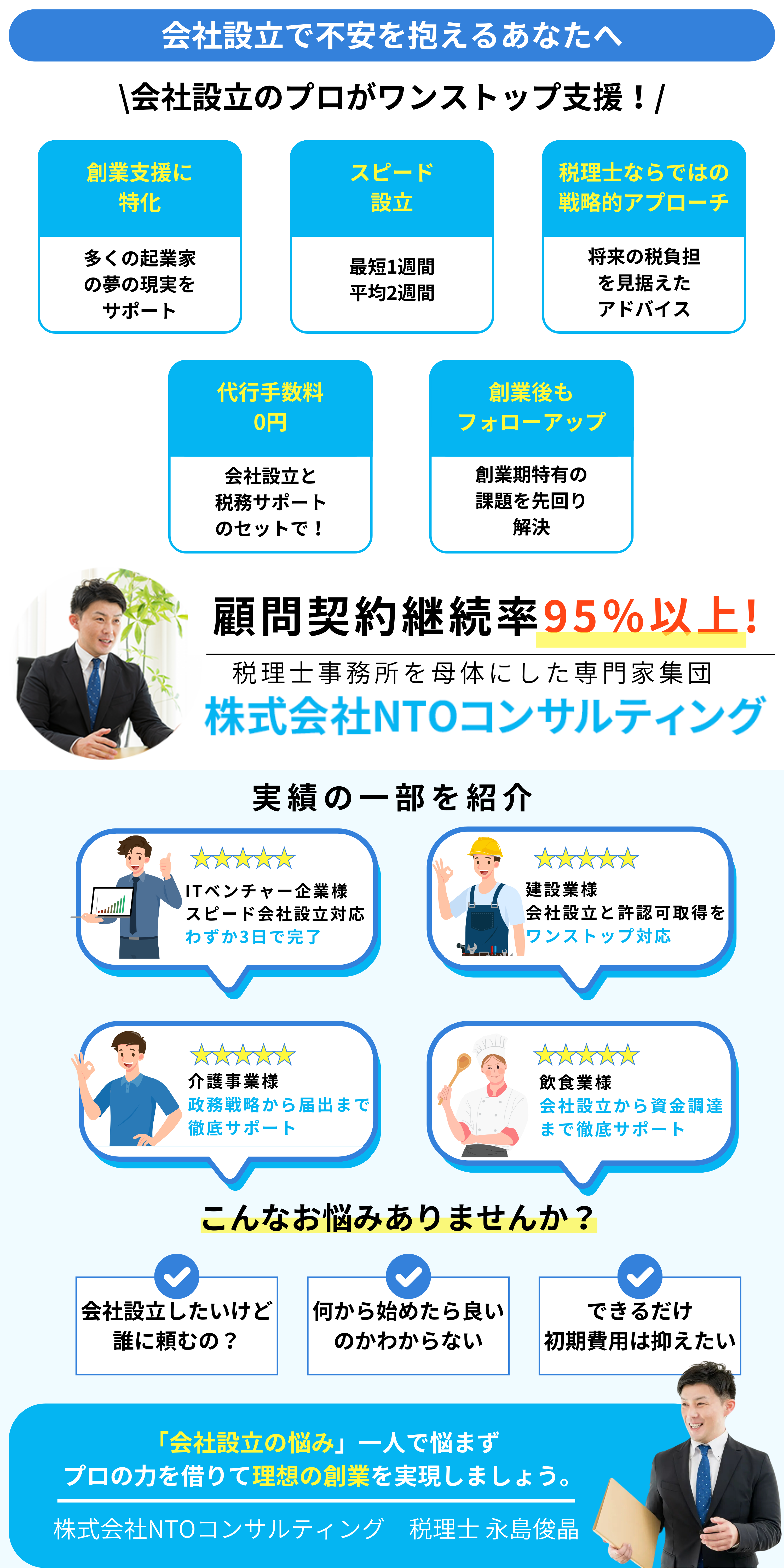
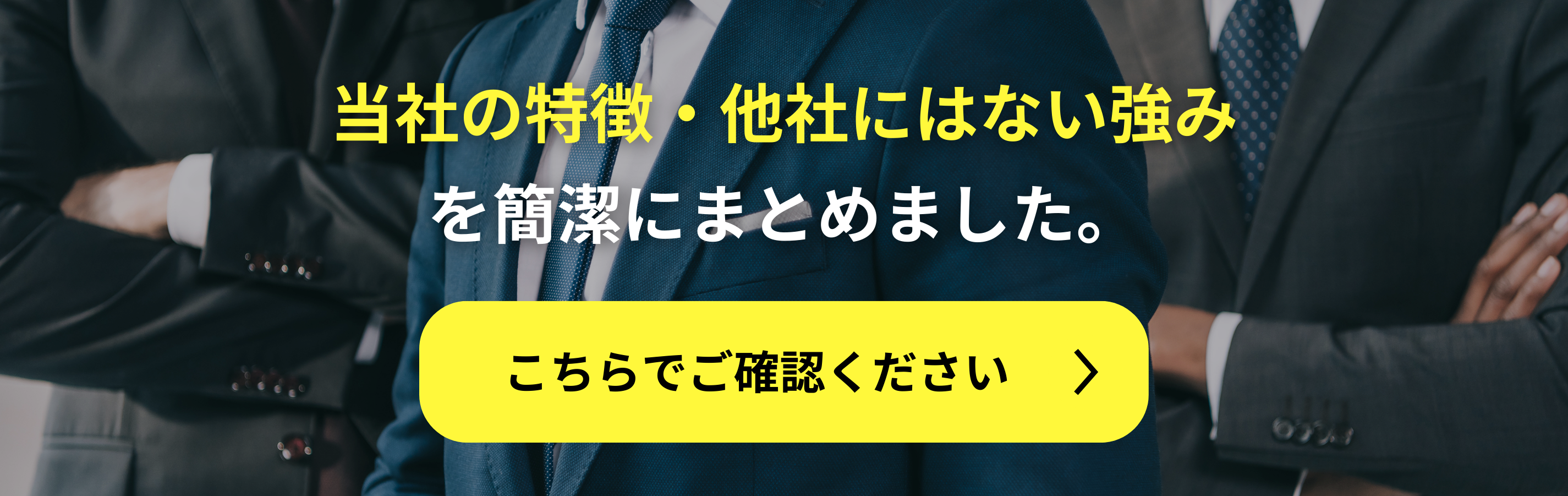
コメント